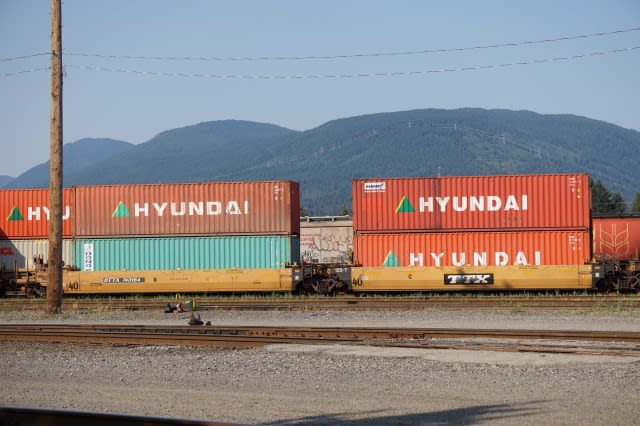2016年10月10日。
9月28日から10月10日まで、岳南電車が「mt」という商品と連携してイベントをやっていました。
mtというのはマスキングテープの商品でして、テープに柄が印刷されたものです。女性の間で特に人気が高く、雑貨の装飾、部屋の模様替え、芸術作品の制作といった本来のマスキングテープの使用法を超えた使われ方がされています。
マスキングテープを飾りに使うのか・・・と、プラモデル塗装の塗り分けという元来の使い方をしている私からすると最初は唖然としたものですが、それは固定観念というものでしょう。何がどう売れるようになるのか分からないものです。
これを製造している会社は全国あちこちでイベントを起こしているようで、今回の岳南電車もそれのひとつのようです。
mt自体はそれほどでも・・・でしたが、開催期間限定で電車にラッピングがされるようですし、こういう時でもないと岳南電車に乗りに行かないと思ったので行ってみることにしました。
いつも通り東海道線で吉原駅まで乗ります。

岳南電車のホームにはちょうどmtラッピングされた7000形7002号が停まっていて、到着直後にあっさりと第1目標撃破です。
ラッピングの柄は今回のイベント用に新たに起こした3種類のマスキングテープの柄で、赤と緑が岳南電車の電車の色(7000形と8000形だ)、青は富士山を基にした色なのだそうな。
センスのあるデザインで、2週間足らずのイベントだけで終わらせるには惜しいなと思いました。
車内はmt目当ての乗客(ほとんど女性)でいっぱいで、立ち客もそこそこ出るほどでした。普段はガラガラなんでしょうから、mtの人気と集客性の高さにびっくり。

まずは電車を撮影することにしていたので、神谷駅で下車。なおmtの会場は途中の岳南富士岡駅でして、そこでほとんどの客は降りていきました。

神谷駅から岳南江尾駅方面へ少し歩いたところで折り返し吉原行きのmtトレインを撮影。前パン先頭で撮りたかったので満足。
単行、前パン、スカート無し、湘南顔というのは21世紀ももうすぐ5分の1を消化という現代にしてはさすがに古臭いものでして、そこがまた魅力なわけですが。

次にやってくる7001号の岳南江尾行きも撮影。井の頭線の復刻塗装車でした。第2目標もこれで撃破。

そのまま岳南江尾駅まで乗車。隣のホームでは8000形が昼寝。

たまにはこんなお写真も。

上記の通り7001号は2016年3月から京王井の頭線3000系の復刻塗装に塗られています。これは7000形が3000系からの改造車だからですね。
パッと見は井の頭線そのものなんですが、細かい考証を見ていくとちぐはぐだなという部分もあります。
車体側面の帯は濃淡2色の太帯ですがこの帯に塗られていたのは、車体更新されて前面窓が側面まで拡大されたパノラミックウィンドウの更新車でして、更新前の前面を持つ7000形ならば本来は1色の細帯が正解に近いです。
ただこれは塗り替えられる前に元々塗られていたオレンジ帯の幅に合わせた処理だと思います。そもそもそれほど目くじら立てるほどの事ではないので、こういうのはノリと勢いを愉しめばいいんです。

前面窓下には井の頭線時代に付けられていた行先表示器をステッカーで再現しています。これがあると引き締まります。岳南電車もこの部品付けておけばよかったのになぁと(7000/8000形の前面は既存車の流用ではなく新しく製作したものを使っているのだ
今は水色で走っていますが、今後検査で塗り替える度に違う色に塗ってくれると面白いしまた行かなきゃとなると思います。

岳南江尾駅駅舎。
最近、一部の駅でパークアンドライドを始めていて、駅前に貸駐車場が出来たという駅が増えました。
電車に乗ろうにも家から駅までは車でいかんとキツイというのは結構あると思うんで、いい施策だと思います。この日も満車までは行きませんが利用者も少しいましたかね。

日本一市民のキモチが盛り上がっている駅・・・だそうな。お、おう・・・。
この駅は終点だったはずなのにいつの間にか沼津どころか銀河系方面へ延伸してるし、銀河鉄道もついに無煙化したんだなぁとシミジミ。
この後は折り返しの電車に乗って、mt会場の岳南富士岡駅へ。

着きました。そういえば貨物輸送が廃止されてなんやかんやした後に降りるのは初めてだったかしら。

ホーム。広告看板は全部mt。

第3目標のマスキングテープを貼られたED40形3号機。

他にもここには岳南鉄道時代の貨物輸送に使われていた電気機関車が置かれています。これはED40形2号機。

その隣には古豪ED50形1号機。あとはED29形もいるんですがイベントのテントに隠れてろくに撮影できず。
どれもずっと野ざらしで置かれているので相応にくたびれています。現状のままだと遅かれ早かれ解体というのは十分あり得ます。なんとかできることがあればなぁ・・・とは思うんですけどもね。

構内にある車庫では7000形が昼寝。ここの車庫はこじんまりと可愛くて好きです。

駅舎も看板がmt仕様に。普通におしゃれだし、ずっとこのままでも良いくらいです。
こんなところで今日はここまで。
後編へ→