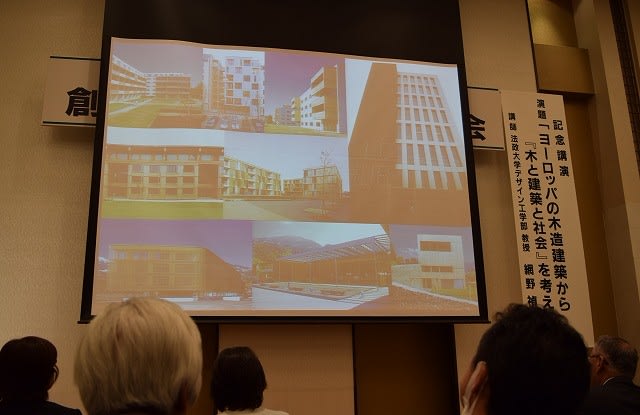4月7日に、山形県建築士会女性部の役員会が、酒田市の勤労福祉会館で行われた。ここに来るのは何年ぶりだろう。以前は建築士会やキープランで勉強会をしていたものだが。
役員会では、規定通りに事業報告と決算書、来年度の事業計画と予算書を議題に載せ議論した。県内支部の建物を巡る「ふるさと探検」も27回を終え、そろそろ県内から県外の施設に目を向けたらと言う訳で卒業し、秋期研修と合わせて大きな行事にしようと計画することになった。その計画は、副委員長のブロックで行い、皆で応援すると取り決めた。その計画とは別に、酒田支部は福島への見学会の計画を立てている。

全国女性建築士連絡協議会で、各県毎に「後世に残したい和の空間ガイドブック」の製作の為、3物件を提出することになった。庄内だけでなく全県で推薦したいのだが、相変わらず先頭だって動く人がなく、委員長さんがまとめてくれた。その中の庄内地区は本間美術館の清遠閣と鶴舞園を取りまとめたのだが、庭園から借景に鳥海山を臨む写真がなくて、会議が終わった後に3人で本間美術館へ行くことになった。私も年会費を払えるのに好都合と着いていった。

年会員になると、お茶券(抹茶と干菓子)が1枚貰える。3枚も貯まった券を今回消費した。

池のほとりで見かけたゼンマイ。春だなと思う。

見にくいだろうが、玄関の先の梅。何年経った物だろうか、よくこんな姿で蕾を付けることが出来るものかと感心する。

庭園の鶴舞園は国指定の名勝になっており、文化10年(1813年)本間家4代目の本間光道が鳥海山を借景にした池泉回遊式庭園を、冬期間の港で働く人の失対対策事業として実施した。日和山の築山も庄内浜の黒松の植樹も、本間家は公益として行ったのも知られている。本来なら行政が行う事業なのだろうと思う。庭園を造った庭師の名は、酒田の鶴舞園、奇暢亭庭園、清亀園を作った名庭師の山田挿遊(やまだ・そうゆう)だと、過去記事の酒田景観町歩きに書いてあった。
そして酒井藩主が領内巡視をする際の休憩所として造られた清遠閣は、酒田の迎賓館として昭和天皇が皇太子の頃にも宿泊された建物である。使用されている材料と良い、京風の繊細な造りは、次世代の建築を学ぶ者のお手本となると思う。いつ見ても、清遠閣の軒先の鋭さは美しい。


戸袋の引き手は、良く見ると奥が七宝焼きになっているのではあるまいか。細かい細工を見つければ見つけるほど、なるほどと感心する建物だと思う。
鳥海山がはっきりと映っている庭の写真は、私のブログからは見つからない。滅法良い天気で、青空がはっきりと白い山と分かれている状態でないと見にくい。清遠閣の違い棚に飾っていた写真は、その天気の良い日に、かなり高い位置で、脚立にでも載って撮影したのかもと思う。それに、鳥海山を横切る電線は、う~~~と邪魔だ。まぁ根本は、庭の樹木が育ちすぎたからなのだが。