 理事長 丸井一郎
理事長 丸井一郎です。
★ 四国の谷筋のこと ★
もう35年ほど昔に、
愛媛大学で文化人類学を研究する
先輩同僚から聞いた話です。
その後関連の文献を調べてみても
ぴったり合うものが見つかりません。
あやふやな話で申し訳ないのですが、
この地に住んでみた実感と良く合うので紹介します。
四国、とくにその山間には、
かつて何千という「谷筋の仕組み」があって、
そこで人びとは、ほぼ自給をしながら
何百年の時を過ごしてきた。
山の中腹あたりには段々畑が、
地形が許せばやがて流れ下る小さな水路と棚田が広がる。
尾根に近いところには材になる樹木が、
やや低く里山では薪やキノコや薬草や木の実などが、
畑と田んぼより下の谷川では鮎やウナギやエビやカニなどが
一年の巡りを通じて糧(かて)となる。
季節になればシシやシカもツグミなもとれた。
奥山も里山も野も畑も川も多様な資源を提供した。
それより上にはもう自然林しかない棚田では、
森を抜けてきた水の恵み(ミネラルや有機質など)で、
あまり苦労せずに稲を育てることができた。
米の収量は十分ではないが、畑の芋(サツマイモ、田芋=里芋)や
陸稲(おかぼ)、アワ、ヒエ、キビ、タカキビ、豆類などを
上手に組み合わせて食した。
谷川には、文字通り果物が「あゆる(落ちる)」ごとくに、
アユ(あいのうお)が落ちて(=流れて)くる。
梁(やな)をしつらえれば大量に取れる(やなのせ)。
この谷の仕組みは、
わずかなタンパク質(塩づけや焼いたり乾燥した海の魚)と
手工業品(刃物など)を外から補充すれば、
ほぼ永久に持続できた。
屋敷は多湿で災害の多い川沿いよりは、
むしろ尾根に近く建てられた。
尾根つたいに行けば、川沿いの低湿地で難渋するより
快適かつ迅速に行き来ができる。
修験者などはこの尾根の道を活用した。
より広大な土地にまばらに居住地が散在する
日本列島の東部・東北部とは異なり
、四国では山間にあっても集落が一定の密度で見られた。
ということなのですが、
これに加えて「お城下」など町(佐川や安芸や中村など)、
さらに湊(港)や浦々のことを考えれば、
土佐をはじめ阿波・伊予・讃岐の昔の暮らしが思い描けるでしょう。
「お四国さん」(四国八十八ケ所)の巡礼達も浦や町だけでなく
、山間に確実に点在する集落の人びとの援助を受けて、
無事に結願(けちがん)できたのではないでしょうか。
関東生まれの義父が生前に
「四国には、山間でもいたるところにちゃんとした百姓屋敷があるもんだ」
との感想を述べていました。
弘法大師はそのへんの条件をも見定めて、
千年以上持続できるシステムを創設したのではないか、
と考えたくなります。
ちなみに結願御礼「上がり」の高野山は和歌山県ですが、
昔の制度では、四国と和歌山(紀州)とで
「南海道」をなすとされていました。
残念ながら今日では、自活し持続する
「谷筋の仕組み」は、絶滅しました。
近代化、産業化、開発主義(による地域間格差)のせいです。
とはいえ今日でも、かつての伝統の暮らしをしのばせて、
山と町と浦が出会うのが、
1690(元禄3)年創設の「土佐の日曜市」です。
観光化の弊害も(大いに)あるものの、
これは言うならば(少なくとも一部は)生きた民俗博物館です。
今風の食材や食べ方ももちろん大切ですが、
私たちの生活の場である四国(土佐)の風土の中で
伝承されてきた食べ方暮らし方に学ぶことは、
大切な視点だと思います。
負荷(環境・エネルギー)の少ない、
持続可能で充実した暮らしを考える上でも。














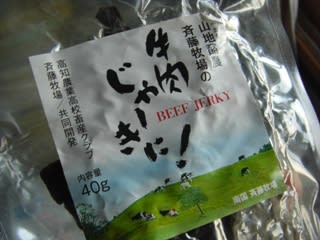

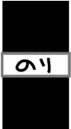 「本物の海苔のおいしさを伝えたい」
「本物の海苔のおいしさを伝えたい」 ◆寿司はね焼きのり
◆寿司はね焼きのり ◆カット焼海苔青のり混り
◆カット焼海苔青のり混り ◆味付けおかず海苔
◆味付けおかず海苔 ◆韓国風味付塩焼海苔
◆韓国風味付塩焼海苔 ◆味のりふりかけ
◆味のりふりかけ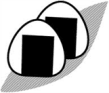 今週提出の注文書で注文できます。
今週提出の注文書で注文できます。


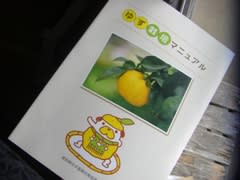

 山の温泉宿から ~人気レシピ~
山の温泉宿から ~人気レシピ~



 ごま油をナベに入れ、水切りしたイタドリを炒める。
ごま油をナベに入れ、水切りしたイタドリを炒める。 お好み焼きに入れるふし粉を少し入れ、
お好み焼きに入れるふし粉を少し入れ、
 小幡 尚
小幡 尚




 梼原町 谷川農園の谷川徹です。
梼原町 谷川農園の谷川徹です。


 会員Hです。
会員Hです。 理事長 丸井一郎です。
理事長 丸井一郎です。



