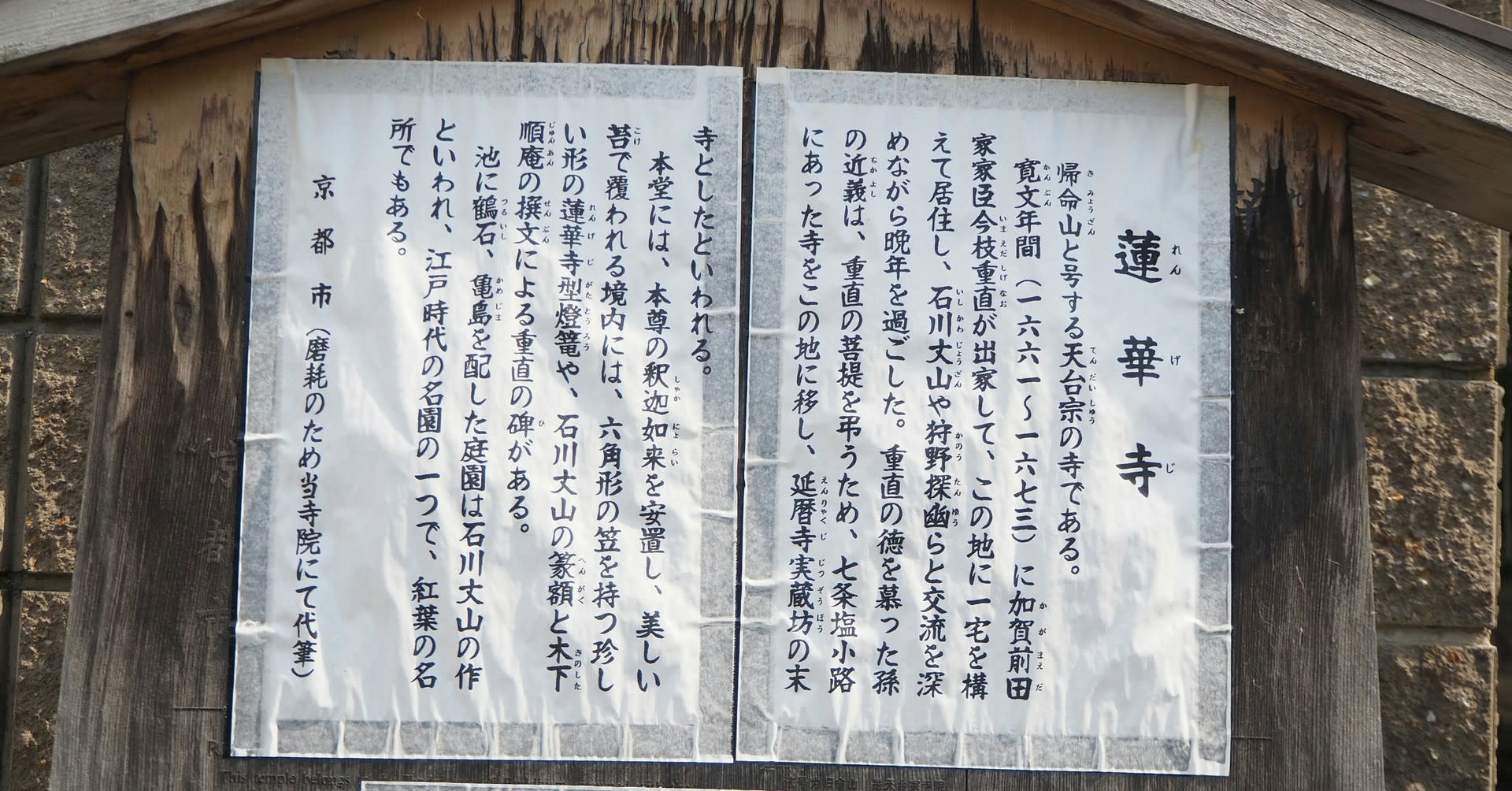まだ梅雨入り宣言が出されていないですが、朝から曇天で雨予想の朝の散策です。
京都の五花街のうち四つは祇園にありますが、北野天満宮の東門前町にあるのが上七軒です。
歴史は五花街のなかで最も古く、起源は室町時代に遡ります。
北野天満宮が火災にあった際に、その再建で残った木材を使って七軒の茶屋を建てました。
後に太閤秀吉が北野で大茶会を開いたとき、七軒の茶屋で出された団子に感動し、団子を商う特権と茶屋株を与えました。
今も上七軒のお茶屋の軒下を飾る提灯は「つなぎ団子」です。
西陣に近く、織物産業が好景気のときは、多くの旦那衆で賑わいました
現在も10軒ほどの茶屋と20数名の舞妓、芸妓さんが在籍し、春には「北野をどり」が開催されます。
舞踊は花柳流(はなやぎりゅう)。春の公演は「北野をどり」、秋には「寿会」が開催されます。
紋章は秀吉のエピソードにちなみ、まるく交差する五つ団子。
天満宮東門に近いところから東に(北野天満宮東参道)歩いていきます。今にも雨が降りそうです。
以前は電柱が不粋だったのですが、地下に埋設され、石畳です。
先日祇園新橋を投稿しましたが。電柱の不粋さには本当に残念でした。
往時より軒数は減りましたが、二階建ての茶屋形式の町屋が並び、二階から簾が下がる落ち着いた茶屋街です。







上七軒歌舞練場入口

お店マップ


くろすけ





お茶屋

面白い表札 夜明かりが点ると風情あるでしょうね。




お茶屋




ガスメーター、エアコン室外機も隠しています。




インターホンもこのように





画像が多くなりましたので続きます。