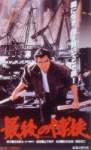タイトルの『最後の博徒』というのは、松方弘樹が扮した主役の荒谷政之のことで、映画はやくざの仁義を通した彼の一代記みたいなストーリーだった。広島の呉市での少年時代から始まって、石岡組の舎弟になり、大戦後、新興やくざ・山辰組との抗争に巻き込まれながらも、筋金の入ったやくざとして、男を上げていく。荒谷は呉の一匹狼・加納良三(千葉真一)とも親交を結ぶが、加納は山辰親分(成田三樹夫)にうまく利用され、石岡親分(梅宮辰夫)を襲って刑務所に入れられてしまう。その間、山辰組の策謀にあってついに石岡親分が殺されてしまう。殴りこみに行った荒谷も警察に捕まり、刑務所へ。出所後、荒谷は加納と手を組んでその仕返しをしようとするのだが、血で血を洗う抗争を終わらせようと仲裁に入った大親分(萬屋錦之介)に説得されて、二人とも仕返しを断念。荒谷は広島を出て、大阪へ行き、菅田組の親分(鶴田浩二)と兄弟分の契りを結んで、今度は兄貴分菅田のために一肌脱ぐ。そんなあらすじだった。
詳しく調べたわけではないが、『仁義なき戦い』の登場人物とダブっているやくざが出てきたと思う。『仁義なき戦い』で菅原文太が演じた主役の広能昌三がこの映画では千葉真一の加納良三で、金子信雄がユニークに演じた新興やくざの親分・山守義雄が、成田三樹夫の山辰信男になっていたようだ。名前も役柄も似ていたので、そう思った。
ところで、錦之助が登場するシーンはわずか三箇所。錦之助の役は、清島春信というやくざの親分で、なんだか浮世絵師みたいな名前だった。どこの地域の親分かは分からなかったが、古いタイプの侠客といった感じだった。最初に錦之助が出てくるのは、石岡親分の葬儀の時で、正装の着物を着て単身現れ、親族に挨拶すると、どことなく寂しげに去っていた。風格がある立ち姿だったが、やつれている印象は拭えなかった。この時、錦之助が言葉を交わした相手役が日高澄子で、彼女は石岡親分の年老いた母親役だったが、私の頭にはこの二人の昔の場面がよぎった。思えば、『花と龍』で、どれら婆さんの島村ギンを演じていたのが日高澄子で、また、古くは名作『弥太郎笠』で、錦之助の弥太郎と恋仲だったお雪(丘さとみ)の憎憎しい継母役が彼女だった。この継母役の日高澄子は大変印象的で、年増の色気と妖しい魅力を振りまいていた姿が私の目に焼きついている。『最後の博徒』に出演した時の日高澄子は、それから25年も経っていたが、老いてなお健在であり、素晴らしい演技を見せていた。多分、この映画で、彼女に注目した人も少ないと思うので、ぜひここに書いておきたい。
次に、錦之助が登場するのは、あらすじにも触れたが、山辰を殺そうと血気はやる荒谷(松方弘樹)と加納(千葉真一)の隠れ家へ、抗争の仲裁にやって来る場面だった。この場面の錦之助はさすがに見せ場だけあって、気迫に満ちていた。やはり単身現れ、もちろん着物姿だったが、二人の前にどっかりと腰を下ろし、諄々と説得するのだが、荒谷は承知したものの、加納の気がおさまらない。そこで、錦之助が、自分を撃ち殺してから行けと加納に迫る。この場面の錦之助のにらんだ表情が、凄かった。ここを観ただけでも、この映画を観る価値があると思ったほどである。松方弘樹も千葉真一もチンピラに見えてしまうのだから、病後とはいえ、錦之助の貫禄は段違いだった。
第三のシーンは、その足で錦之助が山辰組へ乗り込み、親分(成田三樹夫)に会長職を辞めて引退するように迫る場面だった。ここは意外にあっさりとしていて、成田三樹夫も恐れをなし、錦之助の顔を立ててすぐに承知する。
多分、錦之助の出番はトータルで10分かそこらだったと思うが、他の出演者たちとの格の違いを見せていた。
この映画の後半では、錦之助に代わって、鶴田浩二が登場するが、それこそ昔日の面影がなく、やつれ果てていた。言い忘れていたが、『最後の博徒』は、鶴田浩二の最後の出演映画だった。すでにガンに冒されていたのだろう。鶴田浩二が亡くなるのは、この映画の一年半後、62歳だった。鶴田は錦之助より8歳年上で、錦之助が東映を去った後、高倉健や池部良とともに東映仁侠映画を全盛に導いた頃のことを思うと、この映画の鶴田は、見るに忍びない姿だった。
詳しく調べたわけではないが、『仁義なき戦い』の登場人物とダブっているやくざが出てきたと思う。『仁義なき戦い』で菅原文太が演じた主役の広能昌三がこの映画では千葉真一の加納良三で、金子信雄がユニークに演じた新興やくざの親分・山守義雄が、成田三樹夫の山辰信男になっていたようだ。名前も役柄も似ていたので、そう思った。
ところで、錦之助が登場するシーンはわずか三箇所。錦之助の役は、清島春信というやくざの親分で、なんだか浮世絵師みたいな名前だった。どこの地域の親分かは分からなかったが、古いタイプの侠客といった感じだった。最初に錦之助が出てくるのは、石岡親分の葬儀の時で、正装の着物を着て単身現れ、親族に挨拶すると、どことなく寂しげに去っていた。風格がある立ち姿だったが、やつれている印象は拭えなかった。この時、錦之助が言葉を交わした相手役が日高澄子で、彼女は石岡親分の年老いた母親役だったが、私の頭にはこの二人の昔の場面がよぎった。思えば、『花と龍』で、どれら婆さんの島村ギンを演じていたのが日高澄子で、また、古くは名作『弥太郎笠』で、錦之助の弥太郎と恋仲だったお雪(丘さとみ)の憎憎しい継母役が彼女だった。この継母役の日高澄子は大変印象的で、年増の色気と妖しい魅力を振りまいていた姿が私の目に焼きついている。『最後の博徒』に出演した時の日高澄子は、それから25年も経っていたが、老いてなお健在であり、素晴らしい演技を見せていた。多分、この映画で、彼女に注目した人も少ないと思うので、ぜひここに書いておきたい。
次に、錦之助が登場するのは、あらすじにも触れたが、山辰を殺そうと血気はやる荒谷(松方弘樹)と加納(千葉真一)の隠れ家へ、抗争の仲裁にやって来る場面だった。この場面の錦之助はさすがに見せ場だけあって、気迫に満ちていた。やはり単身現れ、もちろん着物姿だったが、二人の前にどっかりと腰を下ろし、諄々と説得するのだが、荒谷は承知したものの、加納の気がおさまらない。そこで、錦之助が、自分を撃ち殺してから行けと加納に迫る。この場面の錦之助のにらんだ表情が、凄かった。ここを観ただけでも、この映画を観る価値があると思ったほどである。松方弘樹も千葉真一もチンピラに見えてしまうのだから、病後とはいえ、錦之助の貫禄は段違いだった。
第三のシーンは、その足で錦之助が山辰組へ乗り込み、親分(成田三樹夫)に会長職を辞めて引退するように迫る場面だった。ここは意外にあっさりとしていて、成田三樹夫も恐れをなし、錦之助の顔を立ててすぐに承知する。
多分、錦之助の出番はトータルで10分かそこらだったと思うが、他の出演者たちとの格の違いを見せていた。
この映画の後半では、錦之助に代わって、鶴田浩二が登場するが、それこそ昔日の面影がなく、やつれ果てていた。言い忘れていたが、『最後の博徒』は、鶴田浩二の最後の出演映画だった。すでにガンに冒されていたのだろう。鶴田浩二が亡くなるのは、この映画の一年半後、62歳だった。鶴田は錦之助より8歳年上で、錦之助が東映を去った後、高倉健や池部良とともに東映仁侠映画を全盛に導いた頃のことを思うと、この映画の鶴田は、見るに忍びない姿だった。