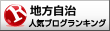牛乳は日本の食文化にはもともとなかった食材である。日本の農地は日光量が多く水資源が豊富なため、世界的にも極めて生産性が高い地域である。日本農業が生産性が低いと思っている人たちは、規模の問題と取り違えているのである。
牛乳は日本の食文化にはもともとなかった食材である。日本の農地は日光量が多く水資源が豊富なため、世界的にも極めて生産性が高い地域である。日本農業が生産性が低いと思っている人たちは、規模の問題と取り違えているのである。日本ほど一国の中で多種類の農産物を生産できるところは少ない。
上の表は農民連が作成した、植物が生産する生産するカロリーを算出して、その国の摂取カロリーで除した数字である。日本が飛びぬけて高いことが判る。
日本で最初に乳牛を飼ったのは、アララギ派の詩人で「野菊の墓」を著した伊藤左千夫たちである。明治初期のことであるが、千葉県が長年日本第二の酪農県であったのも、森永乳業が支えた伝統なのでなのである。
牛を飼うのは飼料として牧草が採れるところである。牧草は日本中どこでも採れるが、平地は生産性の高いコメを主体とした換金作物が主体となる。草しか採れないところは山間地域即ち高原や、北海道などの冷涼な地域である。つまり牧場と言えば、白樺を連想した中で草を食べる牛を思い描くが、それは伝統的な日本の風景とは言い難い、エキゾチックなロマンを思い浮かべさせるのである。伊藤左千夫たちが酪農を始めたのも、そうしたロマンが背景にあろう。
北海道に入植して牛を飼う人たちにも、非日本的な酪農風景、牧歌風景への憧れが背景にある。それは生産性の低い、非換金作物の牧草でも採れるような冷涼な僻地で、明治以降になって日本酪農は定着してきた経緯がある。
そもそも畜産は、人間が食べることができない物や残滓を家畜に与えて、肉や卵や牛乳を生産してもらう形態を言うのである。そして家畜が生産するもう一つの物、糞尿が農地に肥料とした与えられて生産を高めてくれるものであったのである。日本のように生産性の高い地域には、そうした背景によって畜産は定着しなかったのである。
ヨーロッパや大陸などの農業を日本では、「有畜農業」と呼ぶのであるが、畜産という言葉はこれらの国にはない。単に農業と呼ぶだけである。
しかし、近代になっての畜産は大きく形態を変えてきた。穀物を給与するようになったのである。乳牛であれば、これまで年間4千キロ泌乳すれば十分であったが、穀物を与えるようになって現在では1万キロも生産するようになった。
穀物はほとんどがアメリカ産のトウモロコシである。地球の裏側から金を払ってまで買って乳牛に与えるのは、穀物が安く購入できて高い牛乳を生産してくれるからである。アニマルウエルフェアーについて以前に書きましたが、穀物給与による高生産は、カロリー生産や牛の健康面などから見ても極めて大きな無駄を生むのです。
消費者の多くの方が口にされる牛乳の95%は、穀物主体の飼料によって生産されたものです。科学的な比較は難しいのですが、カロリー比較のザックリとした表現すれば、牛乳のほぼ7割はアメリカの穀物によって生産されたものと言えます。私はこうした畜産を、畜産加工業と呼んでいます。
日本の飲用乳のほとんどは高温殺菌したものです。焦げたような感じがすると私たちは表現しますが、これは牛乳の生産形態に加えて、牛乳の本来の形を失って消費者の届けているといえるのです。