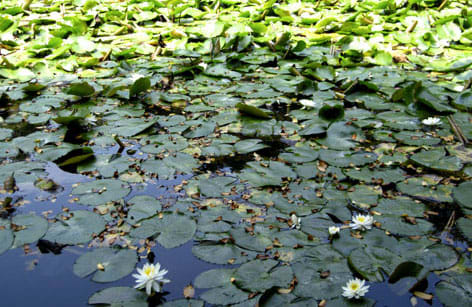太子町から竹内街道沿いの磯長(しなが)の地は、聖徳太子にまつわる事績や用
明天皇、推古天皇、敏達天皇、孝徳天皇の天皇陵、お寺が数多く点在しています。
叡福寺は、聖徳太子陵墓を祭祀守護、追福を営むためのお寺として創建されたと
いいます。その後聖武天皇の勅願により、堂塔伽藍が整備され、太子信仰の中核
をなした寺院として、今も上の太子と称され親しまれているそうす。その後の歴
史は戦乱、天災を被りながら江戸期に今の姿になったといいます。広大な境内は
整然と整備され、非常にきれいなお寺です。ただ伽藍配置は、陵墓を祭祀守護の
為なのか既存の配置ではなく、規則性と云うのは感じることは出来ません。
南大門。
昭和33年に再々建された朱色も鮮やかな大門。左右にはやや小ぶりの金剛力士、
阿吽両像が安置されています。


南大門偏額。
やはり寺名、山号ではなく聖徳廟と記されています。揮毫はなぜか岸信介元内閣
総理大臣。

南大門金剛力士


金堂。
堂々とした堂宇。江戸中期の再建。本尊は如意輪観音菩薩坐像。

多宝塔。
均整のとれた美しい塔です。


聖霊殿。
太子堂とも呼ばれ、聖徳太子16歳像と2歳像が祀られている。この日は大勢の方
が入堂されていました。

上の御堂。
聖徳太子35歳像が祀られています。

念仏堂。
本尊は阿弥陀如来、信州善光寺と関係があるらしく、善光寺48願所第13番札所ら
しいです。この日も数人の方が入堂され、僧侶の読経が響いていました。

弘法大師堂。
弘法大師自らが刻んだ大師像が本尊。

見真大師堂。
真宗教徒のためのお堂。本尊親鸞上人坐像。

浄土堂。
本尊は阿弥陀三尊。

経堂。
六角形の建物。写経納めどころ。

境内に咲く紫陽花。

二天門。
太子廟への入り口とも云うべき門。内側左右に二天がさり気なく祀られています。

二天像。
二天とは通常、四天王の内の二人を云うらしいのですが、説明文が無いので詳し
くは分かりません。察するに、方向色で見ると朱のお顔が増長天、緑のお顔が自
国天と思われます。彩色きれいすぎ、時代を経た造像ではなさそうです。


聖徳太子廟。
山傾に沿って三層の屋根を持つ御廟。石室へ通ずる廟門と思われます。前面の石
柱垣の正面に菊の御紋。宮内庁管理でこれより中へは入れません。

聖徳太子陵。
御陵は磯長山丘陵を利用した円墳。考古学界では「叡福寺北古墳」と呼び、墳丘
の高さは7.2m、直径は54.3m。内部は精巧な切石を用いた横穴式石室で、太子
と母穴穂部間人皇后、妃膳郎女の3人の棺が納められていると伝えられることか
ら、三骨一廟と呼ばれているそうです。石室は現在閉じられており、誰も入るこ
とは出来ないそうです。
墳丘の周囲が「結界石」と呼ばれる石の列で二重に囲まれています。弘法大師が
築いたと言われる聖地と俗界をへだてる結界石が490体あり、いずれも観音梵字
が刻まれています。周辺には周回道がありますが、現在は通行出来ません。

もとは古義真言宗金剛峰寺の末寺であったと云うこのお寺は現在、山号磯長山、
寺名叡福寺、単立寺院です。太子信仰の中心寺院として、宗派に関係なく幅広く
信者を受け入れているお寺と云うことで、親しまれているのでしょうネ。
明天皇、推古天皇、敏達天皇、孝徳天皇の天皇陵、お寺が数多く点在しています。
叡福寺は、聖徳太子陵墓を祭祀守護、追福を営むためのお寺として創建されたと
いいます。その後聖武天皇の勅願により、堂塔伽藍が整備され、太子信仰の中核
をなした寺院として、今も上の太子と称され親しまれているそうす。その後の歴
史は戦乱、天災を被りながら江戸期に今の姿になったといいます。広大な境内は
整然と整備され、非常にきれいなお寺です。ただ伽藍配置は、陵墓を祭祀守護の
為なのか既存の配置ではなく、規則性と云うのは感じることは出来ません。
南大門。
昭和33年に再々建された朱色も鮮やかな大門。左右にはやや小ぶりの金剛力士、
阿吽両像が安置されています。


南大門偏額。
やはり寺名、山号ではなく聖徳廟と記されています。揮毫はなぜか岸信介元内閣
総理大臣。

南大門金剛力士


金堂。
堂々とした堂宇。江戸中期の再建。本尊は如意輪観音菩薩坐像。

多宝塔。
均整のとれた美しい塔です。


聖霊殿。
太子堂とも呼ばれ、聖徳太子16歳像と2歳像が祀られている。この日は大勢の方
が入堂されていました。

上の御堂。
聖徳太子35歳像が祀られています。

念仏堂。
本尊は阿弥陀如来、信州善光寺と関係があるらしく、善光寺48願所第13番札所ら
しいです。この日も数人の方が入堂され、僧侶の読経が響いていました。

弘法大師堂。
弘法大師自らが刻んだ大師像が本尊。

見真大師堂。
真宗教徒のためのお堂。本尊親鸞上人坐像。

浄土堂。
本尊は阿弥陀三尊。

経堂。
六角形の建物。写経納めどころ。

境内に咲く紫陽花。

二天門。
太子廟への入り口とも云うべき門。内側左右に二天がさり気なく祀られています。

二天像。
二天とは通常、四天王の内の二人を云うらしいのですが、説明文が無いので詳し
くは分かりません。察するに、方向色で見ると朱のお顔が増長天、緑のお顔が自
国天と思われます。彩色きれいすぎ、時代を経た造像ではなさそうです。


聖徳太子廟。
山傾に沿って三層の屋根を持つ御廟。石室へ通ずる廟門と思われます。前面の石
柱垣の正面に菊の御紋。宮内庁管理でこれより中へは入れません。

聖徳太子陵。
御陵は磯長山丘陵を利用した円墳。考古学界では「叡福寺北古墳」と呼び、墳丘
の高さは7.2m、直径は54.3m。内部は精巧な切石を用いた横穴式石室で、太子
と母穴穂部間人皇后、妃膳郎女の3人の棺が納められていると伝えられることか
ら、三骨一廟と呼ばれているそうです。石室は現在閉じられており、誰も入るこ
とは出来ないそうです。
墳丘の周囲が「結界石」と呼ばれる石の列で二重に囲まれています。弘法大師が
築いたと言われる聖地と俗界をへだてる結界石が490体あり、いずれも観音梵字
が刻まれています。周辺には周回道がありますが、現在は通行出来ません。

もとは古義真言宗金剛峰寺の末寺であったと云うこのお寺は現在、山号磯長山、
寺名叡福寺、単立寺院です。太子信仰の中心寺院として、宗派に関係なく幅広く
信者を受け入れているお寺と云うことで、親しまれているのでしょうネ。