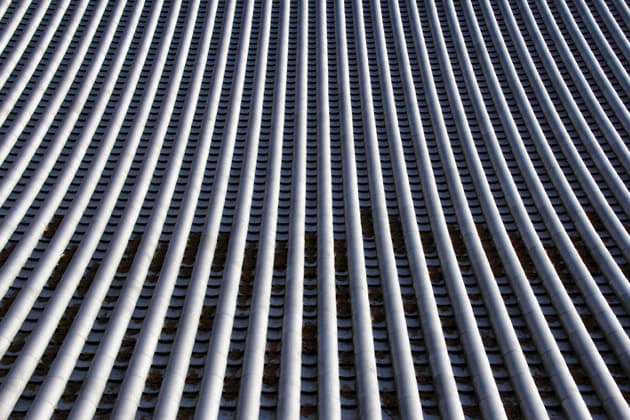(2012.12.01訪問)
山辺の道沿いにある長岳寺で、狩野山楽の大地獄絵が公開されていると聞いたので訪ねました。長岳寺は花
の寺と聞き、ついでに紅葉をもとスケベ心も手伝い、紅葉見頃と新聞予報を信じて奈良へ向かいます。
残念ながら紅葉予報も今日の天気も見事に外れペケ。色褪せた残り紅葉を小雨の中、曇りの中で観るハメに
なりました。とはいえ、きれいな紅葉も残っていたことは念のため。
写真の紅葉の一部はPSでサワリまくっています。
▼紅葉。

[ 長岳寺 ]
●山号 釜の口山(かまのくちさん)
●寺号 長岳寺(ちょうがくじ) 釜口大師
●宗派 高野山真言宗(こうやさんしんごんしゅう)
●勅願 淳和天皇
●開基 弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)
●開創 天長元年(824年)
●本尊 阿弥陀三尊
長岳寺縁起
長岳寺は天長元年(824年)弘法大師空海が淳和天皇の勅願により大和神社(おおやまとじんじゃ)の神宮寺とし
て創建。盛時には塔頭四十八坊、衆徒三百余名を数えたそうです。
▼大門。長岳寺の総門。六脚、切妻造、本瓦葺。寛永十七年(1640年)再建。

▼参道。花の寺にふさわしく春は平戸ツツジのピンクで参道左右が染まります。

▼参道。もうすぐ楼門です。

▼鐘楼門(重文)。空海さん創建当時の唯一の建物だそうです。勾欄付重層四脚鐘楼門、一間一戸、入母屋造、
柿葺。現在梵鐘は吊るされていません。

▼もみじ。

▼本堂。桁行五間、梁行四間、入母屋造、本瓦葺、正面一間向拝付。天明三年(1783年)再建。

▼本尊阿弥陀三尊像(重文)。木造。中央本尊阿弥陀如来坐像、右脇侍観音菩薩半伽椅座像、左勢至菩薩半伽
椅座像。仁平元年(1151年)造像。

三尊はご覧のように三部屋に分かれて祀られています。脇侍の脚をご覧ください、半伽椅座と云う珍しい坐
り方で片足を下げています。目は玉眼、玉眼を用いた仏像としては日本最古のものだそうです。離れていま
すが三尊像として出色、金泥は落ちていますが、見事な調和、慶派に大きな影響を与えた理由がよく判りま
す。
▼本尊阿弥陀如来坐像(重文)。木造、玉眼。像高半丈六、仁平元年(1151年)造像。定印を結んだ結跏趺坐。

定朝様の匂いが残っていますが、鎌倉仏の先駆と云われるように量感が凄い、金泥が少し残っていますがお
顔が丸く口元の紅が子供の初化粧のように妙に初々しい感じがします。納衣のドレープを思わず摘みたくな
るほど。
四天王のお二人。両像とも彩色がよく残っています。あとの二天像はどこへ行かれたのでしょう。
▼多聞天立像(重文)。木造、仁平元年(1151年)造像。

▼増長天立像(重文)。木造、仁平元年(1151年)造像。

▼大地獄絵。
狩野山楽筆、安土桃山時代。写真は閻魔庁閻魔王図部分。
本堂東壁に九幅が、超細密カラーで描かれ凄い迫力で並んでいます。とにかく細かく精微、十王の表情や従
者、死者の怯えた姿かたちは言いようの無い怖さが迫ってきます。これだけの軸が無指定と云うのもよく判
らないなァ。
とにかく今日一!

九幅の軸で構成され、全体が一枚の絵となっています。内容は図の上部に十王裁判図、中程から下部にかけ
て、冥界入口の墓地、罪問間樹、死天山、三途の川、奪衣婆、賽の河原、八大地獄、餓鬼道、畜生道、修羅
道など、すざましい情景が描かれ、第九軸は、極楽より阿弥陀如来が聖衆を連れて極楽往生する人を迎えに
くる聖衆来迎図がえがかれています。
▼ご住職の地獄絵現代風絵解きに聞き惚れました。中学生集団も真剣に聞いていました。

▼天井画。格天井に家紋らしき絵が描かれています。

▼本堂から放生池。

▼本堂。

▼本堂前に建つ練塔。塔身に金剛界四仏の種子が彫られています。
八層石造層塔 (白色凝灰岩、高さ 約400cm) 鎌倉時代後期。

▼境内。

▼放生池。

▼拝堂。桁行三間、梁行二間、寄せ棟造、桟瓦葺。
後ろに建つ大師堂のための拝堂。弘法大師と記された扁額が。

▼拝堂ともみじ。

▼拝堂。奥壇から大師堂が拝せるようになっています。

▼大師堂扁額。

▼拝堂ともみじ。

▼放生池の南に建つ鐘楼堂。皆さん必ず一撞きしてましたよ。

▼もみじ。

▼傘付き石仏。

▼もみじ。

▼石垣と散りもみじ。この道を歩くと踏みしめると云う言葉が実感できます。

▼もみじ。

▼弥勒大石棺仏。三十三カ所道の入り口にたっています。約2mの古墳石材を利用した浮き彫。鎌倉時代。

▼もみじ。

▼もみじ。

▼石仏。

▼もみじ。

▼いずれ全山このような散りもみじで埋もれることでしょう。冬へと季節の衣がえが巡ってきます。

皆様お風邪など召しませんようにお大事にしてくださいませ。ついでに景気が良くなりますように×△○…。
長岳寺オシマイ