
■中国の海洋戦略(第1・第2列島線)

■中国の国防費の推移
<本格的な空母艦隊の編成を進める中国は、10~20年後を視野に米軍と互角に戦える戦力を目指して、日本やフィリピンの周辺に当たる北西太平洋の制海権確保を狙っているとみられる。(中略)かつての中国人民解放軍は世界最大規模の陸軍が中心で、海軍は沿岸を警備・防衛する「脇役」に甘んじていた。だが、この十年の経済成長によって国外の資源・エネルギーに依存するようになり、海洋権益の重要性が飛躍的に拡大。特にマラッカ海峡を経てインド洋につながるルートは命綱と言える。このため、沖縄から台湾、フィリピンをかすめ南シナ海を含むラインを「第1列島線」として防衛圏と位置付けるとともに、小笠原諸島から米領グラム、サイパン、パプアニューギニアなどを結ぶラインを「第2列島線」と認識。制海権確保の狙いがあるとされる。中国艦艇による沖縄県・尖閣諸島周辺での活発な動きも、領有権の主張を超えた戦略的な思惑がある。(中略)戦略実現には、空母をはじめ遠洋航海に適した軍艦が不可欠だ。人民解放軍創始者の一人である朱徳の孫、朱和平空軍少将は今月3日、遼寧の青島配備について「日本を震え上がらせる効果がある」と語った。>
(東京新聞2013年3月6日 中国国防費3年連続2桁増/海軍強化権益に照準/高まる国外資源依存 米アジア戦略に対抗)

■ASEAN加盟国の南シナ海の対応をめぐる温度差
<東南アジア諸国連合(ASEAN)の首脳会議が24日、ブルネイの首都バンダルスリブガワンで始まった。(中略)本誌が入手した議長声明案によると、南シナ海問題について「武力や威嚇でなく、国際法に基づく平和的解決を目指し、法的拘束力を持たせた『行動規範』の早期策定に向けて、中国との協力関係が継続されることを期待する」と、控えめな表現にとどめている。中国は関係当事者国との二国間協議による解決を求め、自国の行動を縛る規範策定には消極的。(中略)ASEANは昨年7月の外相会議で、南シナ海問題で中国と対立するフィリピンやベトナムと、中国から経済支援を受ける議長国カンボジアとの溝が埋まらず、設立以来、初めて共同声明を採択できない異例の事態となった。域内はいまだ結束できず、中国も規範策定の交渉開始を確約していない。>
(東京新聞2013年4月25日付 ASEAN首脳会議 対中国控えめ表現/議長声明「南シナ海」議論)

■中国が南シナ海で管轄権を主張する海域
<シンガポールで開かれているアジア安全保障会議で、ヘーゲル米国防長官やASEAN(東南アジア諸国連合)の一部加盟国の国防相らは、アジア太平洋地域で影響力を増す中国をあからさまにけん制した。(中略)ヘーゲル氏は1日の演説で、オバマ政権は「二正面作戦」を放棄し、アジア太平洋地域に軸足を移す「リバランス(再均衡)」の方針を堅持すると強調した。(中略)同時に「(中国は)大国として新たな責任を負っている」と指摘し、対中均衡を図りながら、中国に対して安定した地域秩序形成に協力するよう求めた。(中略)31日にはベトナムのグエン・タン・ズン首相が基調演説した。南シナ海や東シナ海で領有権問題が複雑化しつつあるとした上で「関係当事国は武力や脅しに訴えるべきではない」と主張。名指しこそ避けたものの中国を念頭に置いた発言とみられている。>
(東京新聞2013年6月2日付 アジア安全保障会議 米・ASEAN「中国包囲網」に厚み/太平洋地域影響力拡大けん制)

■中国軍の動き
<中国海軍の駆逐艦など艦艇5隻は日本海でのロシア海軍との演習後、14日に中国海軍艦艇として初めて宗谷海峡を通過し、太平洋に進出。小笠原諸島の婿島から南西に向かい、沖ノ鳥島とフィリピンの中間海域まで進出した。一方、軍用機は航空機をレーダー監視するY8早期警戒機で、24日午前、沖縄本島と宮古島の間を通過して東シナ海から太平洋へ進出。南下してきた艦艇5隻と合流し、数時間にわたって合同演習した。(中略)中国は台湾有事を想定して、米国の関与を避けるため、太平洋における接近阻止・領域拒否の能力を向上させ、「近海」の範囲を第2列島線まで広げることを目標としている。>
(東京新聞2013年7月31日付 中国軍 太平洋で初の合同演習/日本周辺通過の艦艇・航空機/第2列島線へ進出加速)











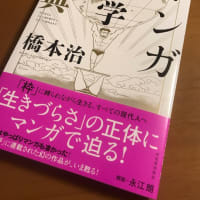
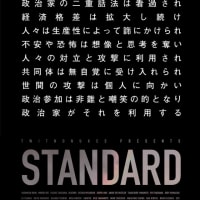



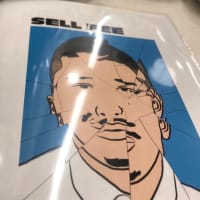
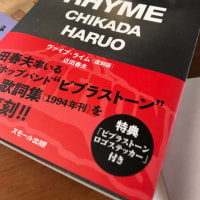
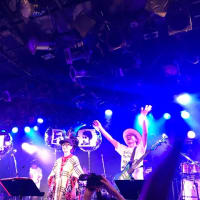
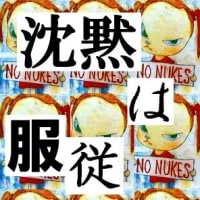
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます