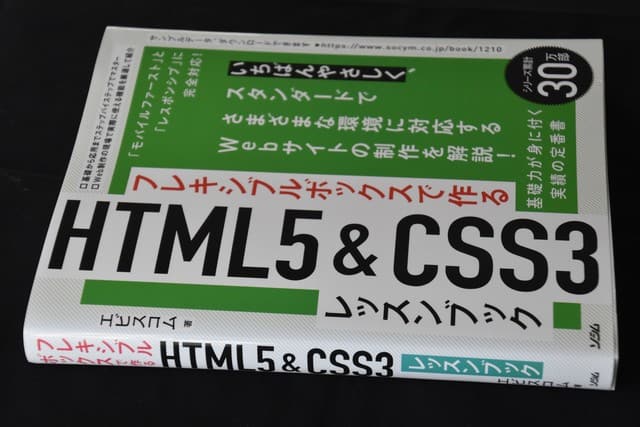花の名前を捜すときに、花の形状別に分類した表があったらよいのでは?・・・と、私自身が思うので、過去に撮った写真を整理し、花名(花写真鑑の基準名)毎に整理し、その写真を見ながら分類をしている。
整理した花の写真は6万枚近くに成り、花の種類が1900種を越えてきたので、時間がかかっているが、現状は先日1400種を越えたばかりである。 そんな途上にて、過去の収集の間違いを発見することがしばしばある。
花の名前の数は、どこで区切るかによって、如何様にも変るが、大きな流れとしては、最近は細分化に向かっているように感じるが、細分化することで、過去の分類がある意味では、間違いということにもなる。
今回は、現在は単なる属名であるが、「トウダイグサ」もしくは「ユーフォルピア」と言う名前で、一括りとしていたものを、現状ではそれぞれが、独立した名前を持ち始めた等、不自然となってきたので、今回分割することにした。
「ユーフォルビア・ブラックパール」 登録番号 第420号
従来、科名、属名である「トウダイグサ」を総称として、全体を一括していたが、今回それぞれに分割することいした。 ここを「トウダイグサ」最初に設立したのが、今は「ユーフォルビア・ブラックパール」という立派な名前があるので、これを独立させた。

次の「ユーフォルビア・マーチニー」と似ているが、ご丁寧なことに、別の名前が付けられているのだ。 誰なのかわ知らないが、そこまでして、金儲けをしたいらしい。・・・と言いつつ、ちゃっかり活用させて戴いたがね!。
「ユーフォルビア・マーチニー」 登録番号 第1440号
花の中心が、赤茶色のアクセントの花は、上記名前らしいのでこれを独立させた。 なお、従来の所が欠番となるので、これをその補充としたので、"新種”としてもおかしくはないが、登録番号は第1440号とした。

「ユーフォルビア・ブラックバード」 "新種"登録 第1907号
今更、"新種"とすることに、抵抗感は無くは無いが、順番ではないと自身に言い聞かせつつ・・・・。

「ユーフォルビア・カラキアス」 "新種"登録 第1908号

「ユーフォルビア・プルプレア」 "新種"登録 第1909号

「ユーフォルビア・アスコットレインボー」 "新種"登録 第1910号

「ユーフォルビア・オブロンガタ」 "新種"登録 第1911号

お陰様でと言うのも、お恥ずかしいが、これにて1911種集めたことになった!。