朝比奈なを『進路格差』の紹介を書いたので、そこからの派生で一度書きたいと思っていたことを。同書の中で、「高校が人生の分水嶺」というようなことが言われていた。全くその通りなのだが、そこで東京都では「様々なタイプの高校」とか「進学指導重点校」など幾つもの「教育改革」が行われてきた。だけど、中学教員も高校教員も体験した自分から見ると、まず必要なのは「中学校への社会全体の支援」だと思う。明らかに一番大変なのも中学校である。
20世紀の中学とはいろいろな点で様変わりしていることだろう。だが、小学校と高校に挟まれ、常に高校受験を意識せざるを得ないのが中学である。部活動が本格化して、休日返上の苦労も中学が一番だ。生徒は思春期を迎え、問題行動も発生して生活指導も苦労の連続。そして地域に密着した義務教育では、「地域の目」が高校とは段違いである。そのような「本質」は不変だろう。
 (教員の苦労の調査)
(教員の苦労の調査)
さらに東京都では中学校の「学校選択制」もあり、また「英語のスピーキング・テスト」まで実施された。また全国で「全国学力テスト」とか「道徳教科化」など、自分の時代にはあり得なかった政策も実施されている。教員の階層化、競争的人事制度も進んでいるうえに、コロナ禍対応、デジタル化対応もある。昔でさえ忙しかったのに、今現在の多忙さは恐るべきものだろう。
高校が人生の分水嶺と言われても、いや違うだろう、大学こそ自分の人生の分かれ道だったと思う人も多いはずだ。自分自身もそっち側で、大学や大学院、あるいはその後の自ら関わった出来事こそ、自分を作ったと思う。それは自分が進学校に入学し、大学へ通うのは当然という意識を持っていたからだ。それを可能にする家庭の経済力も担保されていた。だから、自分にとっては「どのレベルの大学に合格できるか」、さらに「どの学部を目指すか」という問題こそが重要だったわけである。
中学教員のほとんどはそれなりの進学高校出身である。そうじゃないと、大学で教員免許を取って、教員採用試験に合格しない。もちろん高校教員も同様だが、最初に配属される高校が地域で最高レベルということはほとんどない。専門学校や就職を目指す生徒を指導することで「高校生の多様な進路」を知る。中学教員もいろんなタイプの生徒を扱うけれど、様々なタイプの高校を知っているわけではない。工業高校や商業高校へ進学する生徒は多いけど、普通科進学校から順番におおよそ作られている「高校の偏差値序列」に沿って指導しがちになる。
自分もそうだったし、違うタイプの高校へ進学させるべきだったと後悔するようなケースもあった。中学では就職希望の生徒から、国立大学附属校に合格するような生徒まで教えた。授業、部活動、生活指導に追われながら、多種多様な生徒を相手にして、それ以上の進路指導は難しいだろうと思う。自分が高校に異動すると、今度は明らかに間違った進路先を選んだと思う生徒に何人も出会った。高校は義務教育だから、「留年」や「退学」がある。何人もの生徒が退学していったし、また退学させざるを得ない。
留年も退学もできない中学の現場では、多忙の中で多くの生徒や教員が悩んでいるだろう。「人生の分水嶺」である高校への進路指導は、中学教員が頑張るしかない。でも、特に東京には私立高校が数え切れないほどあって、中学3年の担任は学校説明会の訪問に忙殺される。そんな中で、どのように生徒一人一人にとって効果的な進路指導ができるのか。いろいろな意味で、一番大変な中学校の現場に教育的資源を集中的に投じないと日本は持たなくなると思う。
進路指導、教育相談専任の教員を置く余裕はないだろう。だけど、退職教員に民間人も加えて、非常勤でいいから中学に相談員を派遣するべきだ。部活動の地域移管もどんどん進める必要がある。人材難などと言わず、地域にいる卒業生のネットワークを活用する以外にない。大学は中学、高校での学習支援、部活動支援の活動を必履修にして、大胆に単位認定するべきだ。そして、保護者の力。親の中には、様々な仕事に従事している人がたくさんいる。我が子が卒業した後でも、何か地元の中学に協力したいと思っている人は多いだろう。
自分が出た中学の近くで暮らしている。かつて高校に勤務していたとき、朝に出勤するときには、もう中学の電気が付いていた。退勤して家に帰るときも、まだ部活動をやっていた。それどころか、定時制高校勤務時に夜の勤務が終わって帰ってきても、まだ一部の教室に電気が付いていた。これでは潰れてしまうに決まっている。教員の生活だけでなく、生徒にも悪影響が及ぶに決まっている。一番大変な中学校への支援を社会全体で考えないといけない。
20世紀の中学とはいろいろな点で様変わりしていることだろう。だが、小学校と高校に挟まれ、常に高校受験を意識せざるを得ないのが中学である。部活動が本格化して、休日返上の苦労も中学が一番だ。生徒は思春期を迎え、問題行動も発生して生活指導も苦労の連続。そして地域に密着した義務教育では、「地域の目」が高校とは段違いである。そのような「本質」は不変だろう。
 (教員の苦労の調査)
(教員の苦労の調査)さらに東京都では中学校の「学校選択制」もあり、また「英語のスピーキング・テスト」まで実施された。また全国で「全国学力テスト」とか「道徳教科化」など、自分の時代にはあり得なかった政策も実施されている。教員の階層化、競争的人事制度も進んでいるうえに、コロナ禍対応、デジタル化対応もある。昔でさえ忙しかったのに、今現在の多忙さは恐るべきものだろう。
高校が人生の分水嶺と言われても、いや違うだろう、大学こそ自分の人生の分かれ道だったと思う人も多いはずだ。自分自身もそっち側で、大学や大学院、あるいはその後の自ら関わった出来事こそ、自分を作ったと思う。それは自分が進学校に入学し、大学へ通うのは当然という意識を持っていたからだ。それを可能にする家庭の経済力も担保されていた。だから、自分にとっては「どのレベルの大学に合格できるか」、さらに「どの学部を目指すか」という問題こそが重要だったわけである。
中学教員のほとんどはそれなりの進学高校出身である。そうじゃないと、大学で教員免許を取って、教員採用試験に合格しない。もちろん高校教員も同様だが、最初に配属される高校が地域で最高レベルということはほとんどない。専門学校や就職を目指す生徒を指導することで「高校生の多様な進路」を知る。中学教員もいろんなタイプの生徒を扱うけれど、様々なタイプの高校を知っているわけではない。工業高校や商業高校へ進学する生徒は多いけど、普通科進学校から順番におおよそ作られている「高校の偏差値序列」に沿って指導しがちになる。
自分もそうだったし、違うタイプの高校へ進学させるべきだったと後悔するようなケースもあった。中学では就職希望の生徒から、国立大学附属校に合格するような生徒まで教えた。授業、部活動、生活指導に追われながら、多種多様な生徒を相手にして、それ以上の進路指導は難しいだろうと思う。自分が高校に異動すると、今度は明らかに間違った進路先を選んだと思う生徒に何人も出会った。高校は義務教育だから、「留年」や「退学」がある。何人もの生徒が退学していったし、また退学させざるを得ない。
留年も退学もできない中学の現場では、多忙の中で多くの生徒や教員が悩んでいるだろう。「人生の分水嶺」である高校への進路指導は、中学教員が頑張るしかない。でも、特に東京には私立高校が数え切れないほどあって、中学3年の担任は学校説明会の訪問に忙殺される。そんな中で、どのように生徒一人一人にとって効果的な進路指導ができるのか。いろいろな意味で、一番大変な中学校の現場に教育的資源を集中的に投じないと日本は持たなくなると思う。
進路指導、教育相談専任の教員を置く余裕はないだろう。だけど、退職教員に民間人も加えて、非常勤でいいから中学に相談員を派遣するべきだ。部活動の地域移管もどんどん進める必要がある。人材難などと言わず、地域にいる卒業生のネットワークを活用する以外にない。大学は中学、高校での学習支援、部活動支援の活動を必履修にして、大胆に単位認定するべきだ。そして、保護者の力。親の中には、様々な仕事に従事している人がたくさんいる。我が子が卒業した後でも、何か地元の中学に協力したいと思っている人は多いだろう。
自分が出た中学の近くで暮らしている。かつて高校に勤務していたとき、朝に出勤するときには、もう中学の電気が付いていた。退勤して家に帰るときも、まだ部活動をやっていた。それどころか、定時制高校勤務時に夜の勤務が終わって帰ってきても、まだ一部の教室に電気が付いていた。これでは潰れてしまうに決まっている。教員の生活だけでなく、生徒にも悪影響が及ぶに決まっている。一番大変な中学校への支援を社会全体で考えないといけない。










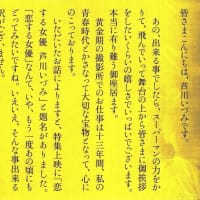
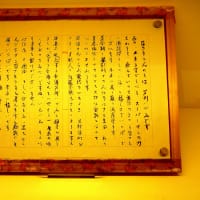








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます