五日市憲法を歩く① 土蔵から発見された“源流”
ツルシ カズヒコ
1955年生まれ。編集者・ジャーナリスト。元『週刊SPA!』編集長。本紙旅欄で「ツルシのぶらり探訪」連載中。主著に『秩父事件再発見』ほか
都心から西へ50キロ。「しんぶん赤旗」旅記事の取材で東京都あきる野市を訪れたのは5月でした。東京経済大学の色川大吉教授とゼミ生の調査により、五日市町(現あきる野市)深沢の深澤家土蔵から、「五日市憲法草案」(1881年起草)が発見されたのは1968年8月。自由民権思想家・千葉卓三郎(1852~83年)らが起草し、現憲法の源流と評される、民主的先駆性を持った民間憲法草案のひとつです。今年はその発見50周年です。
色川ゼミの一員として、深澤家土蔵調査に参加したのが新井勝紘さん(元専修大学教授・日本近代史)です。当時大学4年生でした。新井さんの最近著『五日市憲法』(岩波新書)によれば、日本近現代史150年のなかで、憲法に国民の関心が高まった時代は3度ありました。1度めは幕末維新期から大日本帝国憲法発布までの20数年間。2度めはアジア・太平洋戦争終結から日本国憲法公布までの1年あまり。3度めは「安倍9条改憲」が進行中の現在です。
新井さんが顧問を務める「五日市憲法草案の会」の結成は2011年。略称は「護憲」にかけた「五憲の会」。事務局長・鈴木富雄さんの案内で五日市郷土館に向かいました。和紙24枚に毛筆で清書された、204条からなる五日市憲法草案の複製を展示しています。
抵抗権や婦人参政権の規定まである、土佐の自由民権思想家・植木枝盛(えもり)(1857~92年)の「東洋大日本国国憲按(あん)」(1881年起草)とならび、この憲法草案が現憲法の源流とされる理由を、鈴木さんはこう指摘します。

あきる野市の「五日市憲法草案之碑」前でガイド中の新井勝紘さん(左)と鈴木富雄さん(筆者撮影)
「36項目におよぶ具体的で精緻な国民権利規定は、現憲法と対照表ができるほど立憲的・民主的です。たとえば人権の条文で、政治犯への死刑宣告を禁じ、司法の条文でも禁じ、人権を二重に保護しています」
鈴木さんは1940年、福島県生まれ。東京の大学で学んだ後、67年に旧五日市町に移住し、71年に同町初の日本共産党町議に。合併(95年)後のあきる野市議をふくめ、議員を7期30年務めました。著書『ガイドブック五日市憲法草案』(日本機関紙出版センター)は、豊富な現地調査と郷土史家としての視点が盛りこまれ、入門書として秀逸です。コツコツと続けてきたガイド役も200回を超えました。こうして私の五日市憲法草案を知る小さな旅が始まりました。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年11月14日付掲載
五日市憲法草案が起草された1881年(明治14年)といえば、自由民権運動が始まったとされる1874年から7年。10月には板垣退助の自由党が結成されている。
大日本国憲法が施行されたのが1890年。その過程で、今の日本国憲法に通ずる憲法草案が論議されていた。
ツルシ カズヒコ
1955年生まれ。編集者・ジャーナリスト。元『週刊SPA!』編集長。本紙旅欄で「ツルシのぶらり探訪」連載中。主著に『秩父事件再発見』ほか
都心から西へ50キロ。「しんぶん赤旗」旅記事の取材で東京都あきる野市を訪れたのは5月でした。東京経済大学の色川大吉教授とゼミ生の調査により、五日市町(現あきる野市)深沢の深澤家土蔵から、「五日市憲法草案」(1881年起草)が発見されたのは1968年8月。自由民権思想家・千葉卓三郎(1852~83年)らが起草し、現憲法の源流と評される、民主的先駆性を持った民間憲法草案のひとつです。今年はその発見50周年です。
色川ゼミの一員として、深澤家土蔵調査に参加したのが新井勝紘さん(元専修大学教授・日本近代史)です。当時大学4年生でした。新井さんの最近著『五日市憲法』(岩波新書)によれば、日本近現代史150年のなかで、憲法に国民の関心が高まった時代は3度ありました。1度めは幕末維新期から大日本帝国憲法発布までの20数年間。2度めはアジア・太平洋戦争終結から日本国憲法公布までの1年あまり。3度めは「安倍9条改憲」が進行中の現在です。
新井さんが顧問を務める「五日市憲法草案の会」の結成は2011年。略称は「護憲」にかけた「五憲の会」。事務局長・鈴木富雄さんの案内で五日市郷土館に向かいました。和紙24枚に毛筆で清書された、204条からなる五日市憲法草案の複製を展示しています。
抵抗権や婦人参政権の規定まである、土佐の自由民権思想家・植木枝盛(えもり)(1857~92年)の「東洋大日本国国憲按(あん)」(1881年起草)とならび、この憲法草案が現憲法の源流とされる理由を、鈴木さんはこう指摘します。

あきる野市の「五日市憲法草案之碑」前でガイド中の新井勝紘さん(左)と鈴木富雄さん(筆者撮影)
「36項目におよぶ具体的で精緻な国民権利規定は、現憲法と対照表ができるほど立憲的・民主的です。たとえば人権の条文で、政治犯への死刑宣告を禁じ、司法の条文でも禁じ、人権を二重に保護しています」
鈴木さんは1940年、福島県生まれ。東京の大学で学んだ後、67年に旧五日市町に移住し、71年に同町初の日本共産党町議に。合併(95年)後のあきる野市議をふくめ、議員を7期30年務めました。著書『ガイドブック五日市憲法草案』(日本機関紙出版センター)は、豊富な現地調査と郷土史家としての視点が盛りこまれ、入門書として秀逸です。コツコツと続けてきたガイド役も200回を超えました。こうして私の五日市憲法草案を知る小さな旅が始まりました。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年11月14日付掲載
五日市憲法草案が起草された1881年(明治14年)といえば、自由民権運動が始まったとされる1874年から7年。10月には板垣退助の自由党が結成されている。
大日本国憲法が施行されたのが1890年。その過程で、今の日本国憲法に通ずる憲法草案が論議されていた。














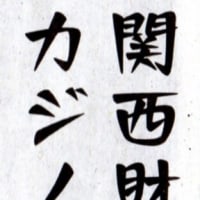









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます