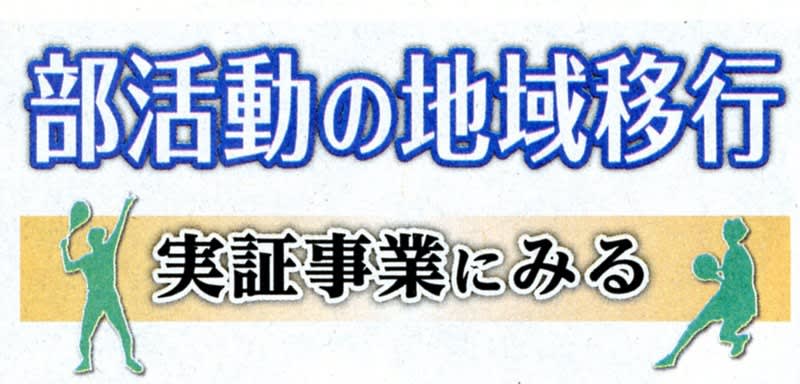後退する都民スポーツ(下) 学校プールの廃止 委託先閉鎖で困難も

小中学校のプールを廃止して水泳の授業を民間のスポーツクラブなどに委託する動きが東京都を中心に全国で起こっています。
日本共産党東京都議団は2023年、都内区市町村を対象に、小中学校のプール廃止に関する調査を行いました。学校プールの必要性や、廃止に伴い水泳授業を民間委託することの問題点を指摘しました。
調査によると、一部実施を含め、学校プールの廃止を「行っている」と回答したのが11自治体で、そのうち本格実施しているのは6自治体。廃止を「検討している」と回答したのは20自治体でした。夏休みのプール開放を実施していないのは30自治体で、うち13自治体が管理の困難さを理由にあげていました。
都議団は、これらの動きの背景に国がコスト削減や効率化を目的に進める「公共施設等総合管理計画」があると指摘しました。
小学校プールを全廃する方針の葛飾区では、24年度は26の小中学校で民間委託での水泳授業を実施しています。
民間委託は、民間10施設と区2施設で行われ、指導をするのは事実上いずれも外部委託された民間のインストラクターです。
指導は、泳力をつけるための反復が中心の形式にならざるを得ず、学習指導要領が示す、児童が相互に学び合うような授業ができていません。

プール授業の民間委託で使用されなくなった区立小学校のプール=東京都葛飾区
往復30分バス移動
委託していた民間プールが閉鎖し、新たな委託先に区外の施設を選ばざるを得なかったこともあり、安定して利用できない問題も浮上しています。
学校外は往復30分前後のバス移動が必要となり、児童も教師も時間に追われる実態があります。水泳授業前後の休み時間がつぶれたり、1時間目の水泳授業のために登校時間を早めたりする例もあるといいます。
小中共同方式なら
「子どもたちに学校プールを!葛飾連絡会」共同代表の高橋信夫さんは「江戸川区は、中学校に温水プールを設置し、そこを徒歩や短時間のバスで移動できる小学校が共同で使う計画です。この方式なら授業の外部委託をしないで済む。移動の負担も軽減し、中学校に温水プールができれば地域への開放もできる」と話し、共産党の議員団とも情報交換し、連携して取り組んでいます。
都議団はこの問題について都議会でも質問しました。「学校プールは地域スポーツの場としても重要」「授業が公営プールで行われるようになった自治体では、一般の方が入れる時間が制約され問題になっている」と実態を明かし、学校プールを廃止するのではなく、教員の負担を軽減しながら水泳授業の場、地域スポーツの場として充実させることを求めています。
(この連載は青山俊明と山崎賢太が担当しました)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2025年6月16日付掲載
「子どもたちに学校プールを!葛飾連絡会」共同代表の高橋信夫さんは「江戸川区は、中学校に温水プールを設置し、そこを徒歩や短時間のバスで移動できる小学校が共同で使う計画です。この方式なら授業の外部委託をしないで済む。移動の負担も軽減し、中学校に温水プールができれば地域への開放もできる」と話し、共産党の議員団とも情報交換し、連携して取り組んでいます。

小中学校のプールを廃止して水泳の授業を民間のスポーツクラブなどに委託する動きが東京都を中心に全国で起こっています。
日本共産党東京都議団は2023年、都内区市町村を対象に、小中学校のプール廃止に関する調査を行いました。学校プールの必要性や、廃止に伴い水泳授業を民間委託することの問題点を指摘しました。
調査によると、一部実施を含め、学校プールの廃止を「行っている」と回答したのが11自治体で、そのうち本格実施しているのは6自治体。廃止を「検討している」と回答したのは20自治体でした。夏休みのプール開放を実施していないのは30自治体で、うち13自治体が管理の困難さを理由にあげていました。
都議団は、これらの動きの背景に国がコスト削減や効率化を目的に進める「公共施設等総合管理計画」があると指摘しました。
小学校プールを全廃する方針の葛飾区では、24年度は26の小中学校で民間委託での水泳授業を実施しています。
民間委託は、民間10施設と区2施設で行われ、指導をするのは事実上いずれも外部委託された民間のインストラクターです。
指導は、泳力をつけるための反復が中心の形式にならざるを得ず、学習指導要領が示す、児童が相互に学び合うような授業ができていません。

プール授業の民間委託で使用されなくなった区立小学校のプール=東京都葛飾区
往復30分バス移動
委託していた民間プールが閉鎖し、新たな委託先に区外の施設を選ばざるを得なかったこともあり、安定して利用できない問題も浮上しています。
学校外は往復30分前後のバス移動が必要となり、児童も教師も時間に追われる実態があります。水泳授業前後の休み時間がつぶれたり、1時間目の水泳授業のために登校時間を早めたりする例もあるといいます。
小中共同方式なら
「子どもたちに学校プールを!葛飾連絡会」共同代表の高橋信夫さんは「江戸川区は、中学校に温水プールを設置し、そこを徒歩や短時間のバスで移動できる小学校が共同で使う計画です。この方式なら授業の外部委託をしないで済む。移動の負担も軽減し、中学校に温水プールができれば地域への開放もできる」と話し、共産党の議員団とも情報交換し、連携して取り組んでいます。
都議団はこの問題について都議会でも質問しました。「学校プールは地域スポーツの場としても重要」「授業が公営プールで行われるようになった自治体では、一般の方が入れる時間が制約され問題になっている」と実態を明かし、学校プールを廃止するのではなく、教員の負担を軽減しながら水泳授業の場、地域スポーツの場として充実させることを求めています。
(この連載は青山俊明と山崎賢太が担当しました)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2025年6月16日付掲載
「子どもたちに学校プールを!葛飾連絡会」共同代表の高橋信夫さんは「江戸川区は、中学校に温水プールを設置し、そこを徒歩や短時間のバスで移動できる小学校が共同で使う計画です。この方式なら授業の外部委託をしないで済む。移動の負担も軽減し、中学校に温水プールができれば地域への開放もできる」と話し、共産党の議員団とも情報交換し、連携して取り組んでいます。