日本時間で29日未明に、スマトラ島沖でマグニチュ―ド8・7の巨大地震が発生しました。被害の様子が刻々と各メデイアで伝わってきますが、昨年末の、大津波を起こした巨大地震の震源域のすぐ南東に隣接する地域で発生した模様で、地震による被害も甚大なものであることが、次第に判明しつつあります。
さて、地震のマグニチュードとは、地震の規模を表すものですが、マグニチュードには3種類の算定方法があるのは、皆さん、ご存知でしょうか?
そもそもマグニチュードは地震の規模を示す値です。1935年にアメリカの地震学者リヒターが考案しました。
リヒターの定義は、震源から100km離れた、特定の種類の地震計が記録した最大の針の振れはばの大きさを、マグニチュードとしました。ただし、実際には、地震計が震源からちょうど100km離れたところにあることはまずないので、距離によってマグニチュードの値を修正していました。
マグニチュードという値を作るときにリヒターが工夫したことは、地震の揺れは小さいものから大きいものまでさまざまなので、最大の振れはばの大きさをそのまま数字で表すのではなく、その数字のケタ数をマグニチュードとしたことです。ですから、巨大地震のマグニチュードも少ないケタ数で表すことができます。
リヒターがマグニチュードを考案した後、マグニチュードの求め方について別の提案があり、目的に応じて、さまざまなマグニチュードが生まれました。現在3通りのマグニチュードの算定方法があります。これらのマグニチュードは、基本的に同じ地震に対して同じ値になるように考案されたものでしたが、実際にはかなりの差ができてしまいました。
これらのマグニチュードについて以下紹介します。
①表面波マグニチュード
地震計で観測した地震波の周期(波の山が来てから次の山が来るまでの時間)が20秒程度の表面波の最大の揺れと、地震計と震央(震源ではない)との距離からマグニチュードを求める方法。
浅いところで発生した地震について用いるが、地震計の限界により大体M8.7~8.8以上の値を表せなく、巨大地震の規模を比較するのには向いていません。
日本の気象庁が発表している「気象庁マグニチュード」も深さ60キロより浅いものは、この表面波マグニチュードを取り入れています。
②実体波マグニチュード
地震計で観測した地震波の実体波(P波とS波)の最大の揺れと周期、震源の深さなどからマグニチュードを求める方法。
深発地震の規模を表すために用いられているが、やはりM8.7~8.8以上の値は表現できません 。日本の気象庁が発表している「気象庁マグニチュード」も深さ60キロより深いものは、この実体波マグニチュードを採用しています。
③モーメントマグニチュード
震源となった断層のずれの量、断層の面積、断層付近の岩盤の性質などの、断層運動からマグニチュード求める方法。
これらの値は、地震波を長い時間観測しなければ求められないので、モーメントマグニチュードは地震速報には用いられない。しかし、どんな大きな地震でも表せるので、巨大地震の規模はモーメントマグニチュードで表されることが多いですね。
ただ、このモーメントマグニチュードは、震源が深い地震は表現できない性質があります。
ちなみに、観測史上最大の地震は、1960年のチリ地震で、この地震のモーメントマグニチュードは9.5でしたし、昨年暮れの、スマトラ島沖地震は、モーメントマグニチュ―ドで9.0でした。
ちなみに昨今の海外の大地震発生時に、これらのマグニチュードをごっちゃにして各メデイアが報道しているように見うけられるふしもありますが、以上のようにどのマグニチュ―ドで算定したのか、はっきり明示するべきであると私は申しあげておきます。
さて、マグニチュードと地震のエネルギーの関係ですが、マグニチュードが1増えると、地震のエネルギーは約32倍になります。2増えれば、エネルギーは32倍の32倍ですから1000倍になります。つまり、M8の巨大地震のエネルギーは、マグニチュード6の中規模の地震1000回分に相当することになります。















 25日の日本列島各地では、一時的に冬型気圧配置が強まり、日本海側では各地で雪となりました。また、全国的に風が強く、伊豆諸島の三宅島では午前10時20分頃、最大瞬間風速34・7mを観測したほか、関東地方では、午前中、JR鹿島線の延方~鹿島神宮間で、運行規制値の25mを観測したため、列車の運行が見合わせとなったりしました。
25日の日本列島各地では、一時的に冬型気圧配置が強まり、日本海側では各地で雪となりました。また、全国的に風が強く、伊豆諸島の三宅島では午前10時20分頃、最大瞬間風速34・7mを観測したほか、関東地方では、午前中、JR鹿島線の延方~鹿島神宮間で、運行規制値の25mを観測したため、列車の運行が見合わせとなったりしました。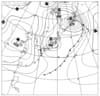 24日は、ポーラーロー(寒冷低気圧)が日本海を東進しました。このため、関東以西の各地では不安定な空模様となり、所々で一時的に強い雨や雷が発生しました。また、風も強まり、瞬間で30mを超す台風並の突風が吹いたところもありました。
24日は、ポーラーロー(寒冷低気圧)が日本海を東進しました。このため、関東以西の各地では不安定な空模様となり、所々で一時的に強い雨や雷が発生しました。また、風も強まり、瞬間で30mを超す台風並の突風が吹いたところもありました。