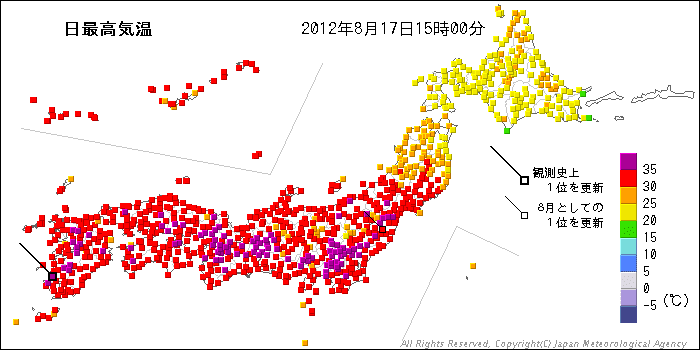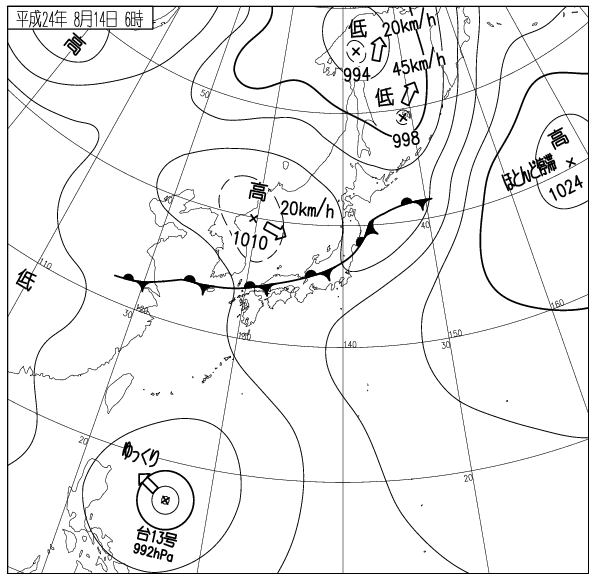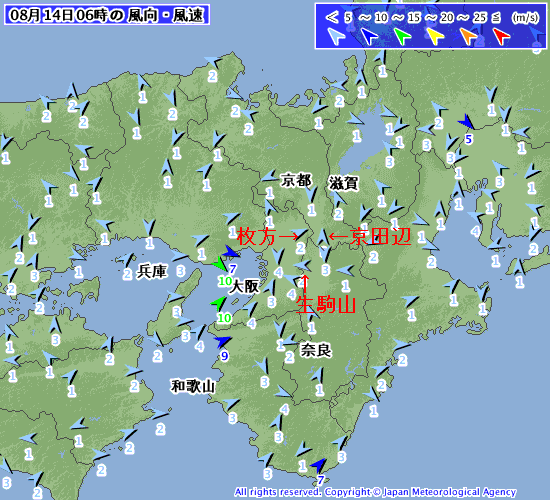引用図は8月31日21時48分フイリピン付近で発生した地震の震央分布図です。気象庁HPより引用・加工
8月31日21時48分頃、フイリピン付近フィリピン付近(北緯10・9度、東経127・1度)で、地震
の規模(マグニチュード)は7・9と推定される大きな地震がありました。
気象庁からは、太平洋津波監視センターからの情報を基に、岩手県~南西諸島、および、小笠原諸島に、津波注意報を発表されました。※ただ、フイリピン沿岸でも高さ数㎝の津波鹿観測されず、各地に発表されていた津波注意報は、1日未明までに全て解除されました。
東北地方太平洋沖地震に伴う大きな津波被害が記憶にまだ新しいですが、ここで、津波の特徴について、私なりにまとめてみました。
津波は、
◆うねりなどの、通常海上で発生している波の波長より、およそ1000倍もの非常に波長が長いもので、地震発生時の海底の地殻変動を受けて発生・伝播して行きます。(海底の深さが4分の1低くなると、津波の高さは2倍になるます※筆者調べ)
◆地震に伴う海底の地殻変動がより広範囲におよび、当該、地殻変動の量がより大きいほど、当該津波の波高はより高くなりますね。
逆に、
◆発生した地震の規模が大きくても、海底で大きな地殻変動を発生させなかった場合、発生する津波は小さいか、津波自体、発生しなくなってしまいます。
一方、地殻が破壊されて発生・伝播する地震(地震動)の強弱は、地殻の変動量・面積もさることながら、当該、地殻が変動する際の速度によって左右されます。
以上の理由から、厳密に単に地震の規模のみで、発生する津波の高さが左右されるわけではないことになります。