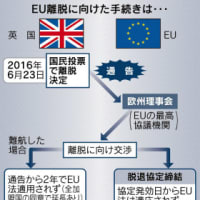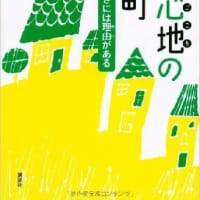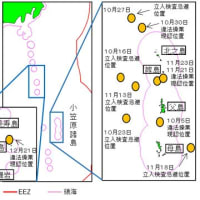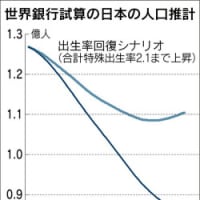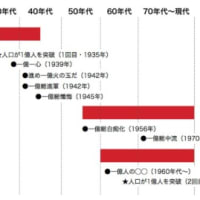「経済学者のサミュエルソンは、教科書『経済学』の冒頭で、経済とは、以下の問題であると指摘している。
『何を』(What)、
『いかにして』(How)、
『誰のために』(For Whom)」
「政治学者のラスウェルの著書題名『政治―だれが、何を、いつ、いかにして得るか』が示す様に、政治・外交の世界では、以下の契機が重要性を持つ。
『だれが』(Who)―行動主体
『いつ』(When)―タイミング」
(永井陽之助『“世界秩序”の時間的構造』「時間の政治学」所収)
従って、国際社会において、「近代化の地球化」によって生じた新たな諸問題―環境、資源、エネルギー、海洋、世界貿易、人権、南北問題等―のグローバルな課題は、誰にでも共通な普遍主義的な技術・経済の社会工学的な側面を重視する議論に繋がり易い。
しかし、これらの争点はTTP交渉に典型的に表れる様に、依然として国家間の「交渉」「協議」「対話」といった政治的活動によって、「政治的」に解決する他に無い問題なのだ。
国内問題も、国際的課題ほどではないが、然りである。また、国際問題とリンクして課題が提起されれば、その複雑化は一国を越える問題ともなる。この場合、“時間”の要因が強く働く。
最近、原発再稼働の課題が、漸く政治課題として取り上げられてきている。地震・津波による福島原発事故後、約4年、経済問題が政治問題として取り上げるまでの時間が必要だったのだ。
報道によれば、安倍首相は18日、参院本会議での代表質問で「国民生活や産業活動を守る責任あるエネルギー政策を実現するには、世論調査の結果だけをみて安易に原発ゼロというわけにはいかない」と述べ、政府方針通り原発再稼働を進める考えを示したとのことだ。
ご同慶の至りであるが、再稼働の必要性に関しての判断は今に始まったことではなく、福島原発事故がある程度の収束をみた後には、問題になっていたはずだ。特に、原油価格が今のように下落する前である。
今頃、大見得を切るが、首相として勇気を出さなければ行けない時期はとっくに過ぎている様に思える。行政が引いた路線を追認しただけで、政治的リーダーシップを発揮したわけではない。
また、再稼働の前提になる地元同意の対象範囲について、首相は「各地の事情がさまざまなので、国が一律に決めるのではなく、各地とよく相談して対応することが重要だ」と述べた。これも行政の書いた答弁書の棒読みの様だ。
これが日本の政治の象徴的側面になる。そこには、「行動主体」と「タイミング」の軌跡が刻まれているわけではなく、行政という執行機構の無名性と見えざる手による既成事実の積み重ねがあるだけだ。
ハンナ・アーレントの言葉を借りれば、“Ruled by Nobody”の世界なのだ。
『何を』(What)、
『いかにして』(How)、
『誰のために』(For Whom)」
「政治学者のラスウェルの著書題名『政治―だれが、何を、いつ、いかにして得るか』が示す様に、政治・外交の世界では、以下の契機が重要性を持つ。
『だれが』(Who)―行動主体
『いつ』(When)―タイミング」
(永井陽之助『“世界秩序”の時間的構造』「時間の政治学」所収)
従って、国際社会において、「近代化の地球化」によって生じた新たな諸問題―環境、資源、エネルギー、海洋、世界貿易、人権、南北問題等―のグローバルな課題は、誰にでも共通な普遍主義的な技術・経済の社会工学的な側面を重視する議論に繋がり易い。
しかし、これらの争点はTTP交渉に典型的に表れる様に、依然として国家間の「交渉」「協議」「対話」といった政治的活動によって、「政治的」に解決する他に無い問題なのだ。
国内問題も、国際的課題ほどではないが、然りである。また、国際問題とリンクして課題が提起されれば、その複雑化は一国を越える問題ともなる。この場合、“時間”の要因が強く働く。
最近、原発再稼働の課題が、漸く政治課題として取り上げられてきている。地震・津波による福島原発事故後、約4年、経済問題が政治問題として取り上げるまでの時間が必要だったのだ。
報道によれば、安倍首相は18日、参院本会議での代表質問で「国民生活や産業活動を守る責任あるエネルギー政策を実現するには、世論調査の結果だけをみて安易に原発ゼロというわけにはいかない」と述べ、政府方針通り原発再稼働を進める考えを示したとのことだ。
ご同慶の至りであるが、再稼働の必要性に関しての判断は今に始まったことではなく、福島原発事故がある程度の収束をみた後には、問題になっていたはずだ。特に、原油価格が今のように下落する前である。
今頃、大見得を切るが、首相として勇気を出さなければ行けない時期はとっくに過ぎている様に思える。行政が引いた路線を追認しただけで、政治的リーダーシップを発揮したわけではない。
また、再稼働の前提になる地元同意の対象範囲について、首相は「各地の事情がさまざまなので、国が一律に決めるのではなく、各地とよく相談して対応することが重要だ」と述べた。これも行政の書いた答弁書の棒読みの様だ。
これが日本の政治の象徴的側面になる。そこには、「行動主体」と「タイミング」の軌跡が刻まれているわけではなく、行政という執行機構の無名性と見えざる手による既成事実の積み重ねがあるだけだ。
ハンナ・アーレントの言葉を借りれば、“Ruled by Nobody”の世界なのだ。