文化人類学者・山口昌男は2013年3月10日に肺炎のため永眠、享年81歳。筆者が何かを付け加えようとするとき、既に関連が深かった知識人のコメントで覆い尽くされているように見える。しかし、十日経って、ふと、山口昌男を何者と表現するのかと考えた時に想い起こしたのは、ラジオ番組「日曜喫茶室」での文化人類学者ならぬ「ジンカブンルイガクシャ」と紹介されたとの発言であった。
そうだ!カセットテープにとっておいたはずだ!と思い立って探すと共にデッキは?すべて処分してしまったか!?幸なことに、家人がイヤホーンで聴くデッキを僅かに持っていた!テープは役に立ったのだ!
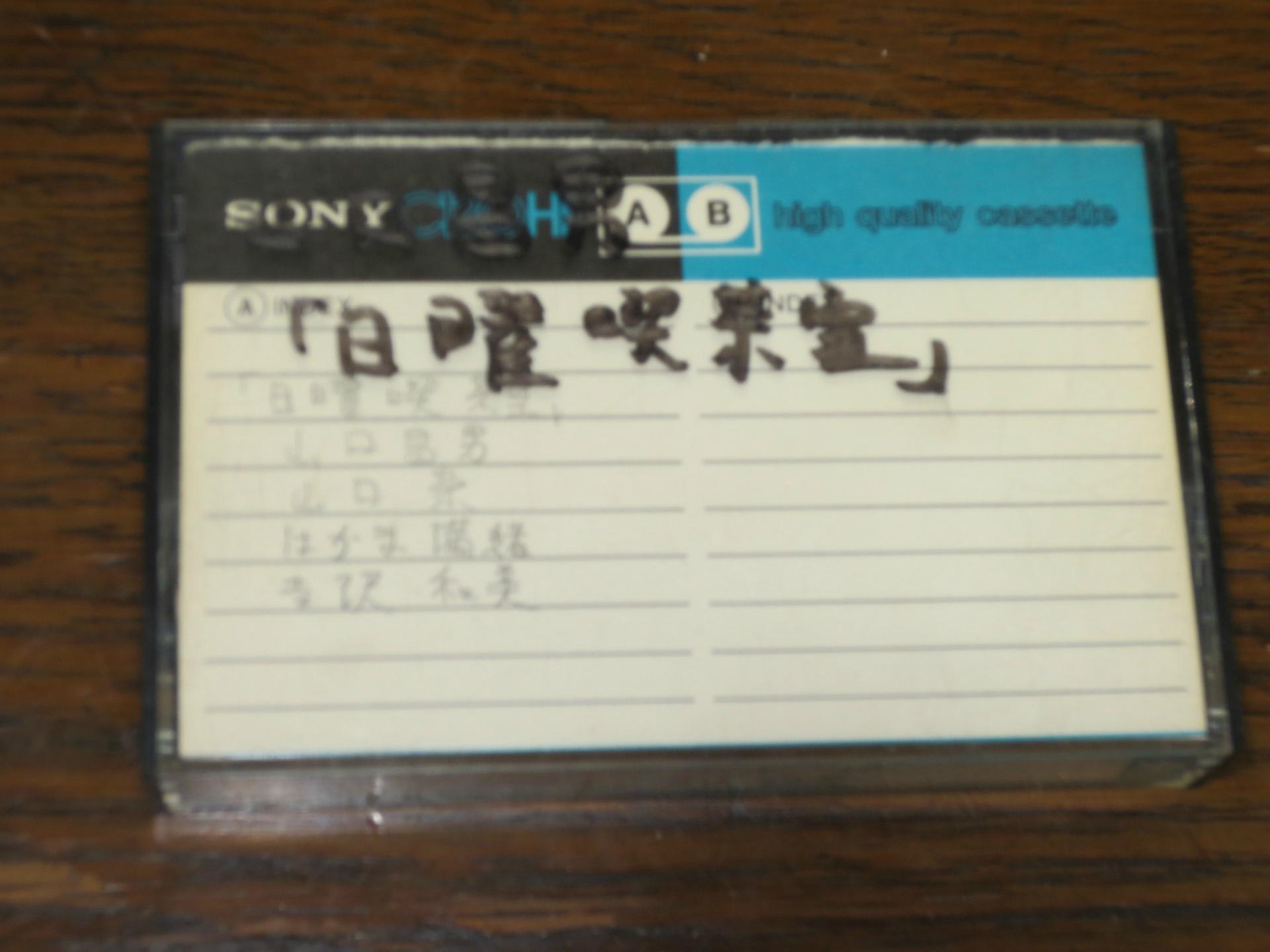
写真にあるようにテープはケースに収められており、表書きとして『日曜喫茶室』とある。当時は毎週の番組であり、家にいるときは良く聴いていた。その後も続き、今は月1回になったが、長寿番組として続いている。テープの欄に「NHKFM(79.4.1)」と書かれているから34年前のエプリルフール、山口昌男は47歳、東京外国語大教授として著作を中心にマスメディアにおいても大活躍していた頃である。
「山口昌男、山口崇(俳優)、はかま滿緒(マスター)、吉沢和美(ウェートレス)」と出演者の名前が書かれている。はかま滿緒の軽快な語り口とゲストを立てながらの受け答えの妙に、時折入れる音楽もマッチしているのが長寿の秘訣のようだ。その時の筆者は、番組表で山口昌男の名前をみて、満を持してテープを用意したのだろう。
山口昌男の場合、翌年7月27日にも財津一郎と共にゲストに招かれている。他にも、俳優・森繁久弥、ワヤン研究家・松本亮、狂言師・野村万作などのテープも残っている。俄然、楽しみが増えたようで嬉しい気分になった。
閑話休題。想い出しながら、聴いてみよう。
先ず、文化人類学者との紹介に、ある会合で誤って紹介された言葉を披露し「塵、芥を集めるクズ屋みたいなもの」「ドサ回り、モク拾いでゴミ箱から拾ってくる廃収品再生業」「塵化分類学者とは当っていないこともない」と彼は言い切った。
誤った言葉を飲み込んで新たなイメージを作り上げる処に氏の発想の真骨頂を見る思いがする。その後も山口崇とはかまを相手に、エピソードを縦横に展開し、吉沢アナが、その話の度に笑い転げていたのが印象的であった。学問的分野に拘らず、自らの感性の赴くままに関心の対象を広げ、それが彼の発想に起点と実は繋がっている。様々な“知的探検”からそれを統一的視点へ組み上げていく“知的冒険”へ、これが彼のプロフェッショナルとしての立ち位置になる。
筆者が本ブログのタイトルに採った“散歩から探検へ”はアマチュアの立ち位置である。しかし、プロは常に探検し、“探検から冒険へ”と志している。その一方で、彼は『アマチュアの使命』(「人類学的思考」(せりか書房)1971)も理解し、重視し、そして自らの立場に含ませている。あるいは出発点のアマチュアをプロとして発展させたという方が当たっているかもしれない。
フレイザー『金枝篇』を評して「…西欧の思想の中で研究の細分化と無関係にかつてアマチュアの学であり雑学の王者であった、未開社会の知恵が常に認識の地平線の拡大にための重要な要素を成して来た事…」との表現に接すれば、彼が間違いに直ぐに反応し、それ以上に「塵化分類学」という言葉を気に入ったことも理解できる。
番組のなかでも、インドネシアで痴漢と間違えられたこと、山口崇との出会いが芸能座の小沢昭二を介していることから、小沢との劇場での対談で麻布高校の先生(小沢氏の出身校)であったと話して先手を取ったこと、白土三平のマンガを日本で始めて批評したことから白土と週刊誌で対談し、その席で互いに似顔絵を競った後に角力を取ったこと、等を話している。これは単に面白いエピソードだけではなく、彼のフィールドワークのスタイルを開示するものだ。
しかし、この山口昌男のスタイルを引き継ぐ人材はどこにもいないようだ。それはアマチュアであることをとことん追求するプロであったと共に、プロであるが故に、巨匠であることにも拘った、彼の好奇心と執着心の所産かもしれない。結局、彼の著作を一言で言えば、塵化分類学者の一代記なのだ。
「山口昌男のページ」に今福隆太の弔辞が記載されている。回りに残った人たちは、確かに弔辞を述べるのに適した人たちであった。これは巨匠の運命かもしれない。今福は弔辞のなかで35年前に「先生」に始めて出遭ったと述べている。
しかし、「先生」と呼ばれる人だったのだろうか、山口昌男は?
インドネシアで登山中に行き倒れて現地の人間に偶然発見された「自分の死亡記事」を生前に書いた機知を有する人であった。これは自らが築いた巨匠というステータスに対する“挫折と敗北”の表現だったかもしれないと筆者は感じている。
そうだ!カセットテープにとっておいたはずだ!と思い立って探すと共にデッキは?すべて処分してしまったか!?幸なことに、家人がイヤホーンで聴くデッキを僅かに持っていた!テープは役に立ったのだ!
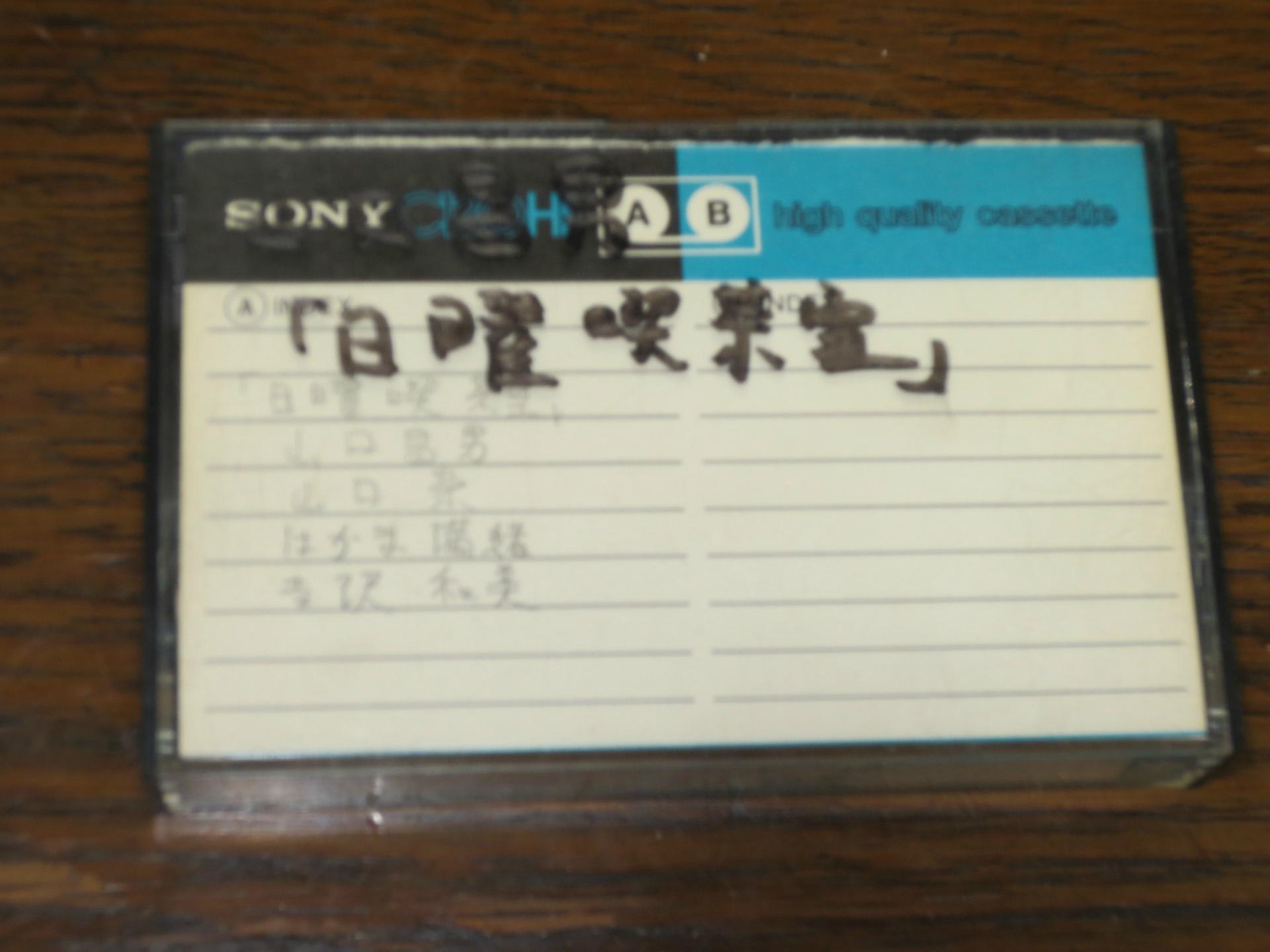
写真にあるようにテープはケースに収められており、表書きとして『日曜喫茶室』とある。当時は毎週の番組であり、家にいるときは良く聴いていた。その後も続き、今は月1回になったが、長寿番組として続いている。テープの欄に「NHKFM(79.4.1)」と書かれているから34年前のエプリルフール、山口昌男は47歳、東京外国語大教授として著作を中心にマスメディアにおいても大活躍していた頃である。
「山口昌男、山口崇(俳優)、はかま滿緒(マスター)、吉沢和美(ウェートレス)」と出演者の名前が書かれている。はかま滿緒の軽快な語り口とゲストを立てながらの受け答えの妙に、時折入れる音楽もマッチしているのが長寿の秘訣のようだ。その時の筆者は、番組表で山口昌男の名前をみて、満を持してテープを用意したのだろう。
山口昌男の場合、翌年7月27日にも財津一郎と共にゲストに招かれている。他にも、俳優・森繁久弥、ワヤン研究家・松本亮、狂言師・野村万作などのテープも残っている。俄然、楽しみが増えたようで嬉しい気分になった。
閑話休題。想い出しながら、聴いてみよう。
先ず、文化人類学者との紹介に、ある会合で誤って紹介された言葉を披露し「塵、芥を集めるクズ屋みたいなもの」「ドサ回り、モク拾いでゴミ箱から拾ってくる廃収品再生業」「塵化分類学者とは当っていないこともない」と彼は言い切った。
誤った言葉を飲み込んで新たなイメージを作り上げる処に氏の発想の真骨頂を見る思いがする。その後も山口崇とはかまを相手に、エピソードを縦横に展開し、吉沢アナが、その話の度に笑い転げていたのが印象的であった。学問的分野に拘らず、自らの感性の赴くままに関心の対象を広げ、それが彼の発想に起点と実は繋がっている。様々な“知的探検”からそれを統一的視点へ組み上げていく“知的冒険”へ、これが彼のプロフェッショナルとしての立ち位置になる。
筆者が本ブログのタイトルに採った“散歩から探検へ”はアマチュアの立ち位置である。しかし、プロは常に探検し、“探検から冒険へ”と志している。その一方で、彼は『アマチュアの使命』(「人類学的思考」(せりか書房)1971)も理解し、重視し、そして自らの立場に含ませている。あるいは出発点のアマチュアをプロとして発展させたという方が当たっているかもしれない。
フレイザー『金枝篇』を評して「…西欧の思想の中で研究の細分化と無関係にかつてアマチュアの学であり雑学の王者であった、未開社会の知恵が常に認識の地平線の拡大にための重要な要素を成して来た事…」との表現に接すれば、彼が間違いに直ぐに反応し、それ以上に「塵化分類学」という言葉を気に入ったことも理解できる。
番組のなかでも、インドネシアで痴漢と間違えられたこと、山口崇との出会いが芸能座の小沢昭二を介していることから、小沢との劇場での対談で麻布高校の先生(小沢氏の出身校)であったと話して先手を取ったこと、白土三平のマンガを日本で始めて批評したことから白土と週刊誌で対談し、その席で互いに似顔絵を競った後に角力を取ったこと、等を話している。これは単に面白いエピソードだけではなく、彼のフィールドワークのスタイルを開示するものだ。
しかし、この山口昌男のスタイルを引き継ぐ人材はどこにもいないようだ。それはアマチュアであることをとことん追求するプロであったと共に、プロであるが故に、巨匠であることにも拘った、彼の好奇心と執着心の所産かもしれない。結局、彼の著作を一言で言えば、塵化分類学者の一代記なのだ。
「山口昌男のページ」に今福隆太の弔辞が記載されている。回りに残った人たちは、確かに弔辞を述べるのに適した人たちであった。これは巨匠の運命かもしれない。今福は弔辞のなかで35年前に「先生」に始めて出遭ったと述べている。
しかし、「先生」と呼ばれる人だったのだろうか、山口昌男は?
インドネシアで登山中に行き倒れて現地の人間に偶然発見された「自分の死亡記事」を生前に書いた機知を有する人であった。これは自らが築いた巨匠というステータスに対する“挫折と敗北”の表現だったかもしれないと筆者は感じている。















