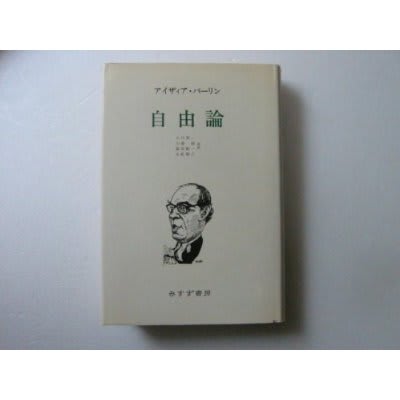岩波ホールで上映中の映画を鑑賞する前に、アーレントの本を振り返ったのだが、話がそこまで到達せずに、時間が経った。振り出しに戻って、「イェルサレムのアイヒマン」のアーレント自身による『あとがき』に触れる。
これは見開き、上から「ハンナ・アーレント」「大久保和郎訳」「エルサレムのアイヒマン」「悪の陳腐さに関する報告」「みすず書房」と書いてある。因みに1969/9刊行。下の写真はすべてアイヒマン、左から軍人時代、南米在住、エルサレム在だ。

副題の「悪の陳腐さに関する報告」に注目する。この裏に「A Report On the Banality of Evil」とある。これはあくまで報告なのだ。悪の陳腐さを論じたというよりも、アイヒマンという人間に顕著にみられたものを報告したのだ。
「私が悪の陳腐さをについて語るのはもっぱら厳密な事実の面において、裁判中、誰も目をそむける事ができなかった或る不思議な事実に触れているときである。」とアーレントは言う。
「アイヒマンはイヤゴーでもマクベスでもなかった。しかも<悪人になって見せよう>というリチャード三世の決心ほど彼に無縁のものはなかっただろう。自分の昇進にはおそろしく熱心だったという他に彼には動機もなかったのだ。そしてこの熱心さはそれ自体としては決して犯罪的なものではなかった。…彼は自分のしていることが全然わかっていなかったのだ。」
「彼は愚かではなかった。完全な無思想性―これは愚かさとは決して同じではないー、それが、彼があの時代の最大の犯罪者の一人となる素因だった。このことが<陳腐>であり、それのみか滑稽であるとしても、またいかに努力してもアイヒマンから悪魔的な底の知れなさを引き出すことは不可能だとしても、これは決してありふれたことではない。」これがアーレントによるアイヒマンの素描だ。
「無思想性と悪との奇妙な関連」とアーレントが言うとき、出版される前からの論争が、騒ぎだけが大きく、噛み合わないものであったことは容易に理解できる。『あとがき』には、抗議運動の対象になり、世論操作も動員され、論争のほうが運動の雑音の中に飲み込まれたとも言う。それは<克服されていない過去>であることを鮮やかに示している。
映画「ハンナ・アーレント」が「報告」それ自体の意味と騒ぎの中味とをどのように織り交ぜて描くのか興味深い処である。
これは見開き、上から「ハンナ・アーレント」「大久保和郎訳」「エルサレムのアイヒマン」「悪の陳腐さに関する報告」「みすず書房」と書いてある。因みに1969/9刊行。下の写真はすべてアイヒマン、左から軍人時代、南米在住、エルサレム在だ。

副題の「悪の陳腐さに関する報告」に注目する。この裏に「A Report On the Banality of Evil」とある。これはあくまで報告なのだ。悪の陳腐さを論じたというよりも、アイヒマンという人間に顕著にみられたものを報告したのだ。
「私が悪の陳腐さをについて語るのはもっぱら厳密な事実の面において、裁判中、誰も目をそむける事ができなかった或る不思議な事実に触れているときである。」とアーレントは言う。
「アイヒマンはイヤゴーでもマクベスでもなかった。しかも<悪人になって見せよう>というリチャード三世の決心ほど彼に無縁のものはなかっただろう。自分の昇進にはおそろしく熱心だったという他に彼には動機もなかったのだ。そしてこの熱心さはそれ自体としては決して犯罪的なものではなかった。…彼は自分のしていることが全然わかっていなかったのだ。」
「彼は愚かではなかった。完全な無思想性―これは愚かさとは決して同じではないー、それが、彼があの時代の最大の犯罪者の一人となる素因だった。このことが<陳腐>であり、それのみか滑稽であるとしても、またいかに努力してもアイヒマンから悪魔的な底の知れなさを引き出すことは不可能だとしても、これは決してありふれたことではない。」これがアーレントによるアイヒマンの素描だ。
「無思想性と悪との奇妙な関連」とアーレントが言うとき、出版される前からの論争が、騒ぎだけが大きく、噛み合わないものであったことは容易に理解できる。『あとがき』には、抗議運動の対象になり、世論操作も動員され、論争のほうが運動の雑音の中に飲み込まれたとも言う。それは<克服されていない過去>であることを鮮やかに示している。
映画「ハンナ・アーレント」が「報告」それ自体の意味と騒ぎの中味とをどのように織り交ぜて描くのか興味深い処である。