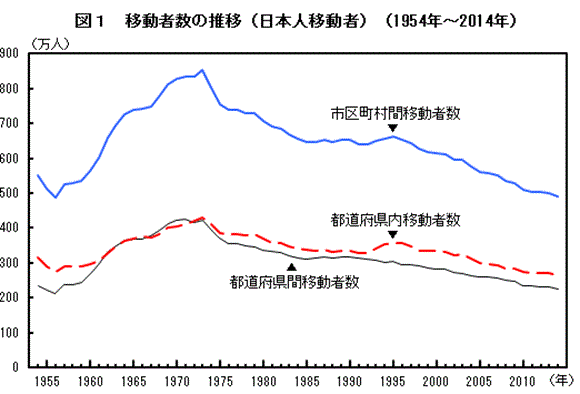ここのところ「イスラム国」問題に囚われて、表題の「戦争と革命」に関する永井陽之助の諸著作と関連の文献を読み返すのに精一杯で本ブログの更新が疎かになっている。
何か書こうとのアイデアは浮かぶのだが、何かまとまらず、どこかで筆が止まってしまう。勿論、筆者の未熟と致す処であり、判っているのだが、1年間程度の時間をフルに使って認識を新たにする必要があるな、との感想を禁じ得ない。
直ぐにはできないから、学び直したことから少しずつ、自分に明らかにすることを念頭において、書いていきたい。このブログも2011年5月2日に始めて、4年経過しているので、乗り換えて気分一新を図るか?考えてみよう。
さて、民族自決を際限なく進めていけば、世界が“バルカン化”する。更に、それに伴って、“確信者”の人間類型が見られる。様々な形で、少数者であるが、確認者を生みだし、それと共にバルカン化が進む。
『イスラム国による人質事件~世界の“バルカン化”150121』
報道によれば、イスラム国には、欧米諸国からも若者が集まるということだ。彼らは確信者なのだ。かつて、大学紛争の時代は、日本及び欧米諸国の国内において、確信者の群れが作られた。その中から、過激派集団が生み出され、日本国内の集団において、中核対革マル等の過激派内ゲバが始まった。その後、更にテロ、ハイジャックに及ぶことになった。
19世紀初頭、イベリア半島におけるナポレオンの侵略に対するスペインのパルチザンが、現代の「戦争と革命」におけるゲリラ戦の嚆矢であったことをC・シュミットは「パルチザンの理論」(1963)で指摘した。その闘いは、二つの大戦、レーニン革命、毛沢東革命、アルジェリア戦争、ベトナム戦争を通し、1978年のイラン革命以降のイスラム原理主義の対応に至るまで、継続している。
『現代ゲリラ戦の起源、19世紀初頭の半島戦争150205』
現代革命の政治哲学的理解を通して戦争と革命の関連を論じたのがH・アーレント「革命について」(中央公論社1975)であった。永井陽之助は『政治的人間』(「柔構造社会と暴力」所収)のエピグラムに「今日、世界を二分し、そこに多くが賭けられているコンテストにおいて、おそらく革命を理解するものが勝利を収めるだろう」とのアーレントとの言葉を掲げた。
『ハンナ・アーレント(3)~「革命論」についての永井コメント131125』
更に、永井は続けて以下の様に述べた。
「核兵器の出現によって、戦争を正当化する理由付けが一切不可能になった以上、逆に大国間の恐怖の均衡が、権力政治の手詰まりを生み出すに至った。そのため、暴力行使の内政化を生み、過去二十世紀を通じてよりも、もっと革命が重大なものになるという、女史の鋭い洞察とやや悲観的な危機意識のなかに、「革命について」の真価があるように思われる」。
永井はこれを約50年前の1968年に書いた(永井編「政治的人間」所収)。アーレントの「革命論」の原著は、その5年前の1963年に出版された。革命の重大性に対する両者の問題意識の「射程の長さ」は、今日のイスラム国の出現で明らかだ。
更に永井は次の様に述べる。
「今年(1978年―筆者注)始め、『フォーリン・アフェアーズ』がその56年にわたる長い歴史上初めて「号外」特集号を出した。「米国と世界―1978年」を特集したことが示す様に、スタンレー・ホフマン教授を含めて多くの論者が、1978年こそが戦後世界政治の一大転換期であることを認め、特に米中国交正常化とイラン革命の重要性を挙げている…」(「時間の政治学」(中央公論社1979)あとがき)。
動向の予測が、直ちに対応策に結びつくわけではない。しかし、深い理解によるに基づく予測はベターな政策に結びとけられることは確かだ。そうだとすれば、深い理解とは何であり、どのような見方が優れた予測の基盤になるのか、それを獲得する様に、優れた先人の努力の軌跡を辿ることが一つの方法になるはずだ。
何か書こうとのアイデアは浮かぶのだが、何かまとまらず、どこかで筆が止まってしまう。勿論、筆者の未熟と致す処であり、判っているのだが、1年間程度の時間をフルに使って認識を新たにする必要があるな、との感想を禁じ得ない。
直ぐにはできないから、学び直したことから少しずつ、自分に明らかにすることを念頭において、書いていきたい。このブログも2011年5月2日に始めて、4年経過しているので、乗り換えて気分一新を図るか?考えてみよう。
さて、民族自決を際限なく進めていけば、世界が“バルカン化”する。更に、それに伴って、“確信者”の人間類型が見られる。様々な形で、少数者であるが、確認者を生みだし、それと共にバルカン化が進む。
『イスラム国による人質事件~世界の“バルカン化”150121』
報道によれば、イスラム国には、欧米諸国からも若者が集まるということだ。彼らは確信者なのだ。かつて、大学紛争の時代は、日本及び欧米諸国の国内において、確信者の群れが作られた。その中から、過激派集団が生み出され、日本国内の集団において、中核対革マル等の過激派内ゲバが始まった。その後、更にテロ、ハイジャックに及ぶことになった。
19世紀初頭、イベリア半島におけるナポレオンの侵略に対するスペインのパルチザンが、現代の「戦争と革命」におけるゲリラ戦の嚆矢であったことをC・シュミットは「パルチザンの理論」(1963)で指摘した。その闘いは、二つの大戦、レーニン革命、毛沢東革命、アルジェリア戦争、ベトナム戦争を通し、1978年のイラン革命以降のイスラム原理主義の対応に至るまで、継続している。
『現代ゲリラ戦の起源、19世紀初頭の半島戦争150205』
現代革命の政治哲学的理解を通して戦争と革命の関連を論じたのがH・アーレント「革命について」(中央公論社1975)であった。永井陽之助は『政治的人間』(「柔構造社会と暴力」所収)のエピグラムに「今日、世界を二分し、そこに多くが賭けられているコンテストにおいて、おそらく革命を理解するものが勝利を収めるだろう」とのアーレントとの言葉を掲げた。
『ハンナ・アーレント(3)~「革命論」についての永井コメント131125』
更に、永井は続けて以下の様に述べた。
「核兵器の出現によって、戦争を正当化する理由付けが一切不可能になった以上、逆に大国間の恐怖の均衡が、権力政治の手詰まりを生み出すに至った。そのため、暴力行使の内政化を生み、過去二十世紀を通じてよりも、もっと革命が重大なものになるという、女史の鋭い洞察とやや悲観的な危機意識のなかに、「革命について」の真価があるように思われる」。
永井はこれを約50年前の1968年に書いた(永井編「政治的人間」所収)。アーレントの「革命論」の原著は、その5年前の1963年に出版された。革命の重大性に対する両者の問題意識の「射程の長さ」は、今日のイスラム国の出現で明らかだ。
更に永井は次の様に述べる。
「今年(1978年―筆者注)始め、『フォーリン・アフェアーズ』がその56年にわたる長い歴史上初めて「号外」特集号を出した。「米国と世界―1978年」を特集したことが示す様に、スタンレー・ホフマン教授を含めて多くの論者が、1978年こそが戦後世界政治の一大転換期であることを認め、特に米中国交正常化とイラン革命の重要性を挙げている…」(「時間の政治学」(中央公論社1979)あとがき)。
動向の予測が、直ちに対応策に結びつくわけではない。しかし、深い理解によるに基づく予測はベターな政策に結びとけられることは確かだ。そうだとすれば、深い理解とは何であり、どのような見方が優れた予測の基盤になるのか、それを獲得する様に、優れた先人の努力の軌跡を辿ることが一つの方法になるはずだ。