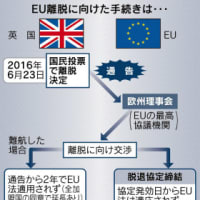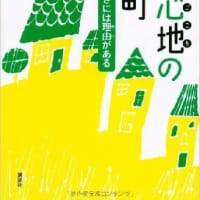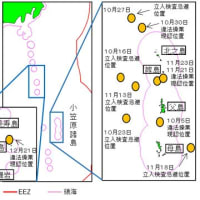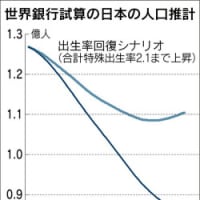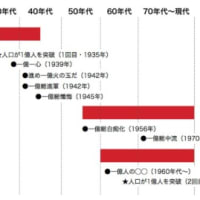重冨たつや議員(川崎市議会)主宰、市民参加可能な研究会(6月)の続きになる。
筆者が見出した以下の問題点の二番目について述べる。
1)生活保護との表現が意味する処→個人の活動領域(=生活)全体を監理する
2)憲法25条における「文化」とは→生存権の中での位置
3)捕択率(保護世帯数/保護水準以下の世帯数)が低い(~15%)→何故?
生活保護法の最初は憲法25条から始まることは周知だ。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
そして、幾つかの訴訟が最高裁まで進み、生存権に関する判断が下されている。しかし、「文化的」とは何かについて議論された様子はみられない。
憲法のなかで他に「文化」と書かれた箇所を探してみたがなかった。法律・政治の世界では文化は無縁なのだろう。そこで「日本国憲法25条、文化的」でネット検索した処、最初の画面に以下の研究の「レジメ」が記載されていた。
「日本国憲法第25条「文化」概念の研究 ―文化権(cultural right)との関連性―」
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/postgraduate/database/2017/6187.html
そのレジメの中で、特に「文化権」の概念及び「憲法成立過程の議論」が生活保護の内容の再定義を迫るものに感じた。特に後者において、その研究で著者は以下のように述べる。
憲法第25条第1項はGHQ案には存在せず、国会審議の過程で社会党提案によって挿入された。日本国憲法成立過程では、憲法第25条に限らず「文化」が論じられる場面が多々あり、その中でも頻繁に用いられたのは「文化国家」論であり、“附帯決議”でも言及された。
憲法25条第1項への挿入の立役者は森戸辰男と鈴木義男だ。彼らは生存をつなぐのに留まらない生活を表現するのに「文化」という文言を用いていた。特に鈴木は「人格的生存権」を提唱し、単なる生存とは明確に区別する立場をとる。
大正期に広まった「文化」概念は文化主義論争等の議論を通じて、人間のよりよい生の実現を目指す理念として、生活と結びついてその理想を語るものとして用いられた。日本国憲法第25条は、生存維持を保障される権利と、文化的生活を保障される権利を一体として生存権として保障すべきという回答を出したと言える。
しかし制定後の学説・判例において、第25条第1項は単なる経済的な生存維持に矮小化していった。その遠因として、生存権と生活権の区別の不徹底が挙げられる。
著者の結論は見事であり、大きな問題的だと筆者は考える。
また、著者は文化権の視点から議論を進めており、法律学者の対応も求められる。
以上の議論を踏まえ、その再定義として例えば、文化的生活の基盤として「平日と休日」の区別、文化人類学的な「ハレ」と「ケ」の循環、具体的には地域における展覧会、音楽会、美術展、遊園地等の休日券配布を考え、また、本人の研鑚、子弟の教育等の援助等の必要制をと筆者は考える。