
12月2日(日)晴れ【ダライ・ラマ14世講演録-kamenoさんのブログ紹介】
ダライ・ラマ14世(1935年7月6日生まれ)が11月に来日されていた。全日本仏教徒会議神奈川大会の特別記念講演での講演録を、kamenoさんがまとめてくださった。そのブログを風月庵だよりにご訪問下さった皆様にもご紹介させていただく許可をいただきましたので、kamenoさんのブログにここからご訪問下さい。おまとめになるのは大変なご苦労であったと存じます。大変に素晴らしい講演録です。
Kameno's Digital Photo Log
その前に、ダライ・ラマ14世について少しだけプロフィール:法名はテンジン・ギァツォ。2歳の時、転生の活仏ダライラマ14世と認められる。5歳より在位。チベット仏教ゲルグ派の最高位の仏教博士号(ゲシェ・ラランパ)を持つ。1949年中華人民共和国の人民解放軍がチベットに侵攻してくる。チベット独立運動を展開するが、1959年にはインドに亡命する。ダライ・ラマ14世がインドに亡命したあとのチベットは中華人民共和国に統合されてしまっている。現在はインドのダラムサーラにチベット亡命政府を樹立している。1989年、ノーベル平和賞を受賞。中国のチベット侵略と現在も行われているチベット人への人権侵害に対して批判をし続け、チベット問題の平和的解決を世界に訴え続けている。
(この土曜と日曜日は、20年来の友人である韓国の陳本覺(永裕)法尼ー中央僧伽大学教授ーが来日していて、昨日は東アジア仏教研究会での研究発表と、今日は東京見物を楽しみましたので、ブログの記事は書けませんが、kamenoさんのブログに委ねます。)
ダライ・ラマ14世(1935年7月6日生まれ)が11月に来日されていた。全日本仏教徒会議神奈川大会の特別記念講演での講演録を、kamenoさんがまとめてくださった。そのブログを風月庵だよりにご訪問下さった皆様にもご紹介させていただく許可をいただきましたので、kamenoさんのブログにここからご訪問下さい。おまとめになるのは大変なご苦労であったと存じます。大変に素晴らしい講演録です。
Kameno's Digital Photo Log
その前に、ダライ・ラマ14世について少しだけプロフィール:法名はテンジン・ギァツォ。2歳の時、転生の活仏ダライラマ14世と認められる。5歳より在位。チベット仏教ゲルグ派の最高位の仏教博士号(ゲシェ・ラランパ)を持つ。1949年中華人民共和国の人民解放軍がチベットに侵攻してくる。チベット独立運動を展開するが、1959年にはインドに亡命する。ダライ・ラマ14世がインドに亡命したあとのチベットは中華人民共和国に統合されてしまっている。現在はインドのダラムサーラにチベット亡命政府を樹立している。1989年、ノーベル平和賞を受賞。中国のチベット侵略と現在も行われているチベット人への人権侵害に対して批判をし続け、チベット問題の平和的解決を世界に訴え続けている。
(この土曜と日曜日は、20年来の友人である韓国の陳本覺(永裕)法尼ー中央僧伽大学教授ーが来日していて、昨日は東アジア仏教研究会での研究発表と、今日は東京見物を楽しみましたので、ブログの記事は書けませんが、kamenoさんのブログに委ねます。)














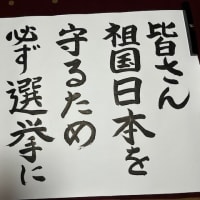





生まれながらに後光が射していたのでしょうか。
他の宗教にありがちな、世襲や閥の中で決めるのではないのは、素晴らしいですね。また幼少にして見出された本人が、裏切ることなくダライラマとして大成するのが不思議です。密教の面目躍如と言うことでしょうか。
彼の力ある声にシンパシーを感じたものの・・・私の力不足でしょうが、清々しさや明るい爽やかなものを見出す事はできませんでした。
京都の夜は、楽しかったです。
しかし、若いときから、チベット民族の生活を何とかしなくてはならない立場に立たれた法王は、単に仏教僧侶の感覚だけでは生きてこられなかったであろうと、私は思います。なんの経済的なバック無しに多くの人々の生活が、法王の肩に掛かっているのですから、普通の神経ではいられないでしょう。また政治的な能力も使わなくてはならないでしょう。
チベットに中国が侵入しなければ、法王の感じも違ったのではないかと思うのですが。
昔、「セヴンイヤーヅ イン チベット」という映画で、ブラッド・ピットの相手をした法王の少年時代をブータンの外相の息子さんが演じましたが、少年時代はあの映画の少年のように清々しかったであろうと想像します。
どのような人生であったかによって、感じは随分変わるように思います。ちょっとそんなことを思いました。
また幼児のどこを見て生まれ変わりと判定されるのでしょうか。
結果として、当たり外れなく、成長して立派な指導者になるのですから、見るポイントがあるのでしょうね。
見いだすポイントについて、以前読んだことがありますが、例えば、亡くなったその人しか知らないことを知っていたり、とか、何かしらの決め手があるようです。ダライラマ法王も何代か前には、法王になるよりも詩人に向いていたような方もいらっしゃったようです。
今の法王は、まさにインドに亡命しなくてはならないという事態が起きるような時代にあっていた方ではないでしょうか。線が細すぎても勤まらなかったことでしょう。
これは「転生活仏(てんしょうかつぶつ)」の制度はチベットで考え出されたものです。14世紀中頃といわれています。チベットで仏教が生き続けていくために、考え出された制度のようです。
「生前に高い次元に到達した僧侶が、衆生を救済するために、この世に何度でも生まれ変わって、指導的な地位につくという制度」(『マンダラとは何か』正木晃著60頁)
たまたま今日この本を読んでいましたら、このような事が書いてありましたので、書き足しました。