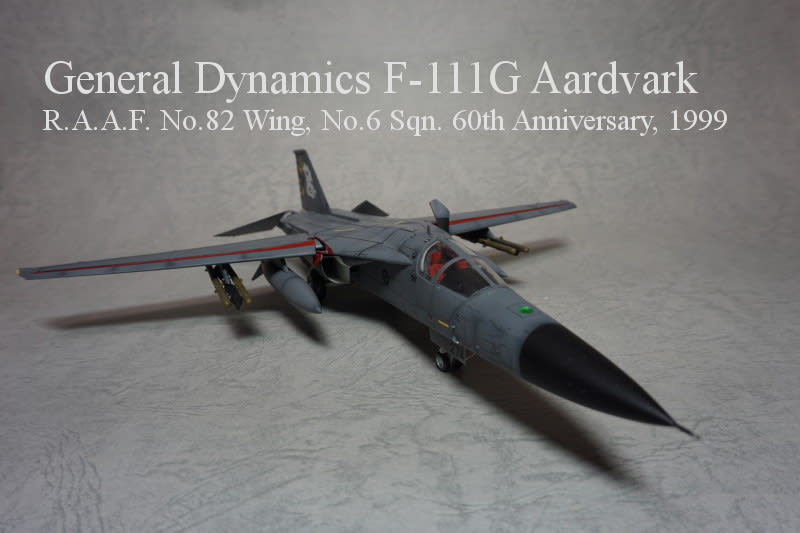キット:カナックモデル CF-18Aホーネット バトル・オブ・ブリテン塗装
仕 様:カナダ空軍デモチーム 2015年バトル・オブ・ブリテン特別塗装機#188761
カナダ空軍にはCF-18Aを用いたデモチームが存在します。主にカナダとアメリカ各地の航空ショーで展示飛行をして、空軍の広報活動等をしています。このチームに在籍しているCF-18Aは、毎年異なる特別塗装を纏って飛行しています。
2015年の特別塗装は、第二次世界大戦中の1940年、イギリスとドイツで戦われた大航空戦「バトル・オブ・ブリテン」にイギリスが勝利してから65周年にあたることから、当時の戦闘機を模した迷彩塗装が機体上面に描かれています。
この戦闘にはカナダ空軍もイギリス連邦の一員として参戦していて、カナダ空軍第1飛行隊(イギリス空軍第1飛行隊と混同してしまうため1941年に第401飛行隊に改名)が約100名の兵士とホーカー・ハリケーンMk Iと共に派遣されました。
この記念塗装は、その第1飛行隊に配備されていたハリケーンMk Iを再現したものです。スピットファイアと混同しがちですが、主翼前縁に描かれているダミーの機関銃の配置を見れば、これがハリケーンを元にしているのが分かるはずです。また、側面に上半分だけ書かれている飛行隊コード「YO」は第1飛行隊を表しています。
2015年、私はBC州コモックスの航空ショーでこの機体の展示飛行を目の当たりにしました。戦闘機らしいパワフルな機動に魅せられてすっかりこの機体が気に入ってしまい、これのプラモデルが発売されるとネットで知った時にはすかさず予約をして購入しました。
キットはすぐに手に入ったものの、当時はまだエアブラシ環境がなかったためしばらくお蔵入り。エアブラシを手に入れた後も失敗が怖かったのでその後も押し入れの奥に。そうこうしているうちにBoBから70年経ってしまいました。そろそろ作ってもよかろうと押し入れから引っ張り出してきて、ようやく完成させることができました。
カナダにまつわるプラモデルを作るのはこれが初めて(カナダにいた時にミニクラフトのホーネットを作ったけどあれは・・・)。今まで温存してきましたがここから一転攻勢、色々な機体を作っていこうと思います。

ジェット戦闘機に茶色と緑色の迷彩というのは、実際のところアメリカ空軍の東南アジア迷彩と混同しそうな気がしないこともないです。色味は全然違うんですけどね。

迷彩柄は見た感じではハリケーンに合わせているようですが、平面形は当然ハリケーンとホーネットでは異なるので(特に主翼の位置は前後している)、そこはアレンジしています。でも見る人が見れば、スピットじゃなくてハリケーンの迷彩だなと分かると思います。

機体下面は通常のCF-18と同じ灰色です。ハリケーンではスカイ一色でした。
成形品はアカデミー製なのですが、噂に違わぬ組みやすさとディテールでした。確かにこれは1/72レガシーホーネットの決定版ですね。CF-18独特の微妙な違いも再現できますし。残りのCF-18を作るために複数在庫しておきたいくらい。

CF-18の独自装備として機首左舷には探照灯が装備されています(761の右隣)。夜間に北極圏からやってくるソ連の爆撃機を識別するために追加したんだそうな。

YO◎Hの機体コードが書かれていますが、なぜか上半分だけ。全部書くと特に蛇の目がイギリス機と誤認される恐れがあったから?
LERXフェンスには、この機体の所属する第425戦術戦闘飛行隊「アロエッツ」の文字が書かれています。

垂直尾翼には肖像画が描かれています。左の人物はジョージ・ドナン軍曹。右の人物は当時のイギリス首相ウィンストン・チャーチルです。

右側の垂直尾翼も同様。第1飛行隊のパイロット、ゴードン・ロイ・マグレガー中尉が描かれています。

尾部です。

尾部。

主翼。国籍章はカナダ空軍のものを当時のイギリス空軍の色使いにアレンジしたものが貼られています。これはナイスだと思います。
前縁にはハリケーンの片側4連装機銃が描かれています。これが、ハリケーンが元になっていると断言できる部分です。

近年のCF-18の機首にはIFFアンテナが追加されています。新造時には無かったので、最近になって追加取付されたと思います。ここらへんの作り分けは少し面倒なところです。ハセガワのレガシーホーネットにはIFFアンテナは再現されていないので少し難儀しそうです。まあプラバンで再現できそうな形状なのですが、素組で作ろうとしたら1/72だったらアカデミー、1/48だったらキネティックが好適なのかなと思います。

左主翼。

以上、CF-18Aホーネット カナダ空軍 バトル・オブ・ブリテン75周年記念塗装でした。