「市役所の年内業務も明日でおしまい」という27日、職員さんから嬉しい報告を聞きました。
南海中央線北伸事業についてです。
南海中央線は、岸和田・堺を結ぶ都市計画道路、その一部である泉大津市域は3つに分割して事業実施、真ん中の部分は4車線道路としてすでに共用されています。
今、推進中の事業は、高石市へつながる北伸部分。
当初の事業期間は1999年から2005年とされていましたが、その後延長し、2012年が完成予定となっています。
「報告」は、これをさらに1年間延長し、2013年度末とするとともに、当初の「片側2車線、4車線」を変更し、片側1車線として、歩道、植樹帯、自転車道を広くするというものです。
歩道3.5メートル、植樹帯1.75メートル。かなり、ゆったりしたものです。
この事業に市が取り組み始めたのは「11年ぶりで、一般会計の赤字」に転落した時期。
松ノ浜の再開発を市が事業主体となってすすめ、総事業費60億円余といわれた、道路建設に踏み出す。「赤字解消の財政再建計画」を掲げながら、借金を膨らませて建設事業推進。
日本共産党は「無謀な財政破綻の道」と警鐘乱打、反対を続けました。
道路の建設用地に家を持っておられる方が、住みなれた土地を離れて行かれました。
莫大な投資をし、大きな犠牲を伴いながら進める事業であるなら、なおいっそう将来に市民の財産として残すものでなければなりません。
だから「反対」するだけでなく、「ここに幅員25メートル、4車線道路が必要でしょうか?」という、問題提起を続けてきました。
最初は「国の補助金を受けている事業なので、計画変更は困難」(ほとんど無理というニュアンスの「困難」)という答弁が繰り返されました。
その後、都市計画マスタープランが市民参加で作られたときも、「道づくり」は、大きなテーマになりました。市民グループのプロジェクト・チームもつくられ「2車線にして歩道と緑道を充実させる」提言がされました。
地元自治会の皆さんの要望もありました。
それらを受けて、2006年6月議会で、特に環境問題との関係で「2車線化」への変更を求めました。環境対策を所管する市民産業部長から「交通渋滞を解消するための道作りは、もちろん大切なことでございますけれども、まず私たち一人一人が湯酔うな車を使用しないタイフスタイルの確立、それと同時に歩行者、自転車等に優しい道づくり、まちづくりが必要である。これが環境の立場からの道路交通問題に対する基本的な考え方と思っております。」という答弁がありました。
都市計画決定は1959年。半世紀たったら、道路環境も、人々の価値観も変わります。
あきらめずに、「ここに必要なのは、車のため道路ではない。安心して歩ける歩行者のための道を」と言い続けてきてよかったと思います。
南海中央線北伸事業についてです。
南海中央線は、岸和田・堺を結ぶ都市計画道路、その一部である泉大津市域は3つに分割して事業実施、真ん中の部分は4車線道路としてすでに共用されています。
今、推進中の事業は、高石市へつながる北伸部分。
当初の事業期間は1999年から2005年とされていましたが、その後延長し、2012年が完成予定となっています。
「報告」は、これをさらに1年間延長し、2013年度末とするとともに、当初の「片側2車線、4車線」を変更し、片側1車線として、歩道、植樹帯、自転車道を広くするというものです。
歩道3.5メートル、植樹帯1.75メートル。かなり、ゆったりしたものです。
この事業に市が取り組み始めたのは「11年ぶりで、一般会計の赤字」に転落した時期。
松ノ浜の再開発を市が事業主体となってすすめ、総事業費60億円余といわれた、道路建設に踏み出す。「赤字解消の財政再建計画」を掲げながら、借金を膨らませて建設事業推進。
日本共産党は「無謀な財政破綻の道」と警鐘乱打、反対を続けました。
道路の建設用地に家を持っておられる方が、住みなれた土地を離れて行かれました。
莫大な投資をし、大きな犠牲を伴いながら進める事業であるなら、なおいっそう将来に市民の財産として残すものでなければなりません。
だから「反対」するだけでなく、「ここに幅員25メートル、4車線道路が必要でしょうか?」という、問題提起を続けてきました。
最初は「国の補助金を受けている事業なので、計画変更は困難」(ほとんど無理というニュアンスの「困難」)という答弁が繰り返されました。
その後、都市計画マスタープランが市民参加で作られたときも、「道づくり」は、大きなテーマになりました。市民グループのプロジェクト・チームもつくられ「2車線にして歩道と緑道を充実させる」提言がされました。
地元自治会の皆さんの要望もありました。
それらを受けて、2006年6月議会で、特に環境問題との関係で「2車線化」への変更を求めました。環境対策を所管する市民産業部長から「交通渋滞を解消するための道作りは、もちろん大切なことでございますけれども、まず私たち一人一人が湯酔うな車を使用しないタイフスタイルの確立、それと同時に歩行者、自転車等に優しい道づくり、まちづくりが必要である。これが環境の立場からの道路交通問題に対する基本的な考え方と思っております。」という答弁がありました。
都市計画決定は1959年。半世紀たったら、道路環境も、人々の価値観も変わります。
あきらめずに、「ここに必要なのは、車のため道路ではない。安心して歩ける歩行者のための道を」と言い続けてきてよかったと思います。











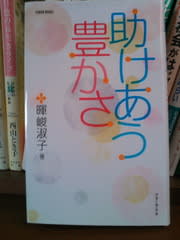


 ・・・大活躍です。
・・・大活躍です。
 にあわせて踊ります
にあわせて踊ります








