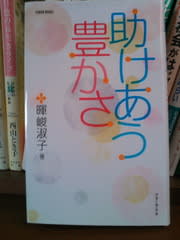
大阪中央会計事務所が「秋の文化行事」として開催した講演会、「豊かさと貧困」の講義録をもとに加筆。編集されたもの。
一会計事務所が、毎年事務所をあげて一般市民向けの行事を企画し、続けていることに感嘆する。そんな事務所と、著者、そして講演会に参加した人たちの想いが生み出した一冊。2011年の終わりにいい本に出合えたと思う。
今年をあらわす漢字は「絆」だという。
3・11のあと、「被災地で助け合う人たち」「やむにやまれず駆けつけるボランティア」を、社会保障への公的責任を縮小する口実にする政府の文書に、情けない思いがした。
本書で語られる「助けあい」とは、そんなものとは違う。
著者は日本がバブル経済に浮かれる時代から「豊かさとは何か」(「岩波新書 1989年)などの著書で、人間と社会のあり方について警鐘を鳴らし続けてきた。それらを、今読み直してみたいとも思った。
自分自身のことをふり返る。
高校を卒業し、一年間、東京の予備校に通った。
隣の席に座った人が、常に「競争相手」であることに、寒々とした思いがした。
一浪ののち、入学したした大学でも、孤独感におしつぶされるような気がした。
民青同盟やサークル活動、学生自治会の活動の中に入っていったときに「人と人との関係の中で生きる」ということの意味を考えた。
分断すること。連帯させないことが反動勢力の攻撃なのだということを知った。
絆を取り戻し、人と手をつなぎなおしたいと心から思った。
「助けあうことは、人間の本性であり、喜びなのです」という著者の言葉を、かみしめたい。
著者:暉峻淑子(てるおか・いつこ) 埼玉大学名誉教授。経済学博士。著書「豊かさとは何か」「豊かさの条件」(岩波新書)、「サンタクロースってほんとにいるの?」(福音館書店)など。
発行;フォーラム・A
















