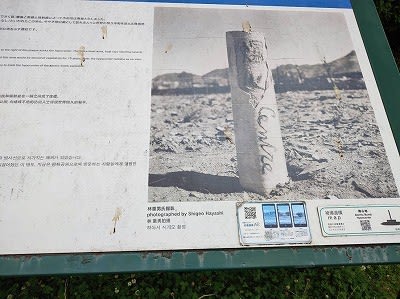建設中の「長崎スタジアムシティ」を外から眺める。



今回の長崎行きの大きな目的は、ジャパネットホールディングスが長崎市で開発を手掛ける複合施設「長崎スタジアムシティ」が2024年10月14日に開業するので事前にどのようなものかを見てみたいとの思いがあった。
水戸ホーリーホックを応援することのきっかけは「街起こし」として「ホーム&アウェイ」(双方向で町を訪ねる)であること。
勝敗はともかく、応援という名目で見知らぬ街を訪ねることが出来る。
が、旅好きに私に向いている。と感じたから。
水戸でも独自のスタジアム計画が有るようだし、行けば何かしら得るところがあるかも。
と、出かけたのだ。


完成予想図
長崎スタジアムシティは三菱重工業の長崎造船所幸町工場跡地の再開発で、敷地面積は約7万5000平米。収容人数約2万席のV・ファーレン長崎のサッカースタジアムを中心に、同約6000席の長崎ヴェルカのアリーナ、地上7階建て約90店舗の商業棟、同14階建て243室のホテル、同12階建てのオフィス棟で構成する。
延べ床面積は約19万4000平米。
数字を並べてもピンとは来ないが、近づいてみると巨大な複合施設だ。
ニッポンハムファイターズの「エスコンフィールドが話題を呼んでいるが、それ以上の内容に感じられる。
連絡道路も整備中だが、道路の間際までビルが建っていて、市街とスタジアムが共存している。


長崎駅から市電で2つ目の「宝町駅」が最寄駅で、長崎駅から徒歩でも15分位で歩けそうな距離だ。
*EYストラテジー・アンド・コンサルティングが算出によれば「長崎スタジアムシティ」の経済効果は、建設時が約1,436億円、開業後は13,000人の雇用により、963億円と推計している。
また、スタジアムシティの年間利用者数は850万人(目標)を想定している。