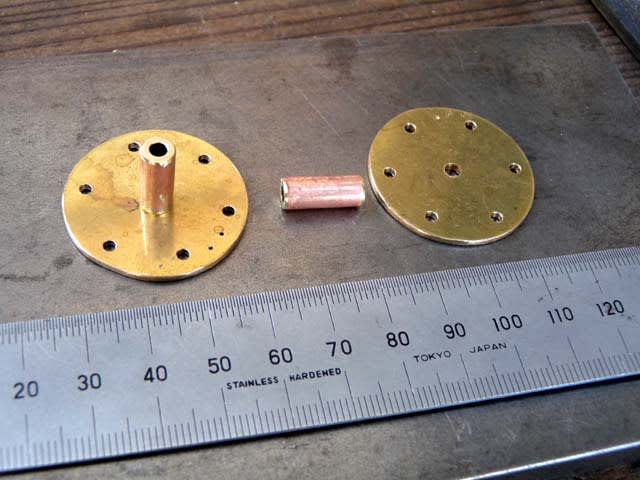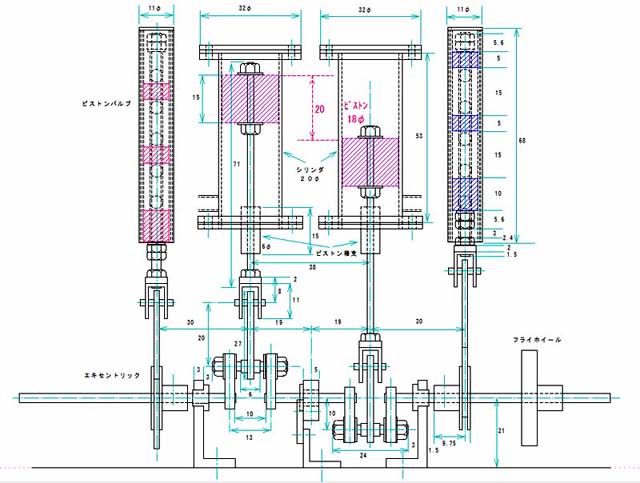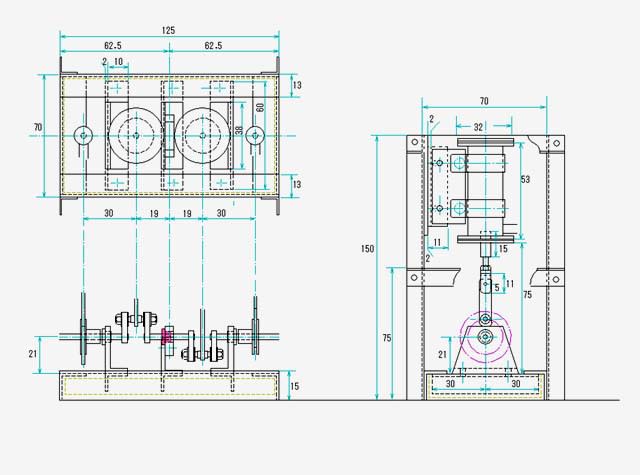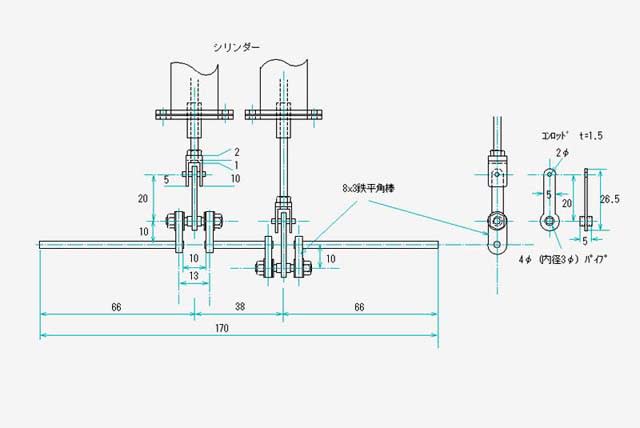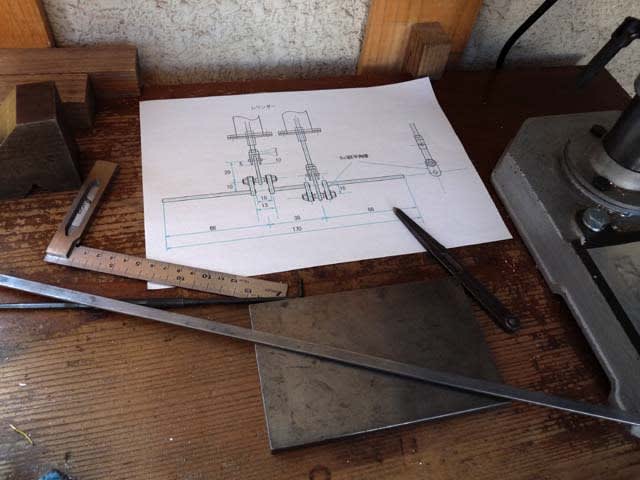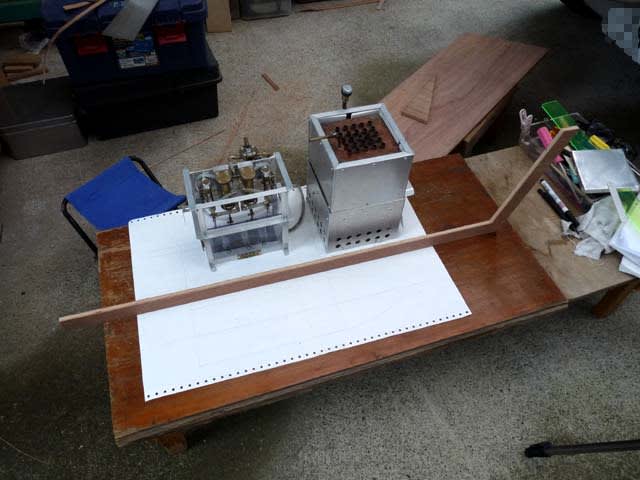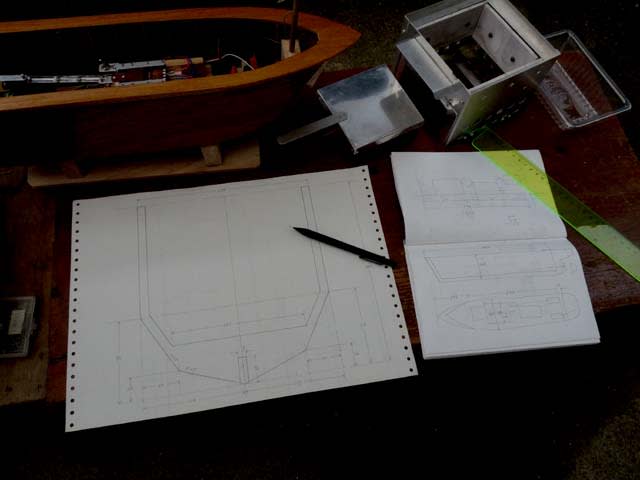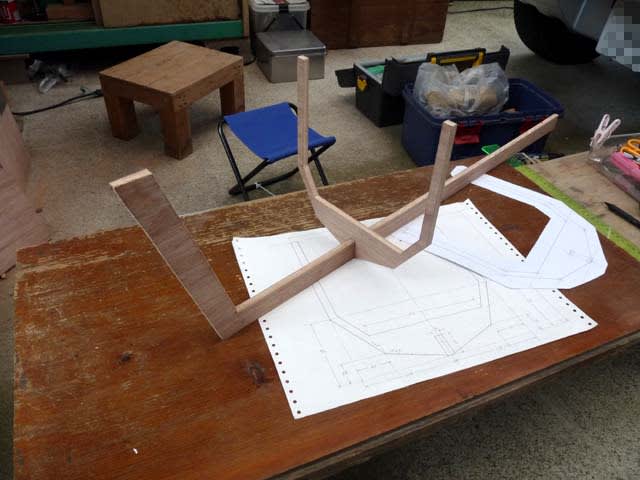2013/04/03 (水曜日) 雨 午後 曇り
昨日に続いて今日も雨降りだった。
昨夜は相当強く降ったようで庭の低いところには水溜りができていた。
今日もモズ君はおやつを貰いに来るだろうなぁ・・・
この間あんなに沢山買い込んできたおやつ(ミルワーム)もほんの少しに
なってしまった。
ホームセンターが開店したら出かけて行って買ってこよう。
↓ 今日は食事室の方からおやつを投げてあげたのでこんな鉢スタンドに止まって待っている。

↓ モズ君は頭も背中も雨で濡れて可愛そうだ。


とうとうミルワームが無くなってしまった。
雨が激しく降る中をホームセンターまで出かけた。
そして小鳥用品の売り場へ直行、ミルワーム置き場に行ってみたが売り切れ・・・・
ありゃー、困ったなぁ・・・どうしよう。
あっ、そうだ、あの人にジョビオ君にあげるミルワームを買った場所を教えてもらおう。
お店の名前と場所がわかったので、そちらに行ってみた。
あった・・・ ミルワームの丸い容器が4つあったので全部買ってしまった。
そんなこんなで家に帰ってきた頃には雨も小降りになってもうすぐ止みそうだった。
そこで、モズ君へのおやつやり(ミルワーム投げ)をお代官に頼んで、オイラは公園に
行ってモズ君が子供の所に戻って来るのを待った。
↓ 親鳥がエサを持ってくると大喜びで翼を震わせる。

↓ 親子の語らい・・・・
「ねぇ、お父さん、ボクは大きくなったら・・・・・になるんだ!」
「おー、そうか、それは偉いなぁ。 頑張るんだよ」

遠くに離れてカメラを構えていたのだが、モズの幼鳥は怖がって林の藪の方に
飛び去ってしまった。
親鳥はそちらに向ってエサを運んで行く。
公園での撮影はこれまでとした。
カメラ: Panasonic DMC-FZ100
テレコン: Olympus TCON-17X(1.7倍)
レタッチソフトによる画像補正及びトリミング
昨日に続いて今日も雨降りだった。
昨夜は相当強く降ったようで庭の低いところには水溜りができていた。
今日もモズ君はおやつを貰いに来るだろうなぁ・・・
この間あんなに沢山買い込んできたおやつ(ミルワーム)もほんの少しに
なってしまった。
ホームセンターが開店したら出かけて行って買ってこよう。
↓ 今日は食事室の方からおやつを投げてあげたのでこんな鉢スタンドに止まって待っている。

↓ モズ君は頭も背中も雨で濡れて可愛そうだ。


とうとうミルワームが無くなってしまった。
雨が激しく降る中をホームセンターまで出かけた。
そして小鳥用品の売り場へ直行、ミルワーム置き場に行ってみたが売り切れ・・・・
ありゃー、困ったなぁ・・・どうしよう。
あっ、そうだ、あの人にジョビオ君にあげるミルワームを買った場所を教えてもらおう。
お店の名前と場所がわかったので、そちらに行ってみた。
あった・・・ ミルワームの丸い容器が4つあったので全部買ってしまった。
そんなこんなで家に帰ってきた頃には雨も小降りになってもうすぐ止みそうだった。
そこで、モズ君へのおやつやり(ミルワーム投げ)をお代官に頼んで、オイラは公園に
行ってモズ君が子供の所に戻って来るのを待った。
↓ 親鳥がエサを持ってくると大喜びで翼を震わせる。

↓ 親子の語らい・・・・
「ねぇ、お父さん、ボクは大きくなったら・・・・・になるんだ!」
「おー、そうか、それは偉いなぁ。 頑張るんだよ」

遠くに離れてカメラを構えていたのだが、モズの幼鳥は怖がって林の藪の方に
飛び去ってしまった。
親鳥はそちらに向ってエサを運んで行く。
公園での撮影はこれまでとした。
カメラ: Panasonic DMC-FZ100
テレコン: Olympus TCON-17X(1.7倍)
レタッチソフトによる画像補正及びトリミング