
(三重県総合博物館のミエゾウの前で集合写真)
松阪史跡探訪会主催の第4回松阪史跡めぐりが、平成27年5月24日行われました。第1回の和歌山街道めぐり、第2回の嬉野方面めぐり、第3回の櫛田川流域めぐりに続き、今回は三重県総合博物館(Miemu)と伊勢街道めぐりでした。
この日は松阪市内から50人の参加があり、2台のマイクロバス(定員28人)分乗して、それぞれの場所で説明を聞きました。
松阪史跡探訪会(会員43名 代表川口 保)は平成25年11月に設立された会で、松阪市内の名勝、名山、城跡、遺跡、古墳、神社、お寺、名木、祭り、神事、食、名産などの歴史的・文化的遺産などを訪ねていくものです。会費が1000円/年という以外は、会則も総会もありません。史跡めぐりの回数は10回、訪ねる史跡は100ヶ所を当面の目標にしています。
今回の史跡めぐりは次のコースで探訪しました。
鈴の森公園、松尾神社(集合)―→三重県総合博物館(Miemu)―→松浦武四郎記念館―→波氐神社・鵲橋―→六軒追分・三渡橋―→忘井―→俵万智短歌―→伊勢街道市場庄―→舟木家―→旧長谷川邸―→駅前商店街散策―→出発地
1)三重県総合博物館(Miemu)(津市一身田)
(案内 三重県総合博物館 中川良平学芸員 、岸田早苗学芸員)
三重県総合博物館は、これまでの三重県立博物館がリニューアルして平成26年4月19日に津市一身田にグランドオープンしました。「ともに考え、活動し、成長する博物館」を基本理念として、三重の自然・歴史・文化に関する42万点の資料を展示・収納しています。1週間前の5月17日に来館者が40万人を突破しました。


参加者はまず、3階のレクチャールームで岸田学芸員から博物館全体の説明を受け、その後それぞれが展示を見学しました。今回の参加者では初めてきた人がほとんどで、短い時間でしたが、博物館を堪能しました。
2)松浦武四郎記念館 (松阪市小野江町)
(案内 松浦武四郎記念館 山本命 学芸員)
松浦武四郎記念館は平成6年に当時の三雲町が建設したもので、平成26年に20周年を迎えました。彼の生まれ故郷の松阪市小野江町にあるこの記念館では、武四郎の関係資料の収集、調査研究、展示公開、教育普及などの博物館活動を行っています。


(山本命学芸員から説明を受ける)
松浦武四郎(1818~1888)は幕末から明治維新にかけて蝦夷地を6回に渡って探検した探検家で、北海道の名付け親です。大変な筆まめで、作家や出版社の顔もあり、その他、画家、書道家、詩人、歌人、学者の顔も持ち、松尾芭蕉、本居宣長とならび三重県3大偉人の一人です。講座室で山本学芸員より武四郎の功績について説明を受け、また展示場内でも説明を受けました。この記念館も初めて来た人が多かったようです。


(鵲橋での七夕まつりなどの説明) (波氐神社の見学)
3)波氐神社・鵲橋(松阪市星合町)
(案内 川口 保)
毎年8月7日に松阪市星合町の波氐(はて)神社と鵲橋(かささぎばし)を中心として「鵲七夕まつり」が行われます。文政年間(1818~1830)の群馬県の旅人の紀行文に、この鵲地区の七夕祭りを見たとの記述があるということから、約200年の歴史がある事がわかります。
「鵲橋」は七夕伝説の架空の橋です。鵲橋の両側に立った織姫と彦星は、川を渡れず途方にくれます。そこに鵲が飛んできて、橋を架け二人は再会することができたという話しです。
当地の鵲七夕まつりの主人公の彦星は鵲小学校の男児が、織姫は女児が扮し、この鵲橋の上で再開します。鵲橋の近くにある波氐神社(現 星合神社)には「多奈波太姫命(たなばたひめのみこと)」が祀られています。
朝鮮半島や日本では九州にしか生息していない「鵲」という地名がなぜ当地区に付いたのか、また当地区と七夕伝説の関わりなど、私が話しました。
4)三渡橋、六軒追分 (松阪市六軒町)
(案内 川口 保)
江戸時代の伊勢街道(参宮街道)は、伊勢神宮に参拝する人で大変な賑わいをみせました。何度か起きたおかげ参りには爆発的に参拝者が伊勢に向かいました。多い時には日本の人口が3000万人の時代に、年間500万人もの人が伊勢を目指しました。
六軒追分は伊勢街道と初瀬(はせ)街道の分岐点で、三渡橋のたもとには道標があり、「大和七在所順道」「やまとめぐりかうや道」「いがごえ追分」と書いてあります。
「三渡」という地名は三渡川に橋がない時代に川を越えるとき、潮の干満によって下流、中流、上流と渡る位置を変えたところからつきました。
鴨長明が文治2年(1186)に記したとされる『伊勢記』に三渡川の地名の由来に関する記述があり、最も潮が引いた時は、「こなたのさき」より「かなたのすさき」へとあります。これは固有の地名ではなく、こちら側の崎(岸)から向こう岸の「洲」や「崎」へという意味に解釈されます。次に潮が半ば満ちたときには「めぐりて松崎と云所」とあり、今の松ヶ崎から渡り、最も潮が満ちた時は「いちは」とあり今の市場庄と考えられます。


(三渡橋、六軒追分の説明) (忘井の見学)
5)忘井 (松阪市市場庄町)
(案内 川口 保)
平安時代の天永元年(1110)の斎王群行に随行した官女甲斐がこの忘井を通った時、都をはるばる離れて伊勢の地に来て望郷の念で涙ながらに詠んだ歌「分かれゆく都の方の恋しきにいざ結びみむ忘井の水」が石碑に刻んであります。
6)俵万智さんの短歌(松阪市市場庄町)
(案内 川口 保)
~街道を俳句あんどんで照らそう「参宮街道夢おこし」~の活動をしている、「光れ街道夢おこしの会(前川幸敏代表)」に歌人の俵万智さんから短歌が寄贈され、大正時代に建設された、旧米ノ庄村役場跡に設置をされています。同会の前川代表から聞かせていただき、見学しました。


(俵万智さんの短歌) (伊勢街道の屋号の表札)
7)伊勢街道市場庄 (松阪市市場庄)
(案内 川口 保)
かつては伊勢街道はもう少し海岸よりを通っていたのを、蒲生氏郷が松坂に城を築いた時、今の場所につけ替えました。小野江付近で雲出川を渡り、六軒で三渡川を渡り、六軒追分で初瀬(はせ)街道と合流し、中林町の月本追分で奈良街道と合流します。
この道を諸大名から庶民にいたるまで多くの人々は行き来し、市場庄も大変賑わいました。市場庄地区の伊勢街道沿いには、全国的にも珍しい妻入り(つまいり)連子格子(れんじこうし)の街並みが今も残っています。
また市場庄の多くの建物には昔の店の屋号を書いた表札が掲げられています。


(市場庄の街並み) (舟木家の長屋門)
8)舟木家長屋門 (松阪市久米町)
(案内 川口 保)
舟木家は南北朝から室町・江戸時代から続く名家で、久米村惣庄屋、津藩無足人となり、その後紀州藩主より「津領地士」としてお目見えをゆるされた家柄です。
舟木家の格式を示す長屋門は寛政6年(1794)に建設され、天保5年(1834)に改修されました。門の正中央より下の部分に施された海鼠壁(なまこかべ)が特徴です。今も舟木家の子孫が住んでみえます。
9)松阪商人 旧長谷川邸(松阪市殿町・魚町)
(案内 市教委文化課 家城和秀さん、中西士典さん )
松阪の生んだ豪商の1つ松阪商人長谷川治郎兵衛家旧宅は、松阪市魚町、殿町にまたがる4688.40㎡の敷地に、主屋1棟、大正座敷1棟、離れ1棟、神祠1棟、土蔵5棟の9棟の建物があり、また周囲に配置された庭園など豪商の旧宅らしく、派手さはないが落ち着いた造りになっています。


旧長谷川邸は平成25年4月1日長谷川家から松阪市に寄贈され、同5月10日松阪市文化財保護審議会開催、答申、5月20日教育委員会が開催され松阪市の文化財に指定(252件目、史跡では38件目)されました。
昨年3月9日、歴史民俗資料館が行う展示のための資料を表蔵で探していたところ、一階の棚の上奥から「長谷川」「長福」と書かれた千両箱が見つかり、中から大判小判などの古銭が発見されました。
この日は松阪市教育委員会文化課の家城和秀さん、中西士典さんから長谷川家の建物・庭園の話しや、蔵から発見された千両箱や大判小判の話しなど説明を受けました。また長谷川邸が松阪市に寄贈されるまで長谷川の社員としてこの建物を管理してみえた、柳瀬實さんも挨拶をしていただきました。
10)駅前商店街散策
長谷川邸の見学を終え、徒歩で駅前などの商店街を散策しました。ぜんざいを食べる人、コーヒーを飲む人、ソフトクリームや鯛焼き・まんじゅうなど買う人、まつさか交流物産館で土産物を買う人など、それぞれ散策を楽しみました。
-お世話いただいた皆さんありがとうございました-
この日は心配された雨も降らず、朝8時から午後4時30分位までの間に10箇所位を見学する強行スケジュールでしたが、参加者の皆さんは史跡めぐりを楽しんでいただきました。
今回の第4回の史跡めぐりの開催に当たり多くの皆さまにお世話になりました。
三重県総合博物館の見学のお世話をしていただいた野呂昭彦名誉館長(前知事)さん、松井一明同館副館長さん、天野秀昭広報・利用者サービス課課長(学芸員)さん、また当日案内をしていただいた中川良平学芸員さん、岸田早苗学芸員さんありがとうございました。
松浦武四郎記念館の見学に際しお世話になった中野恭館長さん、当日案内をしていただいた山本命学芸員さん、また旧長谷川邸の見学でお世話になった松阪市教育委員会文化課の皆さん、説明をしていただいた市教委文化課文化係の家城和秀さん、中西士典さん、柳瀬實さんありがとうございました。
三雲地域のいろいろな情報をいただいた前川幸敏市議さん、見学地の資料をいただいた三雲振興局さん、松阪市観光協会さんありがとうございました。
また安全運転でマイクロバスを走行していただいた立野町の小林岩雄さん、藤之木町の梶間弘功さんありがとうございました。
-次回の第5回史跡めぐりの案内-
次回の第5回史跡めぐりは11月下旬を予定しています。松阪史跡探訪会会員には往復ハガキで案内を差し上げます。入会を希望される方は、川口保まで連絡下さい。
松阪史跡探訪会 代表 川口 保
松阪市西野町1867-1
℡ 0598-58-2948 携帯090-8738-7959
















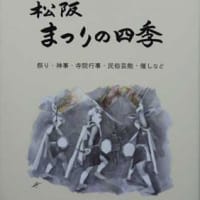









勉強になりました
なかでも松浦武四郎記念館の中村 命さん
素晴らしかった
北海道を旅行した時 松浦武四郎さんのことを聞きました
そんな立派な方が三重にいらっしゃったんだと思っていました
三重でももっともっとみんなに知っていただきたいものですね
それもこんなに大きな
亀山 芸濃 安芸 で骨が見つかったとか
どんなふうにどれくらいいたんだろう
南北に長い三重は日本列島の縮図だと説明があり
なるほど海あり山あり 食べるものも豊富おいしい
果物 新鮮な魚 松阪牛
私たちはいいところに住んでいるんだなあと改めて感じました
三重県も松阪市もいいものがいっぱいあります。
私も史跡めぐりを開催する側ですが、新しい発見たくさんあります。
博物館も、武四郎館ももう少し時間をかけて見学してもらうとよかったのですが、
ここも見てもらいたい、あそこも見てもらいたい、今回もまた強行スケジュールになりました。
次回第5回、乞うご期待。