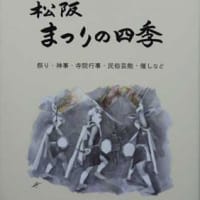松阪市殿町の松阪公園内にある松阪市歴史民俗資料館で企画展「江戸のコスメティック ~伊勢白粉ものがたり~」展が6月11日から始まりました。
勢和村(現多気町)の丹生では昔から全国一といわれる量の水銀が産出し、松阪の射和地区ではこの水銀を使って白粉をつくり、これらを扱った商人が大きな富を得て、多くのが江戸に進出しました。松阪商人のルーツは射和の軽粉、丹生の水銀までさかのぼると言われています。
丹生の水銀の歴史は古く、『続日本書紀』に文武天皇の2年(698)と和銅6年(713)に伊勢国から朝廷に水銀を献上したことが記されており、水銀は仏像や仏具などに金を塗って仕上げるときに必要なもので、奈良時代の東大寺大仏殿建立には、丹生の水銀が2tも使われたということです。また鎌倉時代の初めの東大寺大仏再建の時にも2万両もの丹生の水銀が使われました。平安時代になると、丹生には取引や採掘のため各地から商人や鉱夫が集まり「丹生千軒」と呼ばれる町ができました。これほど盛んだった丹生水銀の採掘も次第に鉱脈がなくなり、江戸時代には衰えてしまいました。旧勢和村丹生には水銀の廃坑が今も180余り残っているということです。
日本で白粉がつくられたのは飛鳥時代で、692年に唐から渡り奈良元興寺の住職となった観成が、唐の製法で白粉をつくり持統天皇に献上したとあります。伊勢国射和で白粉の生産が始まったのは享徳2年(1453)で、当初は京都の公家への贈りものでした。室町時代の後半から伊勢参りのみやげものとして重宝されました。最盛期には83窯の業者ができて活況しました。しかし江戸時代には丹生の水銀鉱が枯渇し、中国などから原料を輸入して製造が続けられていましたが、昭和28年全ての軽粉窯が廃業し、500年にわたる射和軽粉の歴史が終わりました。
この企画展では丹生の水銀の歴史や射和での伊勢白粉の歴史、また水銀採掘の道具や水銀製造の道具、白粉のパッケージなど射和の萬部家に伝わる資料や、同館所有の資料が展示されています。この催しは9月25日まで開催されています。