私は人と会話する時間が、極端に少ない。
過日(と言っても昨年の暮れ近い日のことであったが………)、夕食後、施設の方3人で話す機会があった。歳をとって、よく忘れるという話題であった。
「今日、僕は家に帰ってきたんだが、何をしてきたんだろう?」と、Oさん。(93歳の男性。私は半世紀前、同じ職場で2年一緒に働いたことがある。施設での思いがけぬ再会。)
Oさんは、自分の行った数時間前のことが思い出せず、深刻な思案顔。
「ありますよ。そんなこと。私は眼鏡がない、眼鏡がないと大騒ぎして、あなた右手に持ってるよ、と言われたことがありますよ」
と、Kさんは、動作を交えて話された。(二度繰り返して。)
その間、Oさんは、廊下の天井を見上げながら、
「おかしいなあ。何をしてきたんだろう?」
と、Kさんの話はそっちのけで考え込んでおられる。
Kさんの聞き役は、私である。
みな、帰る家があり、状況が許せば、ひとときでも家でくつろぎたいのであろう。Oさんは社交的な人だが、それでも施設で突如付き合うことになった仲間には気を遣っておられるに違いない。家は誰かに気兼ねしなくて済む場所、きっとひとときくつろいで、また、この施設に戻ってこられたのだろう。くつろぐというという貴重な時間を形で捉えるのは難しい。だから、Oさんの思案は続くのであった。今、思案したことも、たちまち忘れるのが、老いた者の実態でもある。
「ボケないためには、人と話をするのがいいそうですよ」と、Kさん。(また、二度繰り返して。)
繰り返し発言は高齢者に多い。強調したいため? それとも、言った端から忘れるためなのだろうか?
対話は、子供や孫、あるいは脳の働きの尋常な人となら、認知症予防に大いに役立つかもしれない。多少認知症の入った者同士でも、話し合うことの効果があるとは思えないのだが、どうであろう?
昔、友達から聞いたことがある。一日に最低でも、20人程度の人と対話するのがいい、と。
私にとっては至難のことである。
電話での話を除けば、誰にも会ってない、誰とも話していない、というのは私にとっては、日常茶飯である。が、対話の必要性については、心のどこかで気にはしていたようだ。
(コロナのために、会って話したい友人には会えないままだ。)
1月4日の朝日新聞 の下欄の広告に、
『1日誰とも
話さなくても
大丈夫』
と、あるのに目が止まった。
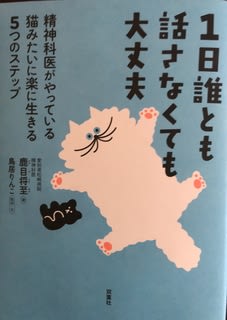
早速、Amazonへ注文。翌日(5日)には届き、その日のうちに読了。
この本の対象は、コロナの感染者が増えるなか、とかく隔離された生活を余儀されがちな人たちに語りかけられた本と言えそうだ。
著者は、精神科医の鹿目将至(かのめまさゆき)さんだが、取材・文は、鳥居りんこさん。(おもしろい形式の本。)
中身(考え方)は、鹿目将至さん、文章表現は鳥居りんこさん、ということのようだ。
中身は、なかなかおもしろかった。[ ]内の表現は引用文。
[ほどよい関係を保つには、ほどよい距離感が必要、逃げることは決して悪いことではないし、むしろ逃げていい!]
[速く行くことだけが、いいわけじゃない。
誰に迷惑をかけるのでもないなら、僕は僕のペースで行けばいいって。
「かたつむり そろそろ登れ 富士の山」と小林一茶も読みました、
僕はこう開き直ることで、ずいぶんと楽になった気がします。]
[せいぜい気にするのは「あさっての天気」まで。遠い先の心配事や悩み事は、目に見えないくらい遠くにまで、放り投げてしまいましょう。]
[「友達百人できるかな?」なんて、僕には無理です。作りたい人はその輪を広げていけばいいでしょう。だけど僕は、話を広げるより、心から友達だと思える大事な人との関係を、じっくり味わって生きていきたい。]
施設においても、上手に距離を保ちながら生きられたら、幸せなことだと思う。ただ、みな異なる過去を持った老人の世界であること、そこに格別の難しさがある。
今日、施設に戻ってきた。5年めを迎える。
人との交わりにおいて、疲れすぎないように、わが道を生きたい。大変難しいことではあるけれど………。
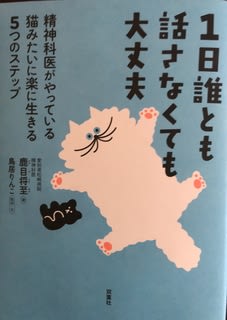



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます