扉ページに
”類推の山 ”
”récit véridique ”
とある。
”récit véridique ”が
《実話》の意であったことに今さら気が付き
朝からちょっと泣いてしまった。
喜びのあまり。
まずラーゲルクヴィストによって「人はなんのために生きるか」という問題を与えられましたが、このドーマルの『類推の山』によって私はひとつの到達点を得たと思います。
この物語がどれほどに私自身であるか、私がどれほどにこの思想に対して真剣であるか、それを説明することはまだできそうにありません。でも、いずれはそれができると思います。
とりあえず今は、友人諸君に一言。
私のような人物には「もう付き合い切れない」とお思いになったとき、それでもちょっとの猶予は与えてもよいとお考えでしたら、どうかこの物語を思い出していただきたい。
これが、私の核心です。何度も読むうちに、はっきりと思い出しました。
始終つまらないことに振り回されているような私ですが、じつは馬鹿げて見えるほどに楽天家(これは何も考えていないということではなく、むしろその逆)なのです。しかも呆れるほど真剣です。
読んでいただければ、私の心根がいかに陽気で率直、前向きかつ誠実であるかが分かっていただけるかと思われます。ええ、とてもそうは思えないとおっしゃりたい気持ちはよく分かりますが…いざという時には騙されたと思ってぜひにお願いします。
いえ。
私のことなんて忘れてしまってもよいですから、「人生は生きるに値するだろうか」という疑惑に直面したとき、あるいは「個人の一生にどれほどの価値があるだろう」「こんなことをやる意味はあるだろうか」とふいに不安になったときには、どうかこの物語のことを思い出してください。
それだけで、私という人間がほんの少しでもあなたがたに関わりを持ったということに意味も価値も生じます。それだけで私は充分ですが、たったそれだけのことがいかに難しいかということはよく分かっています。しかし、その困難こそが私を生かしているとも言えます。
さまよい歩いているようにしか見えなくても、私はその山を目指しています。
このことは、つまり、なんて愉快なんだろう!
こんなふうに、かつて誰かを希望に震えさせた物語があったのだということを、どうかいつか必要になったら思い出してください。そしてもし、読み終えたあなたにも同じ作用を及ぼすならば、それだけこの物語の持つ思想の確かさが証明されることでしょう。
ここまで読んでくれたことに感謝します。
どうもありがとう。
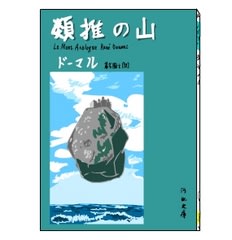
『類推の山』
ルネ・ドーマル 巖谷國士訳(河出書房)
《あらすじ》
はるかに高く遠く、光の過剰ゆえに不可視のまま、世界の中心にそびえる時空の原点――類推の山。その「至高点」をめざす真の精神の旅を、寓意と象徴、神秘と不思議、美しい挿話をちりばめながら描き出したシュルレアリスム小説の傑作。
”どこか爽快で、どこか微笑ましく、どこか「元気の出る」ような”心おどる物語!!
《この一文》
”とすれば、私はそれを発見することに全努力を注ぐべきなのではないだろうか? たとえそんな確信に反して、じつはなにかとんでもない錯覚のとりこになっているのだとしても、そういう努力をついやすことでなにひとつ失うものはないだろう。なぜなら、どのみちこのような希望がなければ、生活のすべては意味を失ってしまうだろうからだ。 ”
**およそ2年前の初読の感想はこちら→→
『類推の山』**
(このときの私はまだ気が付いていないようです。いろいろなことに)
 『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/
『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/ 『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/
『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/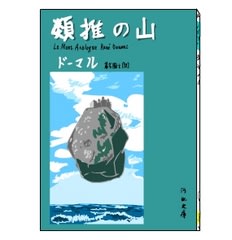 『類推の山』
『類推の山』