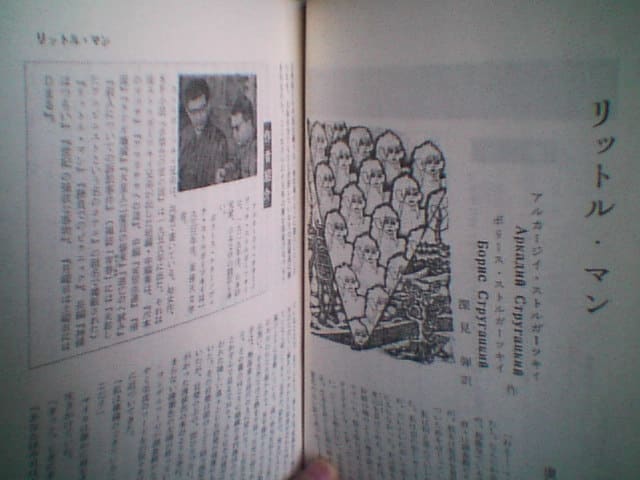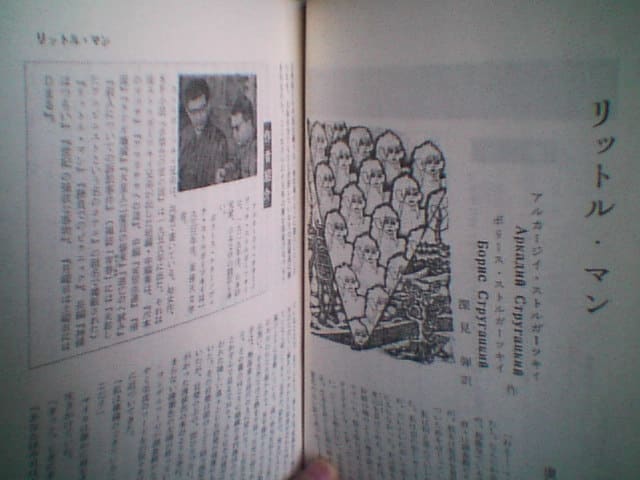
ストルガツキイ兄弟作 深見弾訳(季刊ソヴェート文学 1973 SUMMER 通巻45号)
《あらすじ》
虚無と静寂の惑星で、作業をする地球人たち。コモフ、ワンデルフーゼ、マイカ、ポポフらは、絶滅の危機に瀕したパンタ人を移植させる目的で、この静寂の惑星を改造する『ノアの箱船』計画を実行中だった。彼らはある日、発見されて間もないと思われていたこの星で、地球のものである遭難船を発見する。そして--。
《この一文》
”私はコモフにたいする責任を探してみたが、ただ『俺にとって遍歴者とは何だ? 遍歴者だっって! 俺自身がある程度まで遍歴者じゃないか……』という言葉だけが頭の中を意味もなく駆けめぐっていた。
突然コモフが言った。
「きみはどう思う、スタシ?」 ”
久しぶりのストルガツキイです。K氏が古本で買ってくれていたのをまだ読んでいませんでした。もうかった、もうかった。
さて、この物語は、時間的にはどうやら『収容所惑星』と『蟻塚の中のかぶと虫』もしくは『波が風を消す』のあいだに挟まれるお話のようです。コモフやゴルボフスキーが出て来ました。なつかしー。けど、ちょっとどういう役割の人だったのか、もううろ覚えですよ。またあのシリーズを読み返そう…。マクシムもちらっと登場してました。あと島帝国とか…。なので、やはり『収容所』と『蟻塚』のあいだなのかもしれませんね。
ある惑星で任務を実行中の地球人4人は、作業中に遭難船を発見する。しかも、それは地球のもので、遭難してから随分経っているらしい。静寂と虚無におおわれたこの星での作業は孤独との闘いでもあり、若いサイバー技師のポポフは、ひとりきりの仕事中に幻聴に悩まされるようになる。この場所では絶対にそれを聴くことなどあり得ない音、赤ちゃんの泣き声……。
地球人が宇宙へ出て、他の星々を訪れ、そこに文明が存在すればそれに接触し、ときには干渉する…。そのことをどう考えるか。というようなことが描かれています。…多分。実は、私はまだよく分かりません。いえ、たしかに物語はいつものようにとても面白かったのですが、正直なところ、理解しきれたとは言えません。また何度か読み直すつもりです。できれば、これに関連するほかの作品も読んでみたいですが、訳されてないんだろうなあ。ああ……!
それにしても、なにかと《遍歴者》の名前を持つものが多く登場し過ぎます。今回も、あの《遍歴者》の他にも、遭難した船の名が「遍歴」号だし…。ややこしいんです。
 『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/
『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/ 『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/
『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/