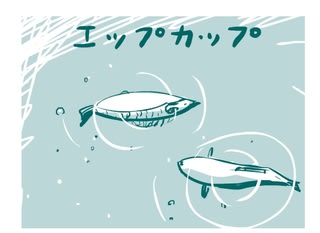三上 延(メディアワークス文庫)
《あらすじ》
不思議な事件を呼び込むのは一冊の古書。
鎌倉の片隅でひっそりと営業している古本屋「ビブリア古書堂」。そこの店主は古本屋のイメージに合わない若くきれいな女性だ。残念なのは、初対面の人間とは口もきけない人見知り。接客業を営む者として心配になる女性だった。
だが、古書の知識は並大抵ではない。人に対してと真逆に、本には人一倍の情熱を燃やす彼女のもとには、いわくつきの古書が持ち込まれることも。彼女は古書にまつわる謎と秘密を、まるで見てきたかのように解き明かしていく。
これは“古書と秘密”の物語。
《この一文》
“人の手を渡った古い本には、中身だけでなく本そのものにも物語がある。”
なるほどなー。とても人気のある小説であることは聞いていましたが、なるほど面白かった。これはライトノベル枠の作品なのでしょうか? 日本の現代小説を読むのが久しぶりだったせいか、おそろしいほどに読みやすかったです。すいすいと1時間ほどで読んでしまいました。
『ビブリア古書堂の事件手帖』は、4冊の古書をめぐる連作短編となっている上に、全体としても大きな一続きの物語ともなっています。最後で最初の謎が解けるようになっています。ひとつひとつの本にまつわる謎解きもそれぞれに面白いですし、その本に対する知識もわずかながら得られるようになっていて、対象の本を読んだことがあってもなくても楽しめるように作られていました。なかなか親切設計ですね。ちなみに私は登場する本は一冊も読んだことがありませんでした。夏目漱石の『それから』とか太宰治の『晩年』くらいは読んでいてしかるべきかもしれませんが、読んだことがないんだから仕方がない。それでも本書は楽しく読めましたよ。へえ、『それから』や『晩年』はそういうお話だったのか。
また、登場人物も分かりやすく魅力的に描かれています。言うまでもなく本書の重要人物であるビブリア古書堂の店主 栞子さんは非常に魅力的です。あざといくらいに魅力的。知的だが内気すぎる美女が自分だけには少し心を開いてくれるような…とか、物語の上でしかあり得ないよ!と分かってはいても、思わずぐっときてしまいます。くそー、罠だな、罠だぜ。ともあれ、栞子さんと本書の語り手である五浦君の関係のように、本についての話を聞いてくれる相手がいるというのがいかに幸福なことであるか、本について語ってくれる人がいるというのがいかに幸福なことであるかについて、私はなによりも共感するわけです。
その他の人物も特徴豊かで、とてもイメージしやすい。人物設定がなかなか上手ですね。
私は第3話の「ヴィノグラードフ・クジミン『論理学入門』(青木文庫)」が気に入りました。素敵なお話でしたね。
続きがあるんでしょうか? あるんだったら読みたい。そんな1冊。