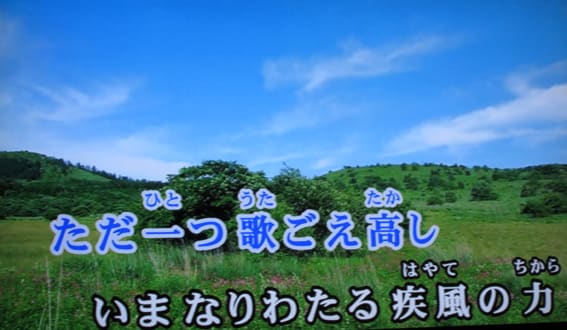4月6日に書いたように、深刻な食糧危機は確実にしのび寄っている。
小麦価格の値上がりは、顕著になってきた。とうもろこしの値上がりもさけられないだろう。
食糧危機は、輸入穀物の価格の暴騰としてあらわれてくる。農産物は、ひろくすでにじりじりと上がりはじめた。これから30年のレンジでみれば、世界人口の爆発的増加、新興国の輸入激増、天候不順、水不足、海面上昇、円安などもからんで、国際的にうばいあいとなる食糧を輸入にたよることが次第に困難になる。
食糧が高騰するなら、国内の農業にもチャンスがある。むしろ、日本の農業が国際競争力をもってくるだろう。高い輸入品に負けることもない。その日本の農業の競争力に目をつけたのがTPPともいえる。絶好のチャンスに農業を外資にうばわれてはいけない。
新興国の製造業においまくられて産業構造の再編をせまられている日本が生きる道は、ひとつは、より知識産業やサービス業にシフトすることであり、もうひとつは、農業を復興させることだ。日本の農業には、絶好のチャンスだ。
農業の復興は、地方の復興であり、地域の復興であり、人口の健全な増加の道でもある。
小麦価格の値上がりは、顕著になってきた。とうもろこしの値上がりもさけられないだろう。
食糧危機は、輸入穀物の価格の暴騰としてあらわれてくる。農産物は、ひろくすでにじりじりと上がりはじめた。これから30年のレンジでみれば、世界人口の爆発的増加、新興国の輸入激増、天候不順、水不足、海面上昇、円安などもからんで、国際的にうばいあいとなる食糧を輸入にたよることが次第に困難になる。
食糧が高騰するなら、国内の農業にもチャンスがある。むしろ、日本の農業が国際競争力をもってくるだろう。高い輸入品に負けることもない。その日本の農業の競争力に目をつけたのがTPPともいえる。絶好のチャンスに農業を外資にうばわれてはいけない。
新興国の製造業においまくられて産業構造の再編をせまられている日本が生きる道は、ひとつは、より知識産業やサービス業にシフトすることであり、もうひとつは、農業を復興させることだ。日本の農業には、絶好のチャンスだ。
農業の復興は、地方の復興であり、地域の復興であり、人口の健全な増加の道でもある。