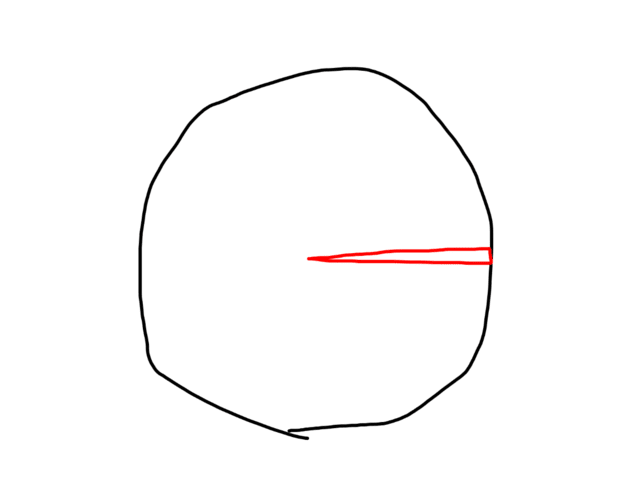選挙が終わりましたね。
国民によるこの判断によって、また今回も特になにが変わるわけでもないわけですが、毎度このブログで言ってることを繰り返させてください。
今回、選挙にいかなかったひとが半分いたんですって。
うはーっ。
お気楽なことです。
わかってんですかね、このことの意味が。
お金持ちは、必ず選挙にいきます。
政治家たちは思います。
お金持ちたちよ、ヨシヨシ、お前らに絶対に損はさせない政治をしてやるぞ。
ジジイも、ババアも、絶対に投票所にいって、世話になってる政治家に投票します。
政治家たちは誓います。
ジジイよ、ババアよ、私は決してお前たちを裏切る政治はしないぞ。
ビンボー人や、忙しがってるやつや、バカは、選挙にいきません。
政治家たちは安心します。
ビンボー人よ、ずっとビンボーでおれ。
忙しがってるやつよ、死ぬまで忙しがってろ。
バカよ、たのむからバカのまま死んでいってくれ。
かくて政治家は、選挙にいかない人間のためには働きません。
政治家は、投票所に足を運んだ人間のためにだけ動きますし、投票所に足を運ばなかった人間を、軽んじ、さげすみ、ちゃっちゃと切り捨てます。
要するに法律とは、投票所に足を運ぶ人間たちのためにできてます。
しかしそれでも、棄権(という名のサボタージュ)をしたひとたちは、精一杯にいきがるでしょう。
「ああ、上等だよ」「政治なんかにゃ頼らねえよ」と。
ぷぷ。
わかっちゃいないところが痛ましいのですが、結局この手の人間がいちばん、政治家にとっちゃ好都合な奴隷なのでした、わんわん。
その態度を、政治家がどう思ってるか、考えたことあります?
「いやー、バカなおひとよ、ありがとうございますー」「すきにやらしてもらいますー」「こうまであいつらをバカにした法律をつくっても文句ひとつ言わないなんて、あいつら便利便利」てなもんですよ。
それだけは覚えとかないと。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園
国民によるこの判断によって、また今回も特になにが変わるわけでもないわけですが、毎度このブログで言ってることを繰り返させてください。
今回、選挙にいかなかったひとが半分いたんですって。
うはーっ。
お気楽なことです。
わかってんですかね、このことの意味が。
お金持ちは、必ず選挙にいきます。
政治家たちは思います。
お金持ちたちよ、ヨシヨシ、お前らに絶対に損はさせない政治をしてやるぞ。
ジジイも、ババアも、絶対に投票所にいって、世話になってる政治家に投票します。
政治家たちは誓います。
ジジイよ、ババアよ、私は決してお前たちを裏切る政治はしないぞ。
ビンボー人や、忙しがってるやつや、バカは、選挙にいきません。
政治家たちは安心します。
ビンボー人よ、ずっとビンボーでおれ。
忙しがってるやつよ、死ぬまで忙しがってろ。
バカよ、たのむからバカのまま死んでいってくれ。
かくて政治家は、選挙にいかない人間のためには働きません。
政治家は、投票所に足を運んだ人間のためにだけ動きますし、投票所に足を運ばなかった人間を、軽んじ、さげすみ、ちゃっちゃと切り捨てます。
要するに法律とは、投票所に足を運ぶ人間たちのためにできてます。
しかしそれでも、棄権(という名のサボタージュ)をしたひとたちは、精一杯にいきがるでしょう。
「ああ、上等だよ」「政治なんかにゃ頼らねえよ」と。
ぷぷ。
わかっちゃいないところが痛ましいのですが、結局この手の人間がいちばん、政治家にとっちゃ好都合な奴隷なのでした、わんわん。
その態度を、政治家がどう思ってるか、考えたことあります?
「いやー、バカなおひとよ、ありがとうございますー」「すきにやらしてもらいますー」「こうまであいつらをバカにした法律をつくっても文句ひとつ言わないなんて、あいつら便利便利」てなもんですよ。
それだけは覚えとかないと。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園