斉藤由貴「毒母」ドラマが示した行き詰まる家族の出口 wol.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15…
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月15日 - 15:49
脳の老化現象で「てんかん」 50歳以上での発症に注意/鶏肉の串カツほか~ある日の食事。 goo.gl/6Gbkx4
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月15日 - 20:58
斉藤由貴「毒母」ドラマが示した行き詰まる家族の出口 wol.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15…
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月15日 - 15:49
脳の老化現象で「てんかん」 50歳以上での発症に注意/鶏肉の串カツほか~ある日の食事。 goo.gl/6Gbkx4
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月15日 - 20:58









 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ


| 脳の老化現象で「てんかん」 50歳以上での発症に注意 2017年3月14日 中日新聞 けいれんや意識を失うといった発作を繰り返す脳の病気「てんかん」。五十歳以上で新たに発症することもあり、病気だと気付かないまま交通事故を起こしたり、記憶力の低下で認知症と間違われたりするケースがある。二十六日はてんかんを啓発する「パープルデー」。主催団体は、誰もが発症しうることを強調し、病気への理解を求めている。 「高齢者のてんかんは、本人に自覚がなく、家族が“おかしい”と感じて医療機関に連れてくることが多い」。愛知医科大病院精神神経科の兼本浩祐教授はこう話す。 てんかんは、脳の神経細胞がさまざまな理由から一時的に異常に興奮することで、けいれんなどを引き起こす。日本では約百万人(人口の1%程度)の患者がいるとされる。乳幼児期の発症が最も多く、成人になると発症率が低くなるものの、五十歳を超えると脳血管障害などで再び発症率が高くなっていく。 兼本教授に典型例=症例1、2=を示してもらった。高齢者に多いのは、記憶や聴覚などにかかわる働きをする側頭葉が原因の部分てんかんという。全身のけいれんは起こらず、日常生活の中で突然、十数秒から数分間、意識が消失してしまう。事例のように生返事をしたり、目を見開いて口を動かしたりする。 発作の間のことは覚えていないため、病気に気付かない人もいる。放置しているうちに記憶力が低下するなどし、認知症やうつ病と診断されてしまうケースもあるという。 「脳波や脳の画像診断といった検査でも異常が見られないことがある。診断は難しく、見落とされる人もいる」と兼本教授は指摘する。症状に心当たりがある場合は、日本てんかん学会がホームページで公表している専門医を受診したい。 こうした症状は、抗てんかん薬で治まることが多く、発作を抑えれば元通りの生活を送ることができる。記憶力が低下していた人でも、治療を始めるとある程度は回復するという。 怖いのは気付かないまま自動車に乗り、運転中に発作を起こすことだ。兼本教授は「脳の老化現象の一つで、だれでも発症する可能性がある。疑わしい症状があれば一刻も早く受診し、治療することが大切です」と呼び掛けている。 ◇ パープルデーの二十六日午後一時から、名古屋市北区の名城公園でウオーキングやランニング、ステージなどの啓発イベントが開かれる。応援する気持ちを表すため、紫色のものを身に着ける。二十五日午後二時からは、同市中区の栄ガスビルで高齢てんかんがテーマの講演会も開く。問い合わせは、すずかけクリニック=電052(731)8300=へ。 (稲田雅文) ◆「認知症」と誤診も <症例1> 50代男性。4年前から、就寝後に全身が震えるようになった。最近になって1分前後、目を見開いて震える発作が起こるようになったが、その時のことは覚えていない。画像検査と脳波で脳を調 <症例2> 50代男性。5年ほど前から妻との会話で生返事をするように。そのときは、ボーッとした表情で口をくちゃくちゃと動かし、問い掛けにも答えない。妻が「おかしい」と指摘しても「病気じゃない」と怒るばかり。徐々に記憶力が低下してきた。 |

 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。

福島の甲状腺がん多発、行政や医療関係者の「原発事故と関係ない」の主張はデータを無視したデタラメだ lite-ra.com/2017/03/post-2… @litera_webさんから
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月14日 - 08:10
森友学園 これで終わりではない/ゴディバのチョコと愛媛デコポン、ヒコハヤシのチーズケーキ~ホワイトディのプレゼント goo.gl/9HvJOp
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月14日 - 21:10
脳の老化に伴う高齢発症のてんかんについて解説しています。中日メディカルサイト | 脳の老化現象で「てんかん」 50歳以上での発症に注意 iryou.chunichi.co.jp/article/detail…
— 中日新聞医療サイト「つなごう医療」 (@chunichi_medi) 2017年3月14日 - 16:03


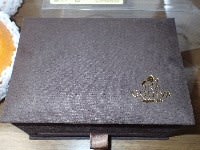
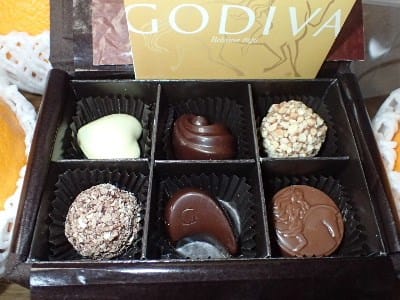



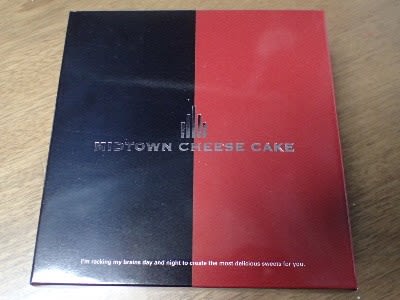





 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ


| 社説:森友学園 これで終わりではない 2017年3月14日 中日新聞 大阪の学校法人「森友学園」は小学校設置のための認可申請を取り下げた。籠池泰典理事長も退任する-。これで幕引きと考えるなら甘い。不可解な取引の全容解明を果たすべく国会招致が必要だ。 「学校が建設できなかった責めを負う。子どもと保護者に申し訳ない」-。籠池氏は十日の記者会見でこのように謝罪し、退任について語ったものの、一連の疑惑に対する明確な回答は避けた。国会の参考人招致にも応じないという。誰がこんな会見内容で納得するというのだろうか。 これほど謎の多い土地取引もない。国有地が八億円も値引かれたからだ。大阪府豊中市にある土地の評価額は当初、九億五千六百万円。それが地中から廃棄物が出たとの森友学園側の申し出を受けて、八億円余りが撤去費用として差し引かれたのである。しかも分割払い。異例ずくめである。 小学校の建築事業費には何と金額が異なる三種類の契約書が存在する。これも疑問だらけだ。高い金額は約二十三億円で国土交通省に、安い金額は約七億円で府に提出されていた。三倍以上の開きがある。府に対しては財務面で問題がないように見せ掛け、国からは多くの補助金を引き出そうとした-。そんな見方が出ている。 実際に国からは五千六百万円の補助金が出たが、これは補助金の不正受給にあたりうる。国交省は既に支払った補助金を返還請求する方向だが、同時に刑事事件の立件可能性も探るべきである。 財務省も旧国有地に建設した校舎を解体し、更地に戻して引き渡すよう学園に要求するという。違約金の支払いも求める。当然の対処である。だが、何よりも国が国有地を評価額の14%で売却した経緯が全く明らかになっていない。 自民党の鴻池祥肇(よしただ)参院議員が財務省への仲介を頼まれたと証言している。どのような「力学」が働いたのか否か明白にしないと国民は納得しない。「安倍晋三記念小学校」の触れ込みで寄付金を募り、安倍首相の妻の昭恵氏が名誉校長に就いていた経緯もある。 共同通信社の世論調査では、国有地が格安で売却された問題について、86・5%が「適切だと思わない」と回答。籠池氏を国会招致し、説明を求めることに「賛成」との回答が74・6%に上った。 関係者を国会招致すべきである。全容解明がなされないと、いつまでも行政府や首相周辺は国民から疑いの目で見られる。 |

 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。

福島原発事故から6年 「アンダーコントロール」からほど遠い現状、海外メディア伝える | NewSphere|ニュースフィア newsphere.jp/national/20170… @newsphere_jpさんから
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月13日 - 21:16
森友学園問題 幕引きはありえない/籠池氏の招致 自民党は何が怖いのか/「森友」申請取り下げ]疑問は深まるばかりだ goo.gl/7DHWZV
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月13日 - 22:26

















 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ


| 社説:森友学園問題 幕引きはありえない 2017年3月13日 朝日新聞 これで幕引きにするわけにはいかない。全容解明には関係者の国会招致がやはり必要だ。 学校法人「森友学園」(大阪市)の籠池(かごいけ)泰典理事長が、4月開校をめざしていた小学校の設置認可の申請を取り下げ、理事長を退任すると発表した。 大阪府はすでに不認可の方針を示していた。申請を取り下げることで、事態の収拾を図ったようにも受け取れる。 だが、10日の記者会見で籠池氏は、国有地売買の経緯や補助金の不正取得疑惑について詳細な説明をしなかった。逆に府に対し「私どもの資料を流出させた」と批判、国会での追及や報道のせいで工事が遅れ、寄付金集めに影響が出たなどと、まるで被害者のように語った。 いま学園に向けられている疑惑は多岐にわたる。反省や、真摯(しんし)に説明する姿勢が見られなかったのは残念だ。 申請を取り下げ、仮に国が土地を買い戻したとしても、土地売却の不可解な減額の経緯や、政治家の関与の有無などを解明する必要性に変わりはない。記者会見で持論を述べるだけでなく、籠池氏は国会で疑問にていねいに答えるべきだ。 野党は籠池氏や当時の財務省幹部らの国会招致を求めている。だが自公両党は応じない。 「民間人だから慎重であるべきだ」「違法性がない」「国会で審議中」。それが与党側の言い分だ。 しかし、過去に民間人が国会に参考人として招致された例は98年の日興証券利益供与事件や02年の外務省NGO問題、15年の年金情報不正アクセスなど、少なからずある。 何より森友学園は小学校の建築事業費をめぐり、金額の異なる3通りの契約書を国や府などに提出、補助金を不正に得ていた疑惑まで浮上している。 何をもって違法性がないと言い切れるのか。 参院での審議では、財務、国土交通両省とも「記録がない」「法的に適正に処理した」と繰り返し、現在の担当局長らが、棒読みのような「官僚答弁」に終始している。 こうした政府の態度に、らちが明かないと多くの国民が感じているのが現状ではないか。 安倍首相の妻昭恵氏の名誉校長就任の経緯やその影響についても、籠池氏や財務省幹部にただす必要がある。首相らが国有地払い下げなどに「不正はない」というなら、堂々と招致に応じて真相を解明すればいい。 このままでは「疑惑にふたをして、逃げている」と言われても仕方あるまい。 |
| 社説:籠池氏の招致 自民党は何が怖いのか 2017年3月13日 毎日新聞 自民党と公明党は、いつまで逃げの姿勢を続けるつもりなのか。 大阪市の学校法人「森友学園」の国有地取得問題に関し、野党が求めている同学園の籠池泰典氏ら関係者の参考人招致を与党が拒んでいる。 だが、拒否の理由は理屈が立たない。学園側が開設を目指していた小学校の設置認可申請を取り下げ、籠池氏が理事長辞任を表明したことで自民党には「参考人招致は必要なくなった」との声があるが、これで幕引きするわけにはいかない。 自民党の竹下亘国会対策委員長は「民間人の招致は慎重であるべきだ」と言う。確かにそうだ。ただし、虚偽の陳述をすれば罰せられる証人喚問も含め、民間人を国会に呼んだ例は過去にも多数ある。 ましてや今回は国民の財産である国有地が格安の価格で売却されたという問題だ。解明しないのは国会の責任放棄といっていい。 これまでの国会質疑で財務省は「適正な手続きだった」と繰り返している。一方で同学園と近畿財務局との交渉記録は破棄したという。ではなぜ破棄したかと聞けば「適正で問題がないからだ」と答弁する。 これで納得しろという方が無理だ。だから関係者から話を聞く必要がある。ところが野党が求めている財務局担当者ら公務員の招致も自民党は応じようとしない。 菅義偉官房長官は「違法性のない事案に関わる参考人招致は慎重に」と語った。しかし、学園側から政治家に口利き依頼はなかったのかという疑問のみならず、不可解な点は次々と明らかになっている。 建築費の額が異なる工事請負契約書を国土交通省、大阪府、関西エアポートに提出していた点をはじめ違法性が疑われている問題は数多い。 自民党からは「違法なら捜査当局に任せればいい」との声も聞くが、既に捜査が始まっている場合には、国会に関係者を呼んでも「捜査中だから答えられない」と証言を拒まれる例が過去には多い。国政に関わる事案について、違法性があるかどうかを、まずただすのも立法府・国会の役割だ。 竹下氏は「テレビや週刊誌が取り上げるから国会で議論しようというのは違う」とも語った。本当にそう考えているとすれば、問題の深刻さを分かっていないというほかない。 籠池氏は突如、小学校の設置認可申請を取り下げたが、言い分は一方的だ。より国会招致が必要になったにもかかわらず、自民党には「籠池氏は何を言い出すか分からない」との不安が強まっているようだ。 結局、招致を拒む理由はそれかもしれない。やましい所がないなら招致を認めればいいだけの話だ。 |
| 社説[「森友」申請取り下げ]疑問は深まるばかりだ 2017年3月13日 沖縄タイムス 一連の問題発覚後、初めて開いた記者会見で籠池氏は「苦渋の決断だった」と述べ、国会での追及や報道によって敷地内のごみ搬出が遅れ、寄付金が集まりにくくなったと説明した。 評価額の14%という格安で学校用地を取得したことなどについて、国会議員の口利きを否定。「安倍首相夫妻からも何もしてもらってない」と語った。 一方、金額の異なる3通の工事請負契約書の問題に質問が及ぶと、説明はしどろもどろ。国から多額の補助金を受け取るために建築費を水増ししたのではないかという疑惑や、不透明な土地取引など肝心なことは何一つ明らかにされなかった。 恨み節に終始し、都合の悪い質問には答えようとしない態度はいかにも身勝手である。 認可申請や建築工事などに関し次々と噴出する疑惑に、府私立学校審議会は「不認可」の意向を固めていたといわれる。 認可申請を取り下げたからといって、問題の幕引きにはならない。疑問は深まるばかりだ。 ■ ■ 会見で籠池氏は「いつの頃からか私の信条が(問題の)中心となり、袋だたきに遭うようになった」と訴えた。 森友学園が大阪市内で運営する幼稚園は「教育勅語」を暗唱させることで知られる。「教育の神髄を伝えている」との理由で導入したというが、戦前の軍国主義教育を否定した憲法、教育基本法の下で、子どもたちが教育勅語をそらんじる姿は異様である。 教育勅語は普遍的な意義を持つ道徳を説く一方で、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」とうたう。戦争になったら天皇のために命を投げ出せとの教えだ。戦後、衆参両院が排除・失効を決議したのは、国民主権の現代にそぐわないからである。 籠池氏は「再びチャレンジする」と別の場所での学校建設を目指す意向を示している。いずれ出直したいと言っているのだから、なおさらこれで幕引きとすることは許されない。 ■ ■ 安倍晋三首相の妻昭恵さんが森友学園が計画する小学校の名誉校長を務めていた問題は、自民党内からも不適切だったとの声が上がっている。 学園の幼稚園教育を巡って、教育勅語を是認する答弁をした稲田朋美防衛相への批判も強まっている。 政府与党としてきちんと解明すべき問題なのに、自民党が籠池氏の国会招致に消極的なのは理解に苦しむ。 国民の疑惑を晴らさなければ政治不信は強まる。与野党協力して籠池氏の参考人招致を実現させるべきだ。 |

 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。

「福島第1」事故から6年 教訓生かし脱原発の道を/NHKスペシャル:メルトダウンFile.6/非常用冷却装置が事故前年まで起動しにくい設定/暖かい日にキンリョウヘンの水やり goo.gl/mMM4fL
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月12日 - 21:52










 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ


| 福島第一原発 非常用冷却装置が事故前年まで起動しにくい設定 2017.3.12 NHK 6年前の東京電力福島第一原子力発電所の事故で、最初にメルトダウンした1号機では重要な非常用の冷却装置が事故の前年まで30年近く起動しにくい設定になっていたことがわかりました。その結果、経験者がいない状態で対応を迫られることになり、専門家は「経験不足が事故の拡大を防げなかった背景となった可能性がある」と指摘しています。 福島第一原発1号機の「イソコン」と呼ばれる非常用の冷却装置は6年前、地震のあと自動で起動し運転員の操作によって原子炉を冷却していましたが、津波で電源が失われた後は稼働状態を見誤るなど十分に生かすことができず、その後1号機はメルトダウンし水素爆発を起こしました。 NHKが東京電力の関係者や情報公開請求などを通じて取材したところ、1981年にイソコンが起動しにくくなる設定の変更が行われていたことがわかりました。 イソコンはトラブルなどで原子炉の圧力が高まると自動で起動しますが、このときの設定変更では原子炉の圧力を下げるための別の機器が先に動くようになり、その後30年近く、トラブルがあってもイソコンが作動した記録は見つかりませんでした。 事故の前の年、安全対策の見直しで今度はイソコンが起動しやすい設定に変更されましたが、その後も実際に動かす試験は行われず、福島第一原発ではイソコンを動かした経験者がいない状態で事故対応を迫られることになりました。 東京電力は1981年の設定変更について、記録が残っておらず理由を確認できないとしたうえで実際に動かす試験を行わなかったことについては、「イソコンに損傷などが生じると放射性物質を外に漏らすリスクがあった」とし、研修などで知識を習得していたとしています。 原子力工学に詳しい法政大学の宮野廣客員教授は「装置は実際に使ってみないと使えず、こうした経緯が事故の拡大を防げなかった背景となった可能性がある。ほかの原発にもある安全設備についても試験や訓練の在り方を見直す必要がある」と指摘しています。 東電OB 動かすこと躊躇する装置 イソコンを実際に動かす試験が行われてこなかった背景について、東京電力の元幹部でビジネス・ブレークスルー大学の二見常夫教授は「イソコンは、万一損傷などが生じると放射性物質を外に漏らすおそれがあり、作動するとごう音とともに大量の蒸気を出すため、周辺住民に不安を与えるとして動かすことを躊躇(ちゅうちょ)するような装置だった」と話しています。 規制庁「動作試験 リスク踏まえ調査・検討したい」 原子力規制庁はNHKの取材に対し、「実際に装置を動かす試験は慎重な検討が必要だが、アメリカは原発の運転中に実際に動かす試験を行っており、リスクも踏まえながら調査・検討したい」としています。 |
| 社説:「福島第1」事故から6年 教訓生かし脱原発の道を 2017.3.12 北海道新聞 6年前のきょう、驚くべき光景がテレビに映し出された。東京電力福島第1原発1号機の建屋爆発である。 現場は今も放射線量が高いため、内部がどうなっているかも分からず、廃炉に向けた作業は遅々として進んでいない。 それを尻目に、国は原発再稼働に向け、突き進んでいる。 すでに12基が原子力規制委員会の審査に合格し、うち3基が稼働している。この1年間に合格したのは7基に上る。 国が2014年に定めたエネルギー基本計画は「原発依存度を可能な限り低減する」と明記した。なのに、政府や電力会社からは、そうした姿勢がうかがえない。 再稼働は多くの国民が懸念し、脱原発を求める声が根強い。 原発を巡る政府や電力業界と国民との溝は広がる一方だ。 ■見つからない核燃料 東電は先月、福島第1原発2号機の格納容器内に、カメラ付きの自走式ロボットを入れた。 ところが、強い放射線でカメラが壊れるなどし、溶け落ちた核燃料の状況は確認できていない。 6年も経過してこれだ。炉心溶融という最悪の事故が起きた原発の実態である。 最も困難とされる核燃料取り出しの方法すら決められず、30~40年かけて行う予定の廃炉は見通しが立っていない。 深刻なのは、事故の影響で、福島県内外に避難している人が今なお約8万人に上ることだ。 政府は避難者の帰還を促し、今月31日と来月1日には、原発の北西に位置する浪江町、飯舘村など4町村の一部で、3万2千人を対象に避難指示を解除する。 だが、4町村の調査で帰還希望者は1~4割台にとどまる。除染が進んだとはいえ、子育て世代を中心に放射線の影響を不安に思う人が多い。 避難指示区域外から古里を離れた自主避難者は、福島県による無償の住宅提供が今月末で打ち切られる。まるで“兵糧攻め”だ。 帰還を急いでまちの消滅を食い止めたい地元の意向もあるのだろうが、肝心の住民の気持ちを軽視してはならない。 ■40年超えも運転延長 原発被災地の実態などお構いなしなのか。政府は再稼働を加速させている。 とりわけ問題なのは、運転開始から40年を迎える老朽原発の関西電力高浜1、2号機、美浜3号機(いずれも福井県)について20年の延長を認めたことだ。 原子炉等規制法が定める、運転期間を原則40年とするルールの骨抜きにほかならない。 老朽原発の審査の順番を他の原発より早める優遇もあった。「再稼働ありき」と取られても仕方あるまい。 政府が「世界で最も厳しい水準」と自賛する新規制基準は、福島の事故を受けてつくられた。 だが、原子炉の冷却機能が失われ炉心溶融に至った―とされる事故原因も、津波や地震の影響をどう受けたかなど詳細は不明だ。 これが現在の科学の限界である。「安全神話」はとうに崩壊している。 本来は原発を含めたエネルギー政策を根本から問い直すのが、政治の役割だ。 しかし、成長戦略に原発再稼働を掲げる安倍晋三政権は、規制委に審査を丸投げし、新たな安全神話をつくろうとしているようだ。 野党の民進党も腰が定まらない。「2030年に原発ゼロ」を党方針にしようとしたが、支持労組の反発で先送りを決めた。 業界やそれを取り巻く研究者らでつくる「原子力ムラ」が社会に根付いていることを示している。 しかし、海外に目を向ければ、ドイツは福島の事故後、脱原発へかじを切った。台湾もそうだ。それが世界の流れではないか。 昨年11月に北海道新聞社加盟の日本世論調査会が行った全国調査で、規制委の審査に合格しても「再稼働に反対」は58%で、賛成の35%を大きく上回った。 ■原点に戻って議論を 大手電力は原発なしでは電力が不足したり、電気料金が上がると主張する。しかし、実際は省エネが進んだこともあって、国内の全原発が停止した時期も電力不足は起きなかった。 福島事故の対策費は当初想定した2倍の計22兆円がかかることが分かり、一部は電気料金や税金にツケ回しされる見通しだ。「原発のコストは安い」とする国の見解も疑わしい。 もはや、原発を再稼働させる理由は見いだしがたい。 風力、太陽光など再生可能エネルギーの導入が各地で進んでいる。脱原発への道筋をどう付けるか。6年前の原点に立ち返った議論が重要だ。 |

 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。

福島 もう一つの真実 3・11とメディア/大震災から6年 「分断の系譜」を超えて/東日本大震災6年/「自分発」風化に立ち向かう goo.gl/fF4y76
— 寺町みどり (@midorinet002) 2017年3月11日 - 21:30




 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ


| 社説:福島 もう一つの真実 3・11とメディア 2017年3月11日 中日新聞 トランプ米大統領のオルタナティブファクト(もう一つの事実)。米国だけの問題ではない。原発報道には以前からあった。どう伝えるかを考えた。 福島県立福島高校のホームページに先月、「福島第一原子力発電所見学報告」がアップされた。昨年十一月に見学した。 報告書を読むと、生徒たちは日ごろから放射線量の計測をしたり、国際ワークショップに参加したりしている。事前に学習会を開き、質問事項も考えていた。 「今、大きい地震が来たときの対策は取られているのか」「賠償は最後の一人になるまでと聞いたが、どこまでいったら最後の一人なのか」-。被災地に生きる高校生ならではの問いが並ぶ。 高校生の鋭い観察眼 見学中、路上に配線や配管が多かったことから「冗長性」も尋ねている。冗長性とは、異常時に備えて、あえて付加した余裕の設備などだ。「原子力発電所は二重、三重にするのが基本的な考え方だが、今の1F(第一原発)では二重が限界。あわてて作ってきたので、本当に二重になっているかは怪しい」と本音を引き出した。 高校生が第一原発に入るのはこれが初めて。全国紙の記事がインターネットのニュースサイトに載った。 「高校生たちは放射線や廃炉について自ら調べ、国内外に発信してきた」と紹介。参加したのは男女十三人だが、写真は壊れた原子炉建屋を背景にした女子生徒、記事中のコメントも女子生徒だった。好意的な記事だったが、インターネット上では「女子生徒の体が心配だ」といった声も出た。 感心な高校生の記事と、放射能は怖いという感想。福島に関する記事ではよくあるパターンだ。 生徒が見学によって被ばくした線量は四・三マイクロシーベルト。日本人の外部被ばくは一日二マイクロシーベルト弱で、二日分を余分に浴びたぐらいだった。 説明とデータが違う ある女子生徒は見学の前に言っていた。「私は放射線の勉強をし、自分の被ばく量も分かっていて、がんの心配はないと考えています。でも、母が気にしているので甲状腺がんの検診は受けます」 甲状腺がんは多くの福島県民の関心事だ。チェルノブイリ原発事故では甲状腺がんが多発した。福島県では二〇一一年十月から、ゼロ歳から十八歳までの全員を対象に検診を始めた。生涯にわたってチェックする方針だった。 よく言われたのは「子どもの甲状腺がんは百万人に数人」「チェルノブイリでは事故から五年後に急増した」だった。 一回目の対象は約三十七万人。がんと診断された人は百人を超えた。専門家は「高精度の検査で、小さいがんを早くに見つけたためだ」と説明した。新たな患者は少なくなると考えられた二巡目の検査だが、昨年末までに四十四人ががんと診断された。前回は異常なしだった子どももいた。 予想と違うデータに、記者会見では毎回、「多発は事故のせいでは」との質問が出る。だが、福島県の検討委員会は「チェルノブイリの知見から被ばくの影響とは考えにくい」の繰り返しだ。「がん患者が○人増加した」と「放射線の影響は考えにくい」という真逆にもみえることが一本の記事になる。「もう一つの事実」が真実を見えにくくしている。 甲状腺がんが増える期間に入った昨年、検査の縮小を求める声が福島県内で強くなった。理由の一つに「国内外での風評につながる可能性」が挙げられ、それがそのまま報道されている。甲状腺がんの増加は風評ではない。事実を風評と過小評価してはいけない。 昨年、「福島子ども健康プロジェクト」が発表した八歳ぐらいの子を持つ母親を対象にした調査では63・7%の人が「放射能の情報に関する不安がある」と答えている。放射線被ばくとがんの関係は研究者によって意見が異なる。それが県民を不安にしている。 福島高校の原尚志(たかし)教諭は「生徒たちが県外で発表すると、質問は、あなたたちは福島県に住んでいて大丈夫なのかと、福島県の食品を食べているのか、ばかりなんです」と話す。 自分の目で見ること 高校生の感想をもう少し。 「誰かのフィルターをかけた1Fではなく、自分の目で見ることができてとても良かった」 「私たちが直面している『偏見』も、今の時点で残っていることは何一つおかしなことではなく、これが恒常的なものになってしまうのかどうか、それを防ぐのかは、これからの私たち次第なんだと強く感じました」 エールを送ろう。私たちは福島に寄り添う。忘れない。そして「何が本当のことなのか」。それを見極めて報道していく。 |
| 社説:大震災から6年 「分断の系譜」を超えて 2017年3月11日(土)付 朝日新聞 どんなに言葉を並べても、書き尽くせない体験というものがある。東日本大震災と福島第一原発事故がそうだった。だからこそ、というべきだろう。あの惨状を当時三十一文字に託した地元の人たちがいた。 《ふるさとを怒りとともに避難する何もわりごどしてもねえのに》津田智 戦後を代表する民俗学者で歌人でもある谷川健一さんは、亡くなる前年の12年、そうした約130首を選んで詩歌集「悲しみの海」を編んだ。 震災から6年。 いまも約8万人が避難する福島で広がるのは、県内と県外、避難者とその他の県民、避難者同士という重層的な「分断」である。 朝日新聞と福島放送が2月末におこなった世論調査で、福島県民の3割は「県民であることで差別されている」と答えた。 《「放射線うつるから近くに寄らないで」避難地の子に児らが言はるる》大槻弘 同じデマがまだ聞こえるという事実が、心を重くする。 ■外と内の「壁」 原発、放射線、除染、避難、賠償……。これらは福島を語るうえで避けて通れない。そして語る者の知識や考えを問うてくるテーマでもある。福島問題は「難しくて面倒くさい」と思われ、多くの人にとって絡みにくくなっている――。社会学者の開沼博さんが2年前に指摘した「壁」はいまもある。 県内では、沿岸部の3万2千人への避難指示がこの春、一斉に解除される。一方、2万4千人はいまだ帰還のめどがたたない。自主避難者への住宅無償支援は打ち切られる。 戻る。戻らない。戻りたくても戻れない。 避難者間の立場や判断の差が再び表面化し、賠償額の違いへの不満などから「あの家は……」と陰口がささやかれる。早稲田大の辻内琢也教授の調査では、首都圏の福島避難者のストレスは今年、上昇に転じた。 ■「もやい直し」の試み この国の戦後を振り返ると、同じような分断とそこから立ち直ろうとする系譜に気づく。 熊本県水俣市。 チッソの排水を原因とした水俣病では、被害者とその他の市民が激しく対立し、「ニセ患者」「奇病御殿」などと中傷の言葉が飛び交った。そう言う人たちも地元を出ると、水俣というだけで差別された。 民俗学者として各地を歩いた谷川さんは、その水俣で生まれた。「『お国はどこですか』と聞かれて『水俣病の水俣です』と答えるときの引き裂かれるような苦痛は、育ったものでなければ分からないでしょう」 ふるさとを「福島」と言えずに「東北」とにごす避難者のせつなさに、きっと寄り添い続けただろう。 分断の克服をめざして、水俣市が約20年前に提唱したのが「もやい直し」だった。 船と船を綱でつなぎあわせるように、人のきずなを結びなおす。ごみ分別や森づくりなど住民が集まる機会を行政が仕掛け、思いがひとつになる小さな体験を重ねていく。「大切なのは、意見の違いを認めたうえで対話することだ」と当時の市長だった吉井正澄さんは言う。 成果は道半ば、である。水俣病の公式確認から61年。だが風評は消えない。今年1月には、県内の小学生が水俣市のチームとのスポーツの試合後、「水俣病がうつる」と発言していた。 「市民が必死に努力しても、簡単には解決しない」と水俣病資料館語り部の会の緒方正実会長は言う。「いま起きていることと向き合い、課題をひとつずつ減らしていくしかない。それが水俣からのメッセージです」 ■復興に必要なもの 谷川さんは終生、沖縄の島々を愛した。ここもまた米軍基地をめぐる「分断」の地である。 米軍専用施設の71%が国土面積の0・6%の県に置かれ、その中で「平和だ」「経済だ」と対立してきた。 しかし各地の風土は多彩な魅力を持っている。それを知る谷川さんは、たとえ地元に良かれという「正義感」からでも、福島=原発、沖縄=米軍基地といったキーワードばかりで語られることを好まなかった。「(外部の支援者は)『水俣病の水俣』しか関心がない。水俣そのものの存在が忘れられるという事態が起こったのです」。重い言葉である。 地元不在の一面的な議論ばかりでは、福島を「難しくて面倒くさい」と思っている多くの人々を引き寄せられない。その結果、全国で共有すべき問題が、特定の地域に押しつけられたままになる。メディアにも向けられた言葉として受け止めたい。 《世界的フクシマなどは望まざり元の穏やかなる福島を恋う》北郷光子 福島沿岸部の復興は、まさに始まったばかりだ。ともに長い道のりを歩き、寄り添い続ける。そういう心を持ちたい。 |
| 社説: 東日本大震災6年/「自分発」風化に立ち向かう 2017年3月11日 河北新報 午後2時46分、静かに目を閉じれば、あの日のことが浮かんでくるだろう。とてつもなく強い揺れが、経験したこともないほど長く続いた。弱まったかと思ったら、またもや激しく揺れだす。 自分のことを知らせ、親しい人の様子を知りたいと、多くの人は携帯電話を手にした。時間は要しても、連絡を取り合えた人は幸いだった。それがかなわなかった人がどれほど多かったことか。 やがて襲った巨大な津波によって、約1万6千人が亡くなった。さらに2500人以上の行方が分からないまま。 1万8千人を超える犠牲者の何倍もの人たちは、どんなに無事を祈ったことだろう。2011年3月11日から東北の被災地の人々の心は激しく揺さぶられ、今もなお収まっていない。 東日本大震災の「風化」が、しきりに聞かれるようになった。岩手、宮城、福島3県の被災地の42市町村長に対する河北新報社のアンケートでは、「多少なりとも風化を感じる」という答えが9割に達している。 震災報道の減少やボランティア事業が少なくなったことに、風化を感じるという。時の経過とともに記憶や関心が薄れていくのは仕方ないことだが、それを自らの努力で食い止めようとしている人も決して少なくない。 国立民族学博物館(大阪府吹田市)の竹沢尚一郎教授(65)は今、企画展「津波を越えて生きる-大槌町の奮闘の記録」を博物館で開催中。岩手県大槌町で被災した人々の写真などを豊富にそろえ、訪れた人に見てもらっている。 もともと東北とは縁がない。それでも6年前、「居ても立ってもいられない気持ち」になり、妻と次女の3人で大槌町の支援に赴いた。4月8日のことだった。 この6年間、ボランティア活動と研究のために何度も大槌町へ行き、企画展開催にこぎ着けた。残念ながら、関西では「もう復興しているんでしょう、といった感じ」と竹沢教授。それでも「大阪にもいつ津波が襲って来るか分からない。だから風化させてならない、と感想を書き残す来訪者もいる」と手応えを感じている。 栗原市で農業を営む菅原正俊さん(75)とさだ子さん(72)の夫婦にとっては、風化などどこ吹く風。震災後ずっと、軽トラックに野菜を積んで宮城県沿岸部の仮設住宅に無償で届けてきた。 「世の中は少しずつ忘れていく気配ですが、私たちはまだまだ前向き」とさだ子さん。昨年暮れまで延べ951カ所に宅配した。年明け後は冬休みだったが、そろそろ再開する。通算1000カ所も間近になっている。 津波と福島第1原発事故が重なった福島県には、真っ正面からの「異議申し立て」で風化に抗しようとする人たちがいる。 散り散りになった避難者で組織する「原発事故被害者・相双(そうそう)の会」のメンバーは「3年後の東京五輪までに国は避難指示をほとんど全て解除し、表面的にはまるで何もなかったかのように思わせたいのではないか」と危ぶむ。 「政策的な風化」とでも呼ぶべき状況になりかねないが、損害賠償を求める裁判で東京電力や国の責任を追及していく。原告団に加わった相双の会のメンバーは「ことしは各地で判決を迎えるはず」と司法判断を待っている。 風化は嘆かわしいとしても、押しとどめることができないわけでもない。諦めず、確かな意志と行動によって。巨大な悲しみに包まれた一つの時代に居合わせ、痛切な思いを共有する一人一人がその当事者になることができる。 |

 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
