平年より23日も早くて、観測史上2番目に早い開花とのこと。
そういえば、福岡や高松では年末に開花していました。
明日から厳しい寒さになるそうですが、
今年は梅の開花が早いようで、うれしいです。
ネコヤナギも少しふくらんできましたね。

きょうは、骨休めの一日。
10時前に家を出て、可児市の花木センターを見て回り、
「湯の華温泉」で岩盤浴とお風呂にはいって、
帰りに、湯の華市場で新鮮なお魚を購入。
お昼ごはんは、マエジマ製パンのおいしいサンドイッチを食べたので、
パンもおみやげにを買ってきました。
出かける前に読んだ中日新聞。
一面下のコラム「中日春秋」も、社説も、
原発被災地の高野病院院長の高野さんが、火事で亡くなったことに関してでした。
被災地の現地で重要な役割を果たしていた病院はどうなるのだろう
と思って調べてみたら、広野町がネットのクラウドファンディングで寄付を呼び掛け
「ふるさと納税」があつまりはじめているとのこと。
全国の医師からもボランティアの申し出が相ついでいる。
とはいえ、
高野病院は「存続の危機」にあるという。
なんとか継続できないものかと、願わずにはいられない。
| 社説:病院長の死が問うもの 原発被災地の医療 2017年1月11日 中日新聞 福島県広野町の高野英男・高野病院長(81)が昨年末、亡くなった。老医師の死は、避難指示解除や地域医療など、被災地が抱える問題を明るみに出した。 高野院長は昨年十二月三十日、火事で亡くなった。病院は福島第一原発から南に約二十二キロ。二〇一一年三月の原発事故後、院長は患者は避難に耐えられないと判断し、患者やスタッフと共に病院にとどまった。おかげで震災関連死を出すことはなかった。三十キロ圏内で唯一、診療活動を継続している病院となった。 院長の死は、八十一歳の老医師の活躍で隠されていた不都合な真実を明らかにした。そのうちの三点について書いていきたい。 常勤医ゼロの非常事態 政府は今春、富岡町、飯舘村の大部分で避難指示を解除する方針だ。浪江町も一部が近く解除される見通しである。政府は解除の要件として(1)年間の放射線量が二〇ミリシーベルト以下(2)インフラの整備、医療・介護などがおおむね復旧(3)県、市町村、住民との十分な協議-を挙げている。住民の間では特に医療環境と商業施設の充実を望む声が強い。 だが、医療の実情は、おおむね復旧とは言い難い。 福島県が昨年九月に公表した医療復興計画によると、双葉郡内の八町村では原発事故前の一一年三月一日現在で、六つの病院が診療活動をし、常勤医は三十九人いた。それが一昨年十二月には、病院は高野病院だけ、常勤医は高野院長一人だけになった。 精神科が専門の院長は、救急患者の診察や検視までやっていた。院長の死で、双葉郡は常勤医がいなくなった。 国や県は「一民間病院の支援は公平性を欠く」という理由で、これまで積極的な援助をしなかったと病院関係者は話す。県内の他の病院と差をつけられないという発想だが、民間企業の東京電力には巨額の税金が投入されている。民間だから、というのは役所が得意の「できない理由」でしかない。 院長の死後、病院の存続が危うくなり、国も県も町もやっと支援を表明した。 高齢者を支える 二つ目は少子高齢化、人口減の地域での医療についてだ。 原発から三十キロ圏内を中心に、原発事故後、国や自治体が住民に避難指示を出した。双葉郡の場合、ほぼ全員が避難した。患者がいなくなれば、病院の経営も成り立たず、医療も崩壊する。 すでに避難指示が解除された地域で、帰還しているのは比較的高齢の人だ。しかも「自分で軽トラックを運転できる」など自立して生活できる人が多いという。 三世代、四世代が同居していた避難前であれば、お年寄りの体の異変に家族が気づき、適切な医療ができた。今は一人暮らしか、老夫婦だけとなり、病気の発見が遅れているという話もある。 この問題は被災地に限らない。過疎地でも高齢者を支えないと、医療機関の整っている都市部へ移動する。政府は医療や社会福祉の支出削減を目指しているが、地方の医療が壊れれば、過疎を加速させる可能性がある。 三つ目は、原発事故に病院は耐えられないということだ。 院長は町が出した全町避難の指示に従わなかった。その方が寝たきりの患者らにはよかった。政府は再稼働に際し、原発から五キロ以遠は屋内退避とした。教訓を生かしたように見える。 しかし本当の教訓は「とどまることは無理」である。スタッフの中には、子どもを連れて避難しなければならない人もいた。医薬品だけでなく、入院患者の食事、シーツの交換なども必要だが、継続できたのは善意や幸運が重なったことも大きかった。事故が起きれば、医療は継続できない。医療がなければ、人は住めないということである。 明日の日本の姿 原発事故からもうすぐ六年。関心が薄れ、遠い出来事のように感じている人が少なくない。 院長の死は「原発事故は終わっていない」と訴えているようだ。「被災地の現状は、明日の日本の姿」と警告している。 政府や自治体は一病院の存続問題と事態を矮小(わいしょう)化してはならない。被災地に真摯(しんし)に向き合えば、将来、日本が必要とする知恵を得ることができるはずだ。 |
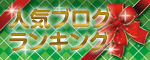 応援クリック してね
応援クリック してね 


| 中日春秋(朝刊コラム) 2017年1月11日 中日新聞 ジョン・ササル氏は戦後長らく、英国南西部の貧しい村で地域医療に打ち込んだ医師だ。村に住み、患者一人一人の暮らしぶりまで知った上で、病と向き合った ▼先日、九十歳で逝った英国の作家ジョン・バージャーさんは、ササル医師の姿を活写した名著『果報者ササル』(みすず書房)で、その医療の本質を描いている。<彼がいい医者だと見なされるのは、患者の心の底に秘められた、口に出されることのない、友愛を感じとりたいという期待に応えているからである> ▼しかし、そんな期待に応え、全人格的に患者と向き合い続ければ、医師はとてつもない喪失感とも向き合わねばならない。だからササル医師は、こんな覚悟で日々を送っていたという ▼「死のことを考えさせられるとき-それは毎日のことだが-わたしはいつも自分の死のことを考える。そうすると、もっと懸命に働こうという気になるんだ」 ▼この方も、そういう覚悟で患者さんと向き合っていたのだろう。福島県広野町で地域医療の柱であり続けた高野病院の院長・高野英男さんが昨年末、八十一歳で亡くなった。原発事故後も患者一人一人に寄り添い、被災地に踏み留(とど)まって医療を支え続けた大黒柱の死である ▼院長の逝去で、高野病院は存続の危機にあるという。これは、一病院の問題ではない。被災地を国全体で支え続ける覚悟の問題だろう。 |
| 高野院長の遺志継いで 福島・広野 ふるさと納税 寄付続々 2017年1月11日 中日新聞 東京電力福島第一原発事故後も福島県双葉郡広野町で、患者の診療を続けた高野英男院長(81)が亡くなり、常勤医不在となった高野病院の存続に向け、全国から町に寄付金が寄せられている。町はボランティア医師の交通費や宿泊費を支給するため、ふるさと納税を利用した寄付を9日から募集したところ、10日夕には300万円を超える寄付が集まった。 病院には内科の寝たきりの高齢者や精神科の患者ら102人が入院している。高野院長が昨年末の火災で亡くなった後、町と南相馬市立総合病院の医師らが「高野病院を支援する会」をつくりボランティア医師を募ると、全国から応募が相次いだ。 町は9日午前11時、ボランティア医師の約3カ月分の宿泊費や交通費として250万円を目標にインターネット上で寄付金を募集。ふるさと納税制度の対象になり、寄付額に応じて所得税や住民税が一部控除されるが、返礼品はなく礼状のみ。それでも全国各地から集まり、10日昼には目標額に達した。同町の担当者は「こんなに早く集まるとは」と驚く。 寄付者からは「頑張ってください!」「尽力されてきた高野医師の意志を引き継ぐ形ができることを祈っております」などの応援メッセージが届いた。 寄付の募集は2月末までで、目標額を上回る分は、町の地域医療のための事業などに充てる。支援する会の会長も務める遠藤智町長は「高野病院が存続し、被災地の医療体制を崩壊させないよう、全力で取り組みたい」と話している。 寄付はガバメントクラウドファンディング「Ready forふるさと納税」(https://readyfor.jp/projects/hirono−med)のホームページからできる。問い合わせは広野町=電0240(27)2111=へ。 |
| 福島・病院長死亡 被災地医療の拠点危機 支援相次ぐが… 2 017年1月6日 毎日新聞 福島県広野町の「高野病院」でただ一人の常勤医だった高野英男院長(81)が火災で亡くなったことを受け、全国の医師からボランティアの申し出が相次いでいる。支援グループに関東や九州など少なくとも31人が協力を申し出ており、月内の人繰りにはめどがついた。だが、医療法などの規定で常勤医が必要で、福島第1原発事故被災地の医療を守ってきた病院は危機にひんしている。 火災は昨年12月30日夜、病院敷地内で高野さんが1人暮らしをする宿舎で発生。木造平屋建て住宅の一部を焼き、室内から高野さんの遺体が見つかった。 院長以外の医師9人は非常勤で、勤務ローテーションが組めなくなった。入院患者は約100人。県内の若手医師が「支援する会」を発足させ、フェイスブックなどでボランティア医師を募っている。このほか、町や病院に複数の医師が支援を申し出ているという。 厚生労働省によると、医療法などで病院管理者の要件は常勤医師と定められている。病院が県や国に支援を求めているが、確保の見通しは立っていない。 二人三脚で病院を支えてきた理事長で次女の己保(みお)さん(49)によると、高野さんは県内外で勤務医を経験し、古里・南相馬市に近い広野町で1980年に高野病院を開いた。院長室に布団を持ち込み、ほぼ24時間体制で地域医療に打ち込んだ。2003年、敷地内に宿舎を建てた。己保さんは「父はこの病院が好きで患者を一番に考えていた」と振り返る。 11年3月の原発事故で町民の大半が一時避難。高野さんは一部の入院患者と一緒に病院に残った。その後も双葉郡8町村で唯一の病院として帰還した住民や廃炉作業員の外来診療を担った。 週2、3日は当直に入り、救急患者にも対応してきた。足元がふらつくこともあり、己保さんが体調を気遣うと「患者がいる。臨床医とはそういうものだ」と気丈に語ったという。己保さんは「患者さんたちを放り出すわけにいかず、存続できるのなら病院を町に寄付してもいい」と訴えている。【曽根田和久、高井瞳】 |
| 「高野病院」医師支援へ資金援助を...広野町がネットで呼び掛け 2017年01月10日 福島民友新聞 原発事故後も双葉郡内で唯一、入院患者を受け入れている高野病院(広野町)の院長高野英男さん(81)が火災で亡くなり常勤医が不在になっている問題で、町は9日、インターネット上で資金援助を募るクラウドファンディングの取り組みを始めた。町や支援する会などに対し、窮状を知った全国の人から「せめて寄付という形で力になりたい」と申し出が相次いでいる。 高野病院では昨年12月30日以来、院長と常勤医が共に不在の非常事態が続いている。高野さんに代わって診療に当たっているボランティアの医師は「無償で協力する」と申し合わせているため、寄せられた資金は医師の宿泊費や交通費に役立てる。これらの費用については、町が負担する方針を示しており、資金は支援制度の財源として活用される。 目標額は250万円。寄付は1口3000円からで、2月28日まで受け付ける。ふるさと納税制度を適用し、寄付した人は税控除を受けられる。9日午後8時30分時点で、90人から計126万8000円が寄せられ、目標額の半分を突破した。 「地域医療」守るため 支援する会の呼び掛けで全国から延べ30人以上の医師が協力に名乗りを上げ、1月中は診療を続けられる見通しだが、中長期的な医療体制の構築は予断を許さない。会長の遠藤智町長は「全国からの支援に感謝の念に堪えない。皆さんの厚情に応えるべく、被災地の地域医療を守るため全力で取り組む」と力を込めた。 同会の中心メンバーの一人で南相馬市立総合病院の尾崎章彦医師(31)は「高野さんの功績やスタッフの頑張りが評価され、高い関心が寄せられていることに感謝している」と語った。また、高野病院は地域医療を担う社会インフラとして重要な役割を果たしてきたとし、寄付をきっかけに「原発事故の被災地にとどまらず、過疎地域ではどこでも起こり得る問題であり、全国の人に自分のこととして考えてほしい」と訴えた。 |
最後まで読んでくださってありがとう


 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね












































