元旦の翌日は、わたしの誕生日。
メールやフェイスブックでお祝いをいただいた皆さま、ありがとうございます。
ちなみに、
「1月2日生まれ」は一年365年のうち、3番目に少ないとのこと。
お正月とバースデイで二度めでたい、かどうかは不明ですが、
お正月で仕事はお休みなので、誕生日祝いをかねて、
子どもたちが遠くから集まってきてくれるのはうれしいです。
きょうはわたしたちは、10時に予約したケーキを取りにいってきて、
こどもたちはお昼前にあつまって、持参したものや買ってきたもので、
てきぱきと食事の準備。
わたしは昨日までに、なますや黒豆、たつくりなどを作っておいて、
きょうは誕生日なのでみてるだけ(笑)。

更科の冷やしたぬきそばもゆであがって、
みんなそろって「いただきます」。

3時には、バースディケーキをいただきました。

ともちゃんが予約したフランボワーズのホールケーキ「プリンセス」と、
健さんとみくさんからは、ヒコハヤシのショートケーキ。

ケーキは、イチゴをどけておいて、人数分に切り分けました。

つれあいの好物のバームクーヘンや、お菓子もいっぱい。
おなか一杯になったので、分けっこしておみやげにしてもらいました。

ケーキは食べきれなかったので冷蔵庫へ。

まどかさんとなほこさんからは、北海道のズワイガニをいただきました。

カニとショートケーキは、明日以降のたのしみにしましょう。
みんなが帰ったあとは、のんびりと二人。
これから夕ご飯です。
無心に遊ぶ小さなひとたちをみていると、
戦争や暴力のない平和な社会をのこしたい、と願わずにはいられません。
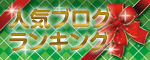 応援クリック してね
応援クリック してね 


社説:憲法70年の年明けに 「立憲」の理念をより深く
2017年1月1日(日)付 朝日新聞
世界は、日本は、どこへ向かうのか。トランプ氏の米国をはじめ、幾多の波乱が予感され、大いなる心もとなさとともに年が明けた。
保守主義者として知られる20世紀英国の政治哲学者、マイケル・オークショットは、政治という営みを人々の航海に見立てている。
海原は底知れず、果てしない。停泊できる港もなければ、出航地も目的地もない。その企ては、ただ船を水平に保って浮かび続けることである――。
今年の世界情勢の寄る辺なさを、予見したかのような言葉として読むこともできるだろう。
と同時にそれは本来、政治にできることはその程度なのだという、きわめて控えめな思想の表現でもある。
昨今、各国を席巻するポピュリズムは、人々をあおり、社会に分断や亀裂をもたらしている。民主主義における獅子身中の虫というべきか。
オークショットのように抑制的で人気取りとは縁遠い政治観は、熱狂や激情に傾きがちな風潮に対する防波堤の役割を果たす。
■人々の暮らしの中で
不穏な世界にあって、日本は今年5月、憲法施行70年を迎える。
憲法もまた、政治の失調に対する防波堤として、大切な役割を担ってきた。その貢献の重みを改めて銘記したい。
「立憲主義」という言葉の数年来の広がりぶりはめざましい。政治の世界で憲法が論じられる際の最大のキーワードだ。
中学の公民の教科書でも近年、この言葉を取り上げるのが普通のことになった。
公の権力を制限し、その乱用を防ぎ、国民の自由や基本的人権を守るという考え方――。教科書は、おおむねこのように立憲主義を説明する。
それは人々の暮らしの中で具体的にどう働くのか。
例えば、政党機関紙を配った国家公務員が政治的な中立を損なったとして起訴されたが、裁判で無罪になった例がある。判断の背景には、表現の自由を保障した憲法の存在があった。
■民主主義をも疑う
立憲主義は、時に民主主義ともぶつかる。
民主主義は人類の生んだ知恵だが、危うさもある。独裁者が民主的に選ばれた例は、歴史上数多い。立憲主義は、その疑い深さによって民主主義の暴走への歯止めとなる。
根っこにあるのは個人の尊重だ。公権力は、人々の「私」の領域、思想や良心に踏み込んではならないとする。それにより、多様な価値観、世界観を持つ人々の共存をはかる。
ただ、こうした理念が、日本の政界にあまねく浸透しているとは到底いえない。
自民党は立憲主義を否定しないとしつつ、その改憲草案で「天賦人権」の全面的な見直しを試みている。
例えば、人権が永久不可侵であることを宣言し、憲法が最高法規であることの実質的な根拠を示すとされる現行の97条を、草案は丸ごと削った。
立憲主義に対する真意を疑われても仕方あるまい。
衆参両院の憲法審査会は昨年、立憲主義などをテーマに討議を再開したが、議論の土台の共有には遠い。
どんな立場を取るにせよ、憲法を論じるのなら、立憲主義についての真っ当な理解をより一層深めることが前提でなければならない。
■主要国共通の課題
立憲主義にかかわる議論は、欧米諸国でも続く。
一昨年のパリ同時多発テロを経験したフランスでは、非常事態宣言の規定を憲法に書き込むことが論じられたが、結果的に頓挫した。治安当局の権限拡大に対する懸念が強かった。
同じくフランスの自治体が、イスラム教徒の女性向けの水着「ブルキニ」を禁止したことに対し、行政裁判の最高裁に当たる国務院は「信教と個人の自由を明確に侵害する」という判断を示した。
個人、とりわけ少数者の権利を守るために、立憲主義を使いこなす。それは今、主要国共通の課題といっていい。
環境は厳しい。反移民感情や排外主義が各地で吹き荒れ、本音むき出しの言説がまかり通る。建前が冷笑されがちな空気の中で、人権や自由といった普遍的な理念が揺らぐことはないか、懸念が募る。
目をさらに広げると、世界は立憲主義を奉じる国家ばかりではない。むしろ少ないだろう。
憲法学者の長谷部恭男・早稲田大教授は「立憲主義の社会に生きる経験は、僥倖(ぎょうこう)である」と書いている。
であればこそ、立憲主義の理念を、揺らぎのままに沈めてしまうようなことがあってはならない。
世界という巨大な船が今後も、水平を保って浮かび続けられるように。 |
社説:不戦を誇る国であれ 年のはじめに考える
2017年1月1日 中日新聞
新年早々ですが、平和について一緒に考えてください。人類はなぜ暴力を好み、戦争がやめられないのか。どうしたらやめる方向へと向かうのか。
日本の平和主義を二つの観点から見てみましょう。
一つは、だれもが思う先の大戦に対する痛切な反省です。
振り返れば、日本は開国をもって徳川の平和から明治の富国強兵へと突入します。
平和論より戦争論の方が強かった。「和を以(もっ)て貴しと為(な)す」の聖徳太子以来の仏教の平和論をおさえて、ヨーロッパの戦争論がやってきます。
例えば「戦争は政治の延長である」という有名な言葉を記すプロイセンの将軍クラウゼヴィッツの「戦争論」。その一、二編はドイツ帰りの陸軍軍医森鴎外によって急ぎ翻訳され、続きは陸軍士官学校が訳します。海洋進出を説く米国の軍人で戦史家マハンの「海上権力史論」も軍人必読でした。
欧米の戦争を学ぶ。いい悪いはともかくも追いつかねば、の一意専心。帝国主義、植民地主義。日清、日露の戦争。
そういう戦争精神史をへて突入したのが、満州事変に始まって太平洋戦争に至るいわゆる十五年戦争です。
最大の反省は人間が人間扱いされなかったことです。人間が間化されたといってもいいでしょう。そういう異常の中で敵側は人間以下であろうし、味方にもむやみな死を求める。
クラウゼヴィッツのいう政治目的の戦争ではもはやなく、ただ進むしかない、戦争を自己目的化した戦いになっていたといっていいでしょう。
ただの戦争嫌いでなく
その絶望の果てに戦後日本は不戦を尊び固守してきたのです。
守ってきたのは元兵士と戦争体験者たちです。
文字通り、命がけの訴えといってもいいでしょう。ただの厭戦(えんせん)、戦争嫌いというのでなく、国は過ちを犯すことがあるという実際的な反省でもあります。国民には冷静な目と分析がつねに必要だという未来への戒めです。
日本の平和主義についての二つめの観点とは、戦後憲法との関係です。
戦争勝者の連合国は敗者の日本、イタリア、西ドイツに非軍事化条項を含む憲法を求めた。
戦後冷戦の中で日本はアメリカの平和、いわゆるパックス・アメリカーナに組み込まれ、自衛隊をもちます。
その一方で稀有(けう)な経済成長に恵まれ、その資力を主にアジアの発展途上国への援助に役立てます。
ここで考えたいのは、平和主義とはただ戦争をしないだけでなく平和を築こうということです。前者を消極的平和、後者を積極的平和と呼んだりもします。
例えば積極的平和を築こうと一九六〇年代、平和学という学問分野が生まれ、ノルウェーにはオスロ国際平和研究所ができた。政治や法律、経済、国際関係、歴史、哲学、教育など科学を総動員して平和を築こうというのです。
実際にノルウェーは大国などではありませんが、イスラエルとパレスチナの間に和平をもたらそうというオスロ合意を成立させた。中東の国連平和維持活動に出ていて、両者の争いを終わらせるのは武力でなく対話しかないと考え至るのです。今は失敗かとまでいわれますがその熱意と意志を世界は忘れていません。
日本国憲法の求める平和主義とは武力によらない平和の実現というものです。
対象は戦争だけでなく、たとえば貧困や飢餓、自然災害の被害、インフラの未発達など多様なはずです。救援が暴力の原因を取り去るからです。
NGО、非政府組織の活動が広がっている。ミリタリー、軍事から、シビリアン、民間への移行です。日常の支援が求められます。ミリタリーの非軍事支援も重要になっている。
だが残念ながら世界は不安定へと向かっているようです。
武力によらない平和を
格差とテロとナショナリズム。それらが絡み合って国や民族が相互不信の度を高めつつある。しかし不信がつくられたものなら、解消することもできるはずです。
そういう時だからこそ、私たちは平和主義、世界に貢献する日本の平和主義をあらためて考えたいのです。
ただの理想論を言っているのではありません。武力によらない平和を求めずして安定した平和秩序は築けない。武力でにらみあう平和は軍拡をもたらすのみです。
理想を高く掲げずして人類の前進はありえないのです。 |
最後まで読んでくださってありがとう 
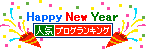
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね 












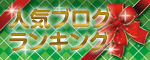 応援クリック してね
応援クリック してね 












 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。










































 ローストビーフもつれあいです。
ローストビーフもつれあいです。











