7月に登った伊吹山。
山頂付近は日本有数のお花畑です。
わたしたちが行った後、台風によるがけ崩れで
ドライブウェーが通行止になっていたのですが、
明日5日から開通します。
きっと7月とは違うお花が咲き乱れているのでしょう。
また行きたい!







昨年末から続けてきた上野千鶴子さんの
『女ぎらい~ニッポンのミソジニー』読書会も、8月でいよいよ最終章。
この本の編集者と、先日紹介した島今日子さん著
『〈わたし〉を生きる―女たちの肖像』(紀伊國屋書店)の編集者は同じかた。
とてもすてきな方で、上野さんつながりで知り合って、
島崎さんの本も送ってくださったのです。
もちろん! 女性、です。
上野千鶴子さん登場の新刊二冊~『“わたし”を生きる―女たちの肖像』
『脱原発社会を創る30人の提言』(2011-07-27)
ちょうど今日、PCの前で仕事をしていたら(ここ半月ほど朝から晩までですが)、
『〈わたし〉を生きる―女たちの肖像』の著者の島崎今日子さんと、
上野千鶴子さんの刊行記念トークイベントが、10月6日にリブロ池袋であると知らせてくださいました。
イベントはすでにホームページで公開され、チケット販売がはじまっています。
参加チケットは1000円とめちゃお値打ちですが、定員は100人。
きっとすぐに満員になってしまうので、聴きたい人は、お早めに
「リブロ池袋本店書籍館地下1階リファレンスカウンター」まで。
ところで、リブロ池袋本店って、どこにあるんだろう・・・?
もうすぐ東京に行くので、チケット買いに行きたいんだけど、
わたしのブログを見て申し込みが殺到して、
満席になってしまったら・・・と悩ましい(笑)。
広い東京のこと、迷子になるといけないから、まずはGoogle地図で探してみよっと。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
ついでに、と言ってはなんですが、
上野さんが「ちづこのブログNo.12」を更新されました。
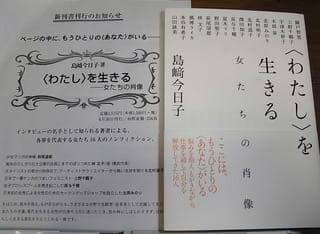
『〈わたし〉を生きる―女たちの肖像』と一緒に紹介した、
『脱原発社会を創る30人の提言』の記事です。

「あとは本を買って読んでくださいね」とのことなので、ブログの冒頭部分だけ紹介。
わたしはもう読みましたが、これだけ読めば、福島原発事故後の
「いまとこれから」がわかる、おススメの本です。
おまけ。
「フェミニズムの先駆者」に誇り 退職の上野千鶴子が特別講義(朝日新聞)の記事。
この記事へのアクセス、とっても多いので再掲します。

最後まで読んでくださってありがとう
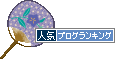
 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

山頂付近は日本有数のお花畑です。
わたしたちが行った後、台風によるがけ崩れで
ドライブウェーが通行止になっていたのですが、
明日5日から開通します。
きっと7月とは違うお花が咲き乱れているのでしょう。
また行きたい!







昨年末から続けてきた上野千鶴子さんの
『女ぎらい~ニッポンのミソジニー』読書会も、8月でいよいよ最終章。
この本の編集者と、先日紹介した島今日子さん著
『〈わたし〉を生きる―女たちの肖像』(紀伊國屋書店)の編集者は同じかた。
とてもすてきな方で、上野さんつながりで知り合って、
島崎さんの本も送ってくださったのです。
もちろん! 女性、です。
上野千鶴子さん登場の新刊二冊~『“わたし”を生きる―女たちの肖像』
『脱原発社会を創る30人の提言』(2011-07-27)
ちょうど今日、PCの前で仕事をしていたら(ここ半月ほど朝から晩までですが)、
『〈わたし〉を生きる―女たちの肖像』の著者の島崎今日子さんと、
上野千鶴子さんの刊行記念トークイベントが、10月6日にリブロ池袋であると知らせてくださいました。
イベントはすでにホームページで公開され、チケット販売がはじまっています。
参加チケットは1000円とめちゃお値打ちですが、定員は100人。
きっとすぐに満員になってしまうので、聴きたい人は、お早めに
「リブロ池袋本店書籍館地下1階リファレンスカウンター」まで。
| 10月6日(木)島今日子『〈わたし〉を生きる―女たちの肖像』 刊行記念トークイベント「規格外な女たち」 ジェンダーをテーマとして幅広いジャンルで取材・執筆活動を続けるジャーナリスト・島今日子さんが、少女マンガの神様・萩尾望都、高卒OLから巨大企業の会長にのぼりつめた林文子、女子プロレスブームを巻き起こした長与千種など、さまざまな分野の先駆者・改革者として活躍してきた16人の女たちを描いた『〈わたし〉を生きるー女たちの肖像』の刊行を記念して、ジェンダー研究のパイオニア・上野千鶴子さんとのトークイベントを開催致します。 2人がこれまで出合ってきた、前例に関係なく道なき道を切り拓いてきた女たちの生きざまから、これからの女子の生き抜く道までを語り合うトークライブ。インタビューの名手としても知られる2人が、どのように対象に切り込んできたのか、その極意についても語ります。 日時:10月6日(木) 午後7時~ 会場:西武池袋本店別館8階池袋コミュニティ・カレッジ コミカレホール 定員:100名 参加チケット:税込1,000円 チケット販売場所:リブロ池袋本店書籍館地下1階リファレンスカウンター お問合せ:リブロ池袋本店 03-5949-2910 【プロフィール】 島今日子:1954年京都生まれ。ジャーナリスト。インタビューの名手として知られ、ジェンダーをテーマに人物・時代・メディアなど、幅広いジャンルで取材・執筆活動を続ける。著書に『この国で女であるということ』(ちくま文庫)、『女学者丁々発止!』(学陽書房』、『芸人女房伝』(集英社文庫)など。 上野千鶴子:1948年富山県生まれ。社会学者、NPO法人ウィメンズ・アクション・ネットワーク理事長、東京大学名誉教授。女性学、ジュンダー研究のパイオニア。1994年『近代家族の成立と終焉』でサントリー学芸賞を受賞。『家父長制と資本制』(岩波書店)、『女ぎらい』(紀伊国屋書店)など著書多数。『おひとりさまの老後』(法研)は75万部のベストセラーに。 撮影:松本路子 |
ところで、リブロ池袋本店って、どこにあるんだろう・・・?
もうすぐ東京に行くので、チケット買いに行きたいんだけど、
わたしのブログを見て申し込みが殺到して、
満席になってしまったら・・・と悩ましい(笑)。
広い東京のこと、迷子になるといけないから、まずはGoogle地図で探してみよっと。
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
ついでに、と言ってはなんですが、
上野さんが「ちづこのブログNo.12」を更新されました。
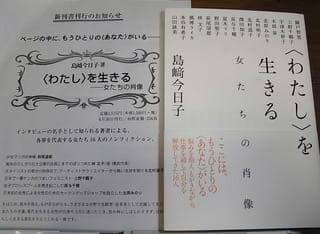
『〈わたし〉を生きる―女たちの肖像』と一緒に紹介した、
『脱原発社会を創る30人の提言』の記事です。

「あとは本を買って読んでくださいね」とのことなので、ブログの冒頭部分だけ紹介。
わたしはもう読みましたが、これだけ読めば、福島原発事故後の
「いまとこれから」がわかる、おススメの本です。
| 『脱原発社会を創る30人の提言』 ちづこのブログNo.12 『月刊うえの』と言われるぐらい、このところ新刊が次々にでていますが、そのうちのひとつを、ご紹介。 脱原発社会を創る30人の提言 著者/訳者:池澤 夏樹 坂本 龍一 池上 彰 出版社:コモンズ( 2011-07-15 ) -------------------------------------------------------------------------------- .『脱原発社会を創る30人の提言』(コモンズ、2011年)が出ました。 30人とは、以下のひとびと。 池澤夏樹、坂本龍一、池上彰、日比野克彦、上野千鶴子、大石芳野、小出裕章、後藤政志、飯田哲也、田中優、篠原孝、保坂展人、吉原毅、宇都宮健児、秋山豊寛、藤田和芳、纐纈あや、上田紀行、仙川環、崎山比早子、大島堅一、斎藤貴雄、星寛治、明峰哲夫、中村尚司、瀬川至朗、高橋巌、菅野正寿、鈴木耕、渥美京子。 順不同。順番は50音順でもありません。なぜだかこの順番で表紙に載っているのをそのまま記載しました。 コモンズは良心的な出版活動を続けてきた小出版社。名前のとおり、コモンズ(共有地)を用いて、知のコモンズ(共有知)をめざそうとしています。編者の名前はありませんが、版元のコモンズ代表の大江正章さんが、これまで食と環境、自治と地域にかかわった出版活動のなかから培ってきた著者とのネットワークがまるごと生きています。大手の出版社が「原発に関する発言○○人」と出すラインナップとは、ひと味違います。初版5千部はただちに売れて、再版したそうです。 版元のお許しを得て、わたしの「提言」のなかから冒頭部分を。全文引用はかんべんしてください、との版元からのご依頼があって、公開はここまで。あとは本を買って読んでくださいね。 ・・・・・(以下略・続きを読みたい方は「ちづこのブログNo.12」へどうぞ)・・・・・ (WAN上野千鶴子web研究室) |
おまけ。
「フェミニズムの先駆者」に誇り 退職の上野千鶴子が特別講義(朝日新聞)の記事。
この記事へのアクセス、とっても多いので再掲します。
| 「フェミニズムの先駆者」に誇り 退職の上野千鶴子が特別講義 2011年7月28日 朝日新聞 今年3月に東京大学を退職した社会学者・上野千鶴子の特別講義が9日、東大で開かれた。3月に予定されていた最終講義が、震災の影響で延期されていた。 上野は1982年、『セクシィ・ギャルの大研究』で論壇デビュー。フェミニズムと女性学の代表的な論客として活動し、老後の女性シングルの生き方を論じた『おひとりさまの老後』(2007年)は、ベストセラーになった。 自らを「女性学というベンチャーの創業者」という上野は、フェミニズムを「女性解放の思想と行動」、女性学を「フェミニズムのための理論と研究」と定義し、車の両輪にたとえた。70年代のウーマンリブ運動からフェミニズムが、さらにその実践を言語化、理論化するために女性学が生まれたという。 女性学は当事者の学問であり、40年前に、大学の外で民間学として始まった。『当事者主権』という共著書もある上野は、当事者の権利とは「私の運命は私で決める、という誰にも譲り渡すことのできない至高の権利だ」とする。社会的弱者はその権利を長く奪われてきたが、いまや女性学だけでなく、患者学、ケア学など、「弱者」とされてきた当事者の視点に立った学問は大きな潮流となった。 「超高齢化社会が来てよかったと思っている。かつて強者であった人も、最後には誰かに支えてもらわないと自分の生を全うできない。強者も、自分が弱者になる可能性を想像しなければならない社会だからです」 フェミニズムも女性学も、その意味では、女性だけのためのものではない。弱者が弱者として尊重される社会をめざすものなのだ。 「フェミニズムの権威、とは呼ばれたくないが、パイオニアと呼ばれることには誇りを持っている」 もちろん、それは一人が切り開いたものではない。上野自身、19世紀末までさかのぼる女性運動の先人たちから「バトンを受けついできた」という自覚がある。 「私はフェミニズムの評判がどんなに悪くなっても、この看板は下ろさない。語る言葉を持たなかった女たちが、言葉をつくるために悪戦苦闘してきた。その先輩たちのおかげで私はいる」 上野が講演の最後をこう締めくくると、教え子も多数詰めかけた会場に万雷の拍手が響いた。 「恩返しのために、次の世代へ渡す時期が来た。バトンは受け取る人がいないと落っこちてしまう。どうぞ受け取って下さい」 この講義の模様はインターネットで視聴できる(http://wan.or.jp/)。(樋口大二) |

最後まで読んでくださってありがとう

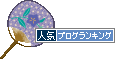
 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね



























