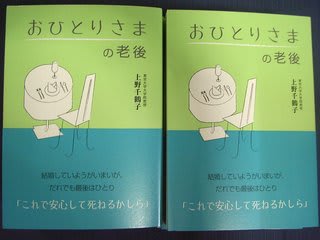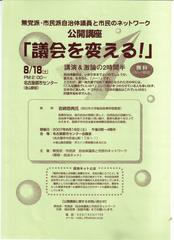2007年度の4回連続講座の最後となるまとめの勉強会。
きのう病院で「明日、とまりの勉強会の講師なんですけど・・・」
と言ったら、「お仕事ならいいですよ。無理をしないようにね」。
といっても、3~4時間のコマが三つもあるのだから、
あまり自信はない。
今回は、《予算&一般質問》とシンプルで、「一般質問」はわたし、
「予算関係」はともまささん、とおもな分担が決まっているので、
疲れたら、セッション2の予算は、ともちゃんに任せようと思う。
いつもなら、もっと早くできる内容と日程の詳細も、
昨夜になって、ようやく詰めて、参加者に知らせた。
「む・しネット」で勉強会をつづけてもう6年になるけれど、
毎回工夫して、同じ内容にはならないようにしている。
今回も、参加者にあわせてカスタムメイド。
以下に、参加できない人にも、ちょっとだけ内容を紹介しますね。
| 2007年度 第4回 『議員と市民の勉強会』 日程表 講師:寺町みどり&ともまさ 於 ウィルあいち 1月26日(土) 13:00~20:00 《予算&一般質問》 1月27日(日) 9:00~14:00 オプション講座 ●内容とスケジュール 1月26日(土)13:00~ 開会・説明 【セッション1】 13:05~15:35 (150分) 「一般質問を事後評価する」 13:05~【課題2-B】の「うまくいった質問、失敗した質問」について、 その理由と今後の課題を各1分半で説明、3分で講師コメント。 14:20~【課題2-A】の「一般質問でつまづいていること」を1分で簡潔に質問、 4分で講師からアドバイス。 15:20~35 一般質問の実例 ・・・組み立てと獲得目標 【セッション2】 15:50~18:45 (175分) 「予算」 1)総論~予算とは何か/行政における予算の流れ/議会における予算審議 2)各論~予算書の読み方/予算審議の手法/政策としての予算 3) 16:30~ ★課題1~予算関係 A. H19年度の予算資料から読み出してくる(一部は担当から訊き出す) ①と② 他自治体との比較 住民一人 総予算 起債 基金 ③ 債務負担行為 億、 損失補償・債務保証 件・億 債務負担行為に計上されている複数年の契約 件・億 債務負担行為に計上していない長期継続契約 件・億 ④ 土地開発公社。長期保有土地(5年以上のもの) 件・億 B. 議会の予算審議のあり方などの問題点。改善点 C.予算を増額修正、D.削除 E.新規に追加 4)18:20~45 ディスカッション 【セッション3】 19:00~20:00 ディスカッション~1年間を振り返って。 ★プレゼンテーション 課題3の「1年間を振り返って」と「2年目のわたしの課題」各1分ずつでプレゼン。 ★ディスカッション 1年間の勉強会を振り返って獲得したことと、次年度をどうしたいかetc。 ---------------------------------------------------------------------- 【オプション講座】 1月27日(日) 9:00~14:00 ● 前日のセッションをさらに深め、あなたが抱えている《予算&一般質問》、 その他 議会のことなど個別の課題についてアドバイスします。 |
こちらは、勉強会参加者に事前に出した課題です。
| 【課題1 予算関係】 ●設問の趣旨の説明 A. H19年度の予算資料から読み出してくる ① ②については、予算書・関係資料をみれば困難はありません。 ③ の債務負担行為については、初めて予算に取り組む人は チンプンカンプンかもしれません。それを解く手助けです。 「債務負担行為に計上していない長期継続契約」については、 何年も予算審議を経験した人でも担当にきかないと分からないと思います。 そのつもりで取り組んでください。 ④ の土地開発公社関係は、18年度決算から導いてもいいです。 公社の長期保有土地(5年以上のもの)については、 担当にきかないと分からないと思います。 B. 議会の予算審議のあり方などの問題と思うところ。改善させたいところ。 何かあればどうぞ。 C. 予算を増額修正させたい事項(事業)や内容を一つ示してください。 D. 予算から削除させたい事項(事業)や内容を一つ示してください。 E. 予算に新規に追加させたい事項(事業)や内容を一つ示してください。 一括同趣旨ですが、予算とは政策実現が如実に現れるもの。 あなたのこだわり、あるいは気づいたことの何でも、 何しろ現状を変えるのが議員の大事な仕事の一つ (何かも現状のままでいいなら、議員は要らない)だから、 そのことを具体的に意識化していただくための設問です。 大きなことでも、小さなことでも、ハードでも、ソフトでも、どうぞ。 【課題2-A 一般質問 】 ・あなたの6月、9月、12月の一般質問について、それぞれの数、 個別の質問について「テーマ、政策的な分類、目的別の分類」をしてください。 ・一般質問でつまづいていること(聞きたいこと)を二つ書いてください 【課題2-B 一般質問 】 今年度にあなたが取り組んだ一般質問のうち、 「うまくいった質問、うまくいかなかった(失敗した)質問」を、 それぞれひとつずつ選んでください。 それぞれの一般質問(計2テーマ) について、A4版のレジメ1枚 (各テーマ1,200字以内×2枚)に作成して提出してください。 1.タイトル (40字) 2.獲得目標 (40字以内) その質問の「獲得目標」はどのようですか? 3.一般質問の質問および構成(300字) 4,答弁の要旨・説明(300字) 5.うまくいった(失敗した)と思う理由(300字) 6.今後の課題(200字) |
何とか、体調を整えて、本番にのぞみたい。
今回、普段は低い血圧が先週からいきなり200超で、頻脈や動悸もあり、
重症高血圧ということで、心臓に原因があるんじゃないかということで、
心電図や心エコー、胸部レントゲンなどいろんな検査を受けた。
昨日までの検査では、主に、心臓とホルモンの異常を調べていたのだけど、
検査の結果は、特に病名がつくような異常はない、とのことで、
まずは一安心。原因は不明とのこと。
ほっとしたこともあって、今朝の血圧は97/66。
夜中は84/46。えっわたし生きてるの?と一瞬思った(笑)。
これって下がりすぎじゃない?とまた別の不安が頭をかすめる。
医師は真っ先に「ホルモンの数値は若干高いものがありますが、
このくらいなら異常はないですね」と言った。
医師が心配していたのは、「甲状腺機能亢進症」のようだ。
わたしが疑っていたのは、むしろ副腎ホルモンの異常。
わたしは、今回の体調不良は、症状のでかたから見て、
前に紹介した漢方薬の「甘草」の副作用じゃないかと思っているのだけど、
医者にも、これ以上は分からないようだ。
ノルアドレナリンとドーパミンの数値が高いので、
ストレッサーによわくなっているようだ。
いずれにしても、
ストレスが万病の元、というのは確かなようです。
写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大
最後まで読んでくださってありがとう

2008年も

 遊びに来てね
遊びに来てね 
 また明日ね
また明日ね