倉庫の南にあったパイプハウスを道の下の畑に設置したので、
今年は、冬になっても、青々とした野菜がたくさんとれます。
ハウスの中は暖かいので、葉物が徒長しないように、
水やりを減らしています。
ハウスの中のホウレンソウとレタスの畝の間に
見慣れない葉っぱがあるので、何だろうと思って
引っ張ってみたのですが、土が堅くて根がしまってなかなか抜けません。
ショベルで掘ってみたら、日野菜カブ、でした。
日野菜はお漬物にするとおいしいので、
さっそく少し収穫してきました。

きれいに洗って、半日ほど干して、

昆布茶で少ししんなりさせて出たアクを絞ってから、
浅漬けにしました。
一夜明けて、

歯ごたえがあってかおりのよい日野菜カブのお漬物ができました。
水菜はお揚げとちりめんじゃこの炊き合わせに。

細いので、さっと数分火を通しただけでできあがり。

クリック してね



冬においしい根菜類で、筑前煮も作りましょう。
人参とスナップエンドウは、畑でとれたもの。



根菜類をラウス昆布角切りを入れて炊いてから、

さいごに、スナップエンドウと鶏ムネ肉を戻し入れ、
3分ほど火を通してなじませてできあがり。

パスタをグラタンにしたり、冷凍卵を目玉焼きにしたり


残り物ばかりの、豪華でおいしい朝ごはんです。

最後まで読んでくださってありがとう
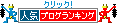 クリック してね
クリック してね 


 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

今年は、冬になっても、青々とした野菜がたくさんとれます。
ハウスの中は暖かいので、葉物が徒長しないように、
水やりを減らしています。
ハウスの中のホウレンソウとレタスの畝の間に
見慣れない葉っぱがあるので、何だろうと思って
引っ張ってみたのですが、土が堅くて根がしまってなかなか抜けません。
ショベルで掘ってみたら、日野菜カブ、でした。
日野菜はお漬物にするとおいしいので、
さっそく少し収穫してきました。

きれいに洗って、半日ほど干して、

昆布茶で少ししんなりさせて出たアクを絞ってから、
浅漬けにしました。

一夜明けて、

歯ごたえがあってかおりのよい日野菜カブのお漬物ができました。
水菜はお揚げとちりめんじゃこの炊き合わせに。

細いので、さっと数分火を通しただけでできあがり。

クリック してね




冬においしい根菜類で、筑前煮も作りましょう。
人参とスナップエンドウは、畑でとれたもの。



根菜類をラウス昆布角切りを入れて炊いてから、

さいごに、スナップエンドウと鶏ムネ肉を戻し入れ、
3分ほど火を通してなじませてできあがり。

パスタをグラタンにしたり、冷凍卵を目玉焼きにしたり


残り物ばかりの、豪華でおいしい朝ごはんです。

最後まで読んでくださってありがとう




 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね









































































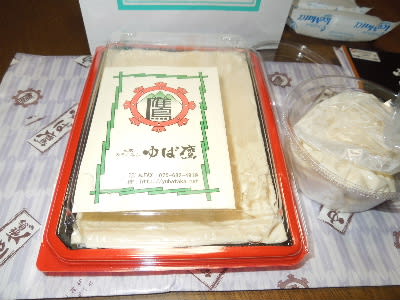







 ロロンカボチャ
ロロンカボチャ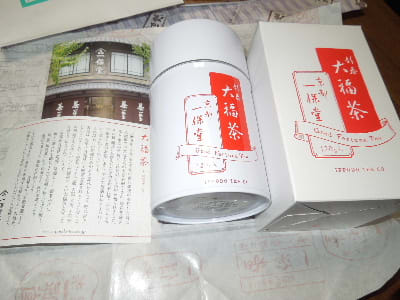






 お茶の葉にさらに熱湯をそそいで、
お茶の葉にさらに熱湯をそそいで、
































