




ギィ・ド・モーパッサン
私は、この物語の素晴らしさをうまく説明する術を持ち合せていないことを
とてもじれったく感じています。
モーパッサンが作家となった初期に書かれた2作品ですが
デビュー早々こんなに円熟していていいのでしょうか?
『脂肪の塊(Boule de Suif)/1880年』

時はプロシア占領下のフランス、ルーアンからル・アーブルに向かう馬車に
10人の客が乗り合わせたことから始まる物語。
客は3組の町の名士夫妻と2人の修道女、そして民主主義者コルニュデと
“ 脂肪の塊 ” というあだ名の人気者の娼婦でした。
細かいあらすじを書いてもはじまらないのですが、読み終わった時
私たちは名士夫妻たちや修道女に怒りを覚え、“ 脂肪の塊 ” に
おおいに同情をよせるでしょう。
だいたい、妻は分かるとして夫たち!
“ 脂肪の塊 ” を汚らわしいもののようにあしらいますが、妻が側にいなきゃ
真っ先に言い寄るのはあんたたちだろうが!って言いたいわ

ただ同じ立場に自分がおかれたら・・・と思うと悩みますね。
虚栄心、優越感、羞恥心が邪魔をして可哀想な娼婦に温かく接することなど
できないかもしれません。
集団心理の怖さってこういうところに潜んでいるのかもしれませんね。
『テリエ館(La Maison Tellier)/1881年』

優雅なマダム・テリエが営む娼館テリエ館の物語。
町の名士の社交場であるサロン、労働者たちの憩いの場カフェを併せ持つ
堂々たる人気店が、ある日突然お休みします。
マダム・テリエは5人の娼婦たちを引き連れて、姪の聖なる儀式に出向いていました。
こちらはあっけらかんとしてていいですね。
聖体拝受式に出席して厳かな心になった女たちも、夕方にはお店に出て商売に精をだし、
マダム・テリエも気前のいいところをみせて、なんだか娼館賛美のようにも思える結末。
日本で娼婦を扱うとどうしてもしめっぽくなりがちですから・・・
さすがフランスって感じです。
2篇とも娼婦を主人公にした物語ですが、印象がまったく違います。
もっとも、あくまでも彼女たちのある一部分を切り取った物語ですから
どちらが幸せでどちらが不幸だなんて言えないのですけれどもね。
『脂肪の塊』の彼女もふだんはおもしろおかしく暮らしているかもしれないし
『テリエ館』の女たちも悔しくてやりきれないことがあるかもしれません。
とにかく、新人とは思えない表現力と落ち着いた筆運び… 名作です。
そして、この2話がセットになってるのが面白さを倍増してる!
これから先、何度読んでもあきないと思います。
 | 脂肪の塊・テリエ館 新潮社 このアイテムの詳細を見る |

















 のロベールと再婚します。
のロベールと再婚します。 気持ちは分かります。
気持ちは分かります。




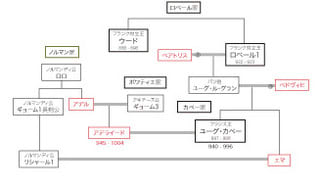

 オースティンの好みでしょうか?)
オースティンの好みでしょうか?)

 余談です
余談です

















 こっぱずかしい~
こっぱずかしい~









