THE MILLSTONE 


1965年 マーガレット・ドラブル
この本は自由が丘にある古本屋さんで買いました。
その古本屋さんには百円コーナーがあって、とんでもない掘り出し物があるの。
百円だったので手を出してみた一冊で、特に期待はしていませんでした。
出だしが若者都会派小説みたいに思えたので「あちゃ~」と後悔しつつ読み始めたのですが
読んでいたらだんだん面白くなってきて、すぐに読み終えてしまいました。
アフリカに赴任中の両親が残していってくれた高級住宅街のフラットで暮らしている
ロザマンドは、ある日妊娠したことに気がつきました。
ロザマンドは作家のジョーと計理士のロージャーと遊び歩いていましたが
思わせぶりに接するだけで、深い関係ではありませんでした。
相手はBBCラジオのアナウンサーのジョージでした。
ここで注目!
ロザマンドは初めてのセックスで子を宿したのね。
しかも、セックスの後の彼の態度で自分は嫌われたと思ってしまい
次の約束もできず、会いにも行けなくなります。
月日は流れ妊娠…
詩の研究家のロザマンドは、仕事は安定していないし、論文を書く時間が必要です。
子供が特に好きなわけでもありません。
というわけで、なんの躊躇もせず(堕ろすために)産婦人科を訪ねて行くのですが
そこで「産んで当たり前」という態度で接する医者に会い
疲れきった様子の待合室の妊婦たちを目にして、いきなり生む決心をします。
友人たち、個人教授をしている生徒たちには相手がわかるまで黙っていました。
両親や兄には言いませんでした。
子供の父親であるジョージにも伝えませんでした。
ロザマンドの妊娠を知った人たちの反応は様々でした。
きっと助けてくれると信じていた姉ベアトリスの猛反対にはショックを受けました。
いろいろあるんだけど端折ってくね。
ロザマンドはオクテイヴィアという娘を生み、深い愛を注ぐようになります。
「子供がこんなに愛おしい存在だったなんて!」と感動に浸るのも束の間
オクテイヴィアが重い病であることがわかり、難しい手術をすることになります。
全編通してロザマンドは自分の言いたいことを飲み込んでしまう
“ 忍耐の人 ” という印象なのですが、入院した子供に会うために
看護婦長と戦う時には自分を爆発させます。
我が子を思う母親の強さとはこういうものなのかと思わされました。
ロザマンドのジョージへの愛は変わらないのですが
相手には何も告げることなく娘と二人の生活を続けます。
二人は近くにいるにもかかわらず再会すること無く時が過ぎて行きますが
ある夜とうとう再会します。
しばらく会話を交わした後、ロザマンドはジョージを自宅に誘いました。
この物語のラストへの印象は、読む人の結婚観とか結婚経験で二つにわかれそう…
私としては “ 一般的な ” ハッピーエンドに終わってほしかったのですが
作者の意図は違っていたようです。
読んでいる最中、平凡な私は、早く相手に打ち明けて責任をとらせればいいじゃんよ~!
あるいは、友人の誰かに打ち明けたことから相手の耳に入り…なんて韓流的流れを期待しつつ
ちょっとイライラしながら読んでいました。
でも読後は、何も語らず、全てを自分で決めて、自分一人で引き受けようとする女性の姿に
羨ましさを覚えました。
“ 凛としている ” というのは、こういうことを言うんじゃないかしら?



1965年 マーガレット・ドラブル
この本は自由が丘にある古本屋さんで買いました。
その古本屋さんには百円コーナーがあって、とんでもない掘り出し物があるの。
百円だったので手を出してみた一冊で、特に期待はしていませんでした。
出だしが若者都会派小説みたいに思えたので「あちゃ~」と後悔しつつ読み始めたのですが
読んでいたらだんだん面白くなってきて、すぐに読み終えてしまいました。
アフリカに赴任中の両親が残していってくれた高級住宅街のフラットで暮らしている
ロザマンドは、ある日妊娠したことに気がつきました。
ロザマンドは作家のジョーと計理士のロージャーと遊び歩いていましたが
思わせぶりに接するだけで、深い関係ではありませんでした。
相手はBBCラジオのアナウンサーのジョージでした。
ここで注目!
ロザマンドは初めてのセックスで子を宿したのね。
しかも、セックスの後の彼の態度で自分は嫌われたと思ってしまい
次の約束もできず、会いにも行けなくなります。
月日は流れ妊娠…
詩の研究家のロザマンドは、仕事は安定していないし、論文を書く時間が必要です。
子供が特に好きなわけでもありません。
というわけで、なんの躊躇もせず(堕ろすために)産婦人科を訪ねて行くのですが
そこで「産んで当たり前」という態度で接する医者に会い
疲れきった様子の待合室の妊婦たちを目にして、いきなり生む決心をします。
友人たち、個人教授をしている生徒たちには相手がわかるまで黙っていました。
両親や兄には言いませんでした。
子供の父親であるジョージにも伝えませんでした。
ロザマンドの妊娠を知った人たちの反応は様々でした。
きっと助けてくれると信じていた姉ベアトリスの猛反対にはショックを受けました。
いろいろあるんだけど端折ってくね。
ロザマンドはオクテイヴィアという娘を生み、深い愛を注ぐようになります。
「子供がこんなに愛おしい存在だったなんて!」と感動に浸るのも束の間
オクテイヴィアが重い病であることがわかり、難しい手術をすることになります。
全編通してロザマンドは自分の言いたいことを飲み込んでしまう
“ 忍耐の人 ” という印象なのですが、入院した子供に会うために
看護婦長と戦う時には自分を爆発させます。
我が子を思う母親の強さとはこういうものなのかと思わされました。
ロザマンドのジョージへの愛は変わらないのですが
相手には何も告げることなく娘と二人の生活を続けます。
二人は近くにいるにもかかわらず再会すること無く時が過ぎて行きますが
ある夜とうとう再会します。
しばらく会話を交わした後、ロザマンドはジョージを自宅に誘いました。
この物語のラストへの印象は、読む人の結婚観とか結婚経験で二つにわかれそう…
私としては “ 一般的な ” ハッピーエンドに終わってほしかったのですが
作者の意図は違っていたようです。
読んでいる最中、平凡な私は、早く相手に打ち明けて責任をとらせればいいじゃんよ~!
あるいは、友人の誰かに打ち明けたことから相手の耳に入り…なんて韓流的流れを期待しつつ
ちょっとイライラしながら読んでいました。
でも読後は、何も語らず、全てを自分で決めて、自分一人で引き受けようとする女性の姿に
羨ましさを覚えました。
“ 凛としている ” というのは、こういうことを言うんじゃないかしら?











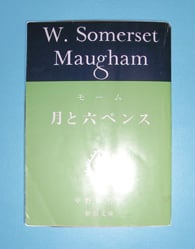

 本当のゴーギャンがどうだったのかはまったく知りません)
本当のゴーギャンがどうだったのかはまったく知りません)










 すごくおもしろかったです。
すごくおもしろかったです。






