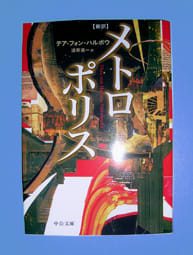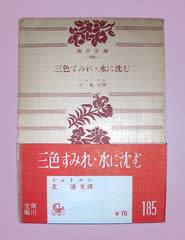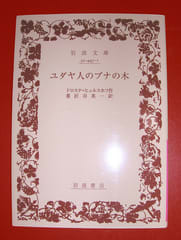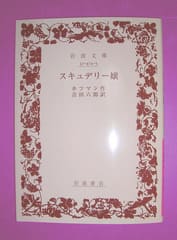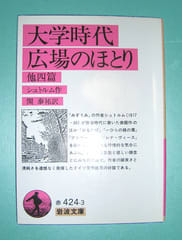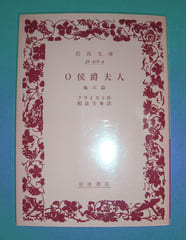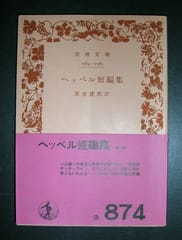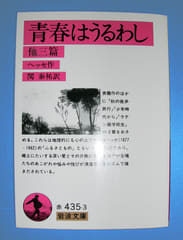DIE NACHT,DIE LICHTER 
2008年 クレメンス・マイヤー
本屋さんに行くと必ずチェックする新潮クレストのコーナーで
作家が旧東ドイツ出身という一点のみに興味を抱いて買った一冊です。
く、暗い… 私は暗い話しはキライじゃないけど、この本にはドーンと滅入ったね。
旧東ドイツ出身というところから、統一後のドイツの高経済についていけない、あるいは
民主主義そのものについていけない人々の悲哀を描いたものだという先入観があって
そういう観点から読んでいましたが、どうやらそれはあまり関係ないみたいです。
薬物中毒者・犯罪者・受刑者・無職・手当受給者などなど、負け組、かつて負け組、
負け組予備軍という人たちが主人公の12篇がおさめられていますが
舞台は別にドイツでなくても、どこにでもあてはまる物語でした。
暗いながらも印象に残った物語をいくつかあげてみます。
『南米を待つ(Wartan auf Sudamerika)』
電気を止められた母の家を出て自分の家に戻ると、一通の手紙が来ていた。
消印はキューバで、古い友人ヴォルフガングからのものだった。
彼は、昔家を出て行った父の遺産を手に入れて、ブラジルを目指して旅しているという。
男の友情ってこういうものなんですかね?
自分はどん底の手当生活なのに、ぜいたくな旅行の様子が書かれた手紙を読んで
友人の幸せを祝ってあげられるとは…
女はどうしても他の女性の幸せを手放しで祝ってあげることってできないからね…でしょ?
『通路にて(In den Gangen)』
大型スーパーの商品整理係の夜勤になって職場にもだいぶ慣れてきた。
菓子類担当の可愛いマリオンは人妻だが夫に問題があるらしい。
フォークリフトを教えてくれたブルーノは郊外で農場をやっていて、皆に慕われていた。
夜のスーパーに職を得た人たちの、そっけないけれど親しみのある付合いが描かれていて
暗い本の中にあって少し望みが持てる物語だと思っていたら…がーーーん
なぜなのぉ? なんの解決もみないまま終わってしまられては…
『君の髪はきれいだ(Du Hast Schones Haar)』
彼は研修にやってきた来た日に娼婦の少女ズィスィと出会い、妻と貯めた金を全額引出した。
その日以来、ズィスィに会いに行くことと、今後彼女と暮らすことしか考えられない。
彼は毎日リトアニア語が話せる男を探す。ズィスィに「君の髪はきれいだ」と言うために…
バカじゃなかろーか! それとも男のロマン?
クラブとかスナックに行って、愛想よくしてくれる女性に本気になっちゃう人がいるけど
本気なわけないじゃないよ~! 粋に遊びましょうよ。
この主人公は遊び慣れてなかったのね、きっと。 だから最後そうなっちゃうでしょうが…
私はさっき舞台はどこでもいいって書きました。
だけど、もしかしてこの独特感は旧東ドイツ出身の作者ならではなのかしら?
たとえば同じような話しをニューヨークの作家が書いたとするとかなり違っていたかも。
古くから競争主義と快楽の情報を知りつくしていた国の作家なら、それらを反映して
もう少しライトでユーモアが感じられる書き方をしていたかもしれません。
登場人物の会話に哀しげなジョークが織り交ぜられたりして
気の抜きどころがあったかもしれないですね。
新たにやってきた主義と情報を使いこなせないまま生きている人々を
正直に描写しようとするとこういう風に仕上がるのかもしれないですね。
勝手に言ってますけど…
なにしろ笑いどころゼロ! クスッとも笑えない生真面目さで書かれてます。
哀しい物語を書くならちゃんと哀しく書きましょう、という感じで
こちらも固い椅子に座って、心して読まねば… という気になりそうでした。
場面や時間が小刻みに行ったり来たり、急に変わったりするので
少し読みづらいところもありました。
内容は嫌いではないのですが、慣れないと楽しんで読むことはできないかな?
慣れるようにあと何冊か読んでみようとは、今は思えないですけど…
ただ、統一がなければ優秀な作家の作品が東ドイツ内だけの需要で終わり
しかも、国が認めた物だけしか書けないという悲劇に見舞われていたわけですよね。
作家たちが自分の書きたいことが書けて、世界で活躍できるということだけ考えても
統一は大きな意義があったのだと言えるのではないでしょうか?
優しすぎる男性の悲哀がにじみでてます
読んでみたいな!という方は下の画像をクリックしてね


 ひとことK-POPコーナー
ひとことK-POPコーナー
今年はSMTOWNに2日とも行けて浮かれていたのですが、EXOに続いてSUPER JUNIORのニュースに驚いたさ!
カワイコちゃんソンミンが誰よりも早く結婚とは!! 気が早いけどパパドル・ソンミンも見てみたいような…

2008年 クレメンス・マイヤー
本屋さんに行くと必ずチェックする新潮クレストのコーナーで
作家が旧東ドイツ出身という一点のみに興味を抱いて買った一冊です。
く、暗い… 私は暗い話しはキライじゃないけど、この本にはドーンと滅入ったね。
旧東ドイツ出身というところから、統一後のドイツの高経済についていけない、あるいは
民主主義そのものについていけない人々の悲哀を描いたものだという先入観があって
そういう観点から読んでいましたが、どうやらそれはあまり関係ないみたいです。
薬物中毒者・犯罪者・受刑者・無職・手当受給者などなど、負け組、かつて負け組、
負け組予備軍という人たちが主人公の12篇がおさめられていますが
舞台は別にドイツでなくても、どこにでもあてはまる物語でした。
暗いながらも印象に残った物語をいくつかあげてみます。
『南米を待つ(Wartan auf Sudamerika)』

電気を止められた母の家を出て自分の家に戻ると、一通の手紙が来ていた。
消印はキューバで、古い友人ヴォルフガングからのものだった。
彼は、昔家を出て行った父の遺産を手に入れて、ブラジルを目指して旅しているという。
男の友情ってこういうものなんですかね?
自分はどん底の手当生活なのに、ぜいたくな旅行の様子が書かれた手紙を読んで
友人の幸せを祝ってあげられるとは…
女はどうしても他の女性の幸せを手放しで祝ってあげることってできないからね…でしょ?
『通路にて(In den Gangen)』

大型スーパーの商品整理係の夜勤になって職場にもだいぶ慣れてきた。
菓子類担当の可愛いマリオンは人妻だが夫に問題があるらしい。
フォークリフトを教えてくれたブルーノは郊外で農場をやっていて、皆に慕われていた。
夜のスーパーに職を得た人たちの、そっけないけれど親しみのある付合いが描かれていて
暗い本の中にあって少し望みが持てる物語だと思っていたら…がーーーん
なぜなのぉ? なんの解決もみないまま終わってしまられては…
『君の髪はきれいだ(Du Hast Schones Haar)』

彼は研修にやってきた来た日に娼婦の少女ズィスィと出会い、妻と貯めた金を全額引出した。
その日以来、ズィスィに会いに行くことと、今後彼女と暮らすことしか考えられない。
彼は毎日リトアニア語が話せる男を探す。ズィスィに「君の髪はきれいだ」と言うために…
バカじゃなかろーか! それとも男のロマン?
クラブとかスナックに行って、愛想よくしてくれる女性に本気になっちゃう人がいるけど
本気なわけないじゃないよ~! 粋に遊びましょうよ。
この主人公は遊び慣れてなかったのね、きっと。 だから最後そうなっちゃうでしょうが…
私はさっき舞台はどこでもいいって書きました。
だけど、もしかしてこの独特感は旧東ドイツ出身の作者ならではなのかしら?
たとえば同じような話しをニューヨークの作家が書いたとするとかなり違っていたかも。
古くから競争主義と快楽の情報を知りつくしていた国の作家なら、それらを反映して
もう少しライトでユーモアが感じられる書き方をしていたかもしれません。
登場人物の会話に哀しげなジョークが織り交ぜられたりして
気の抜きどころがあったかもしれないですね。
新たにやってきた主義と情報を使いこなせないまま生きている人々を
正直に描写しようとするとこういう風に仕上がるのかもしれないですね。
勝手に言ってますけど…
なにしろ笑いどころゼロ! クスッとも笑えない生真面目さで書かれてます。
哀しい物語を書くならちゃんと哀しく書きましょう、という感じで
こちらも固い椅子に座って、心して読まねば… という気になりそうでした。
場面や時間が小刻みに行ったり来たり、急に変わったりするので
少し読みづらいところもありました。
内容は嫌いではないのですが、慣れないと楽しんで読むことはできないかな?
慣れるようにあと何冊か読んでみようとは、今は思えないですけど…
ただ、統一がなければ優秀な作家の作品が東ドイツ内だけの需要で終わり
しかも、国が認めた物だけしか書けないという悲劇に見舞われていたわけですよね。
作家たちが自分の書きたいことが書けて、世界で活躍できるということだけ考えても
統一は大きな意義があったのだと言えるのではないでしょうか?
優しすぎる男性の悲哀がにじみでてます
読んでみたいな!という方は下の画像をクリックしてね

 ひとことK-POPコーナー
ひとことK-POPコーナー今年はSMTOWNに2日とも行けて浮かれていたのですが、EXOに続いてSUPER JUNIORのニュースに驚いたさ!
カワイコちゃんソンミンが誰よりも早く結婚とは!! 気が早いけどパパドル・ソンミンも見てみたいような…










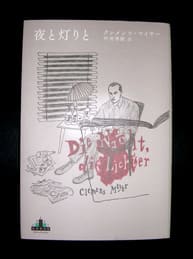





 とお怒りの方もいらっしゃいましょうが
とお怒りの方もいらっしゃいましょうが