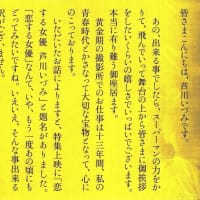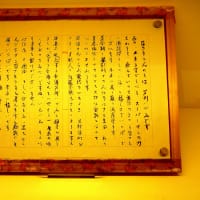見田宗介(真木悠介)さんの著作集を読んできて、残りは真木悠介名義の2冊になった。もう一気に終わらせてしまおうと思って、図書館から2冊を借りてきた。見田宗介著作集(全10巻)は全巻買ったのだが、真木悠介著作集(全4巻)は買わなかった。原著を全部持っていたからだ。それでも図書館から借りるのは、増補や「定本解題」を確認するためである。本来、次は第3巻の『自我の起源』だけど、第4巻を先に読んだ。この巻は短くて読みやすそうだったから。実際すぐ読めて、見田(真木)さんのエッセイストとしての魅力が溢れている。旅心を誘われるし、最初に読むべき本かもしれない。
 (原著表表紙)
(原著表表紙)
著作集では『南端まで』という題名になっているが、これは1994年6月に出た『旅のノートから』(岩波書店)という本の増補版である。「ノート」というだけあって、横書きの本になっている。原著から「汽車とバス」という文章が削除され、原著以後に書かれた5つのエッセイが増補されている。題名の『南端まで』には特に意味はないという。自分の旅は大体「南」へ向かっているからという程度だという。インドの南端には行ってるけど、後はメキシコやブラジル、ボリビアなどが多い。まあ「南北問題」というときの「南」でもあるんだろう。主にインド、ラテンアメリカの旅の記録である。
 (コモリン岬の子どもたち)
(コモリン岬の子どもたち)
上記写真は原書カバーにも使われているが、インド最南端のコモリン岬(タミル・ナド州)で撮られたものである。そこを夜に訪れた時、子どもたちが大きな声で行くなと叫んでいた。著者は多分そこが聖地であり、外部の者は立ち入るなという意味かと受け取ったのだが…。著作集冒頭に収録されている「コモリン岬」は、その時に撮影した写真の意味は何だったのか、2006年になって改めて書かれた文章だ。非常に優れた短編小説の趣があるエッセイ。この巻の文章は読みやすく含蓄が深いものが多いけど、特にこの「コモリン岬」は忘れがたい。(中身にはここでは触れないことにする。)
 (原著裏表紙)
(原著裏表紙)
題名を見ても判るとおり、大体の文章は旅行エッセイなんだけど、それ以外のものも入っている。「伝言」「光の降る森」は屋久島に住んでいた山尾三省をめぐるエッセイで、見田宗介著作集第10巻『晴風万里』と重なる。屋久島まで行ってるから旅でもあるが、山尾三省に触れながら考えたことの記録でもある。山尾三省という存在は著者にとって、非常に大きなものだった。早くからコミューン運動に関心を持っていた著者にとって、山尾三省は特に大きな意味を持っていたことが判る。
「狂気としての近代」は「時間の比較社会学・序」と題されていて、その名の通りの文ではあるが、メキシコの話がいっぱい書かれている。メキシコについては、「メキシコの社会と文化」「メキシコの生と形式」という旅エッセイを越えた本格的評論も入っている。それは1974年から75年にかけて、著者が「エル・コレヒオ・デ・メヒコ」という大学院大学に招かれて教えていたからだ。ここは70年代には毎年日本から教授を招いていて、鶴見俊輔や大江健三郎などもそれでメキシコに滞在したのである。そこがどんなところで、どういう意味を持っていたか、よく理解出来る文章である。
 (当時の著者)
(当時の著者)
また「夢4巻」という不思議な文章もある。自分が見た夢という体裁で、4つの話が出ている。あまりに具体的で詳細であり、これが本当の夢の記録とは思えないが、ちょっとどういう意味を持っているのか僕には判断出来ない。興味深かったのが「コーラムの謎」。コーラムとは、インドの家庭の前に白い粉で書かれた模様である。インドに行ったことがなく、初めて聞いた言葉だった。画像検索してみると、いろんな模様が出て来る。何でそのようなものを書くのか、インド人にも諸説あると書いてある。僕には判らないけど、模様を見てると何か凄いなと思う。
全体を通して、近代化された日本人の感覚では測りがたいインドやメキシコの社会を旅することで、「近代化された身体」を相対化してゆく文章が多い。『気流の鳴る音』ではインディオの教えを分析するという形で、『時間の比較社会学』では世界に存在した各文明の学問的分析という形で行ったことを、旅エッセイという形式で書いたものである。「補巻」としても良かったと言っているが、構成をシンプルにするため止めたという。しかし、内容的にはエピローグだと書いている。僕はむしろ見田宗介著作集を含めて、全体のプロローグとしても読めると思う。この巻を読んで共感出来なかった人は、他を読んでも理解不能だろう。
なお、原著は「シリーズ旅の本箱」という全15冊の一冊だった。全く記憶していなかったけど、そういうシリーズがあったのである。他には加藤周一『幻想薔薇都市』、亀井俊介『アメリカの歌声が聞こえる』、小田実『NYーベルリン 生と死』、養老孟司『昆虫紀行』、沼野充義『モスクワーペテルブルク縦横記』、池内紀『今は山なか今は浜』など、なかなか興味深そうなラインナップが並んでいるが、全く記憶にない本ばかり。
 (原著表表紙)
(原著表表紙)著作集では『南端まで』という題名になっているが、これは1994年6月に出た『旅のノートから』(岩波書店)という本の増補版である。「ノート」というだけあって、横書きの本になっている。原著から「汽車とバス」という文章が削除され、原著以後に書かれた5つのエッセイが増補されている。題名の『南端まで』には特に意味はないという。自分の旅は大体「南」へ向かっているからという程度だという。インドの南端には行ってるけど、後はメキシコやブラジル、ボリビアなどが多い。まあ「南北問題」というときの「南」でもあるんだろう。主にインド、ラテンアメリカの旅の記録である。
 (コモリン岬の子どもたち)
(コモリン岬の子どもたち)上記写真は原書カバーにも使われているが、インド最南端のコモリン岬(タミル・ナド州)で撮られたものである。そこを夜に訪れた時、子どもたちが大きな声で行くなと叫んでいた。著者は多分そこが聖地であり、外部の者は立ち入るなという意味かと受け取ったのだが…。著作集冒頭に収録されている「コモリン岬」は、その時に撮影した写真の意味は何だったのか、2006年になって改めて書かれた文章だ。非常に優れた短編小説の趣があるエッセイ。この巻の文章は読みやすく含蓄が深いものが多いけど、特にこの「コモリン岬」は忘れがたい。(中身にはここでは触れないことにする。)
 (原著裏表紙)
(原著裏表紙)題名を見ても判るとおり、大体の文章は旅行エッセイなんだけど、それ以外のものも入っている。「伝言」「光の降る森」は屋久島に住んでいた山尾三省をめぐるエッセイで、見田宗介著作集第10巻『晴風万里』と重なる。屋久島まで行ってるから旅でもあるが、山尾三省に触れながら考えたことの記録でもある。山尾三省という存在は著者にとって、非常に大きなものだった。早くからコミューン運動に関心を持っていた著者にとって、山尾三省は特に大きな意味を持っていたことが判る。
「狂気としての近代」は「時間の比較社会学・序」と題されていて、その名の通りの文ではあるが、メキシコの話がいっぱい書かれている。メキシコについては、「メキシコの社会と文化」「メキシコの生と形式」という旅エッセイを越えた本格的評論も入っている。それは1974年から75年にかけて、著者が「エル・コレヒオ・デ・メヒコ」という大学院大学に招かれて教えていたからだ。ここは70年代には毎年日本から教授を招いていて、鶴見俊輔や大江健三郎などもそれでメキシコに滞在したのである。そこがどんなところで、どういう意味を持っていたか、よく理解出来る文章である。
 (当時の著者)
(当時の著者)また「夢4巻」という不思議な文章もある。自分が見た夢という体裁で、4つの話が出ている。あまりに具体的で詳細であり、これが本当の夢の記録とは思えないが、ちょっとどういう意味を持っているのか僕には判断出来ない。興味深かったのが「コーラムの謎」。コーラムとは、インドの家庭の前に白い粉で書かれた模様である。インドに行ったことがなく、初めて聞いた言葉だった。画像検索してみると、いろんな模様が出て来る。何でそのようなものを書くのか、インド人にも諸説あると書いてある。僕には判らないけど、模様を見てると何か凄いなと思う。
全体を通して、近代化された日本人の感覚では測りがたいインドやメキシコの社会を旅することで、「近代化された身体」を相対化してゆく文章が多い。『気流の鳴る音』ではインディオの教えを分析するという形で、『時間の比較社会学』では世界に存在した各文明の学問的分析という形で行ったことを、旅エッセイという形式で書いたものである。「補巻」としても良かったと言っているが、構成をシンプルにするため止めたという。しかし、内容的にはエピローグだと書いている。僕はむしろ見田宗介著作集を含めて、全体のプロローグとしても読めると思う。この巻を読んで共感出来なかった人は、他を読んでも理解不能だろう。
なお、原著は「シリーズ旅の本箱」という全15冊の一冊だった。全く記憶していなかったけど、そういうシリーズがあったのである。他には加藤周一『幻想薔薇都市』、亀井俊介『アメリカの歌声が聞こえる』、小田実『NYーベルリン 生と死』、養老孟司『昆虫紀行』、沼野充義『モスクワーペテルブルク縦横記』、池内紀『今は山なか今は浜』など、なかなか興味深そうなラインナップが並んでいるが、全く記憶にない本ばかり。