藤岡陽子「手のひらの音符」(新潮文庫)という本が新聞に紹介されていて、面白そうだった。最初の方は服飾業界の話から、京都の子ども時代の話へ移り、なんだか舞台が身近じゃない感じがする。でも読んでるうちに登場人物たちの構図が判ってくると一気読み。なるほど評判になるだけある。これは今を生きている人に送られた、とても大切なバトンのような本だ。受け取ったバトンを次の人に渡したくなるから、ここで簡単に紹介しておくことにする。

瀬尾水樹はもう40代半ばの服装デザイナーで、「服のマクドナルド」をめざした会社を退社し、自分なりに納得できる服作りを続けてきた。それなりに評価されてきたんだけど、会社が服部門から撤退することを決めてしまう。そんなときに高校時代の男子学級委員、堂林憲吾から携帯電話がかかってくる。高校時代の担任の先生、上田遠子先生が重病で入院しているという。家が貧しく、高卒で就職することしか考えていなかった水樹に、進学を勧めたのが先生だった。もう内定も出ていたのに、三者面談で進学を母に勧め、そのことで今の人生があるのである。
子ども時代の水樹は京都郊外の団地で暮らしていた。近くに住む森嶋家の子どもたちとは幼なじみで、兄の徹、森嶋家の三兄弟と祭りに行ったりするのが楽しみだった。一番上の正浩、同い年の信也、そして発達障害でいじめられている悠人。だが森嶋家に悲劇が訪れ、同級生の森嶋信也は心を閉ざしてしまう。高校も一緒だった信也は忘れがたい人だったが、東京の学校に受かった水樹の上京前日に会ったまま、ある日ふっつりと一家ごと消えてしまった。以後一回も会ったことがない。大切に思ってくれる人もいたけど、結局水樹は独身のままだった。
といろいろ書いても、大事なことは伝わらない気がする。時間と空間を行ったり来たりしながら、水樹の人生を通して読者はずいぶんたくさんのことを感じることになる。「日本のものづくりのありかた」なんかもその一つ。「教員という人生」もある。「親の生き方」も出てくる。水樹の母と森嶋家の母の生き方は違ってくるが、どっちがいいとは言えない。水樹は家が貧しいから、金銭的苦労を掛けたくなくて進学は諦めていた。だけど先生から進学を勧められた母はむしろ喜んだ。自分の子に才能を見出してくれて、そんな子どもにお金を出せるのが親の喜びだったのだ。
やはり「いじめ」も出てくる。悠人へのいじめと水樹自身へのいじめ。その時の森嶋信也の行動。「リレー」を通して語られる「全力で生きること」の大切さ。そう言えば、幼い彼らは周囲になじまない悠人に対して、「ドは努力のド、レは練習のレ、ミは水樹のミ」とうたっていたのだった。この小説が特に重要なのは、「ヤング・ケアラー」の問題を取り上げていることだ。悠人を抱えて生きていく信也だけでなく、実は堂林も壮絶なケアラーとして生きていたのだ。信也、堂林、遠子先生をつなぐものがあったのである。それにしても消えてしまった信也はどこに?
 (藤岡陽子)
(藤岡陽子)
藤岡陽子(1971~)という人は、同志社大学を出て報知新聞のスポーツ記者になり、その後タンザニアのダルエスサラーム大学に留学。帰国後に看護専門学校を出て看護師になった。ここだけでも相当珍しい経歴だが、その後看護やスポーツに関わる小説を書き始めた。デビュー作の「いつまでも白い羽根」(2009)はドラマにもなった。「手のひらの音符」は2014年の本で、2016年に文庫化されていたが、最近になって話題を呼んでいる。題名がいま一つ内容とミスマッチな感じで、これじゃ音楽の話かなと思ってしまう。ラストの忘れがたい感動はぜひ多くの人に読んで欲しい。

瀬尾水樹はもう40代半ばの服装デザイナーで、「服のマクドナルド」をめざした会社を退社し、自分なりに納得できる服作りを続けてきた。それなりに評価されてきたんだけど、会社が服部門から撤退することを決めてしまう。そんなときに高校時代の男子学級委員、堂林憲吾から携帯電話がかかってくる。高校時代の担任の先生、上田遠子先生が重病で入院しているという。家が貧しく、高卒で就職することしか考えていなかった水樹に、進学を勧めたのが先生だった。もう内定も出ていたのに、三者面談で進学を母に勧め、そのことで今の人生があるのである。
子ども時代の水樹は京都郊外の団地で暮らしていた。近くに住む森嶋家の子どもたちとは幼なじみで、兄の徹、森嶋家の三兄弟と祭りに行ったりするのが楽しみだった。一番上の正浩、同い年の信也、そして発達障害でいじめられている悠人。だが森嶋家に悲劇が訪れ、同級生の森嶋信也は心を閉ざしてしまう。高校も一緒だった信也は忘れがたい人だったが、東京の学校に受かった水樹の上京前日に会ったまま、ある日ふっつりと一家ごと消えてしまった。以後一回も会ったことがない。大切に思ってくれる人もいたけど、結局水樹は独身のままだった。
といろいろ書いても、大事なことは伝わらない気がする。時間と空間を行ったり来たりしながら、水樹の人生を通して読者はずいぶんたくさんのことを感じることになる。「日本のものづくりのありかた」なんかもその一つ。「教員という人生」もある。「親の生き方」も出てくる。水樹の母と森嶋家の母の生き方は違ってくるが、どっちがいいとは言えない。水樹は家が貧しいから、金銭的苦労を掛けたくなくて進学は諦めていた。だけど先生から進学を勧められた母はむしろ喜んだ。自分の子に才能を見出してくれて、そんな子どもにお金を出せるのが親の喜びだったのだ。
やはり「いじめ」も出てくる。悠人へのいじめと水樹自身へのいじめ。その時の森嶋信也の行動。「リレー」を通して語られる「全力で生きること」の大切さ。そう言えば、幼い彼らは周囲になじまない悠人に対して、「ドは努力のド、レは練習のレ、ミは水樹のミ」とうたっていたのだった。この小説が特に重要なのは、「ヤング・ケアラー」の問題を取り上げていることだ。悠人を抱えて生きていく信也だけでなく、実は堂林も壮絶なケアラーとして生きていたのだ。信也、堂林、遠子先生をつなぐものがあったのである。それにしても消えてしまった信也はどこに?
 (藤岡陽子)
(藤岡陽子)藤岡陽子(1971~)という人は、同志社大学を出て報知新聞のスポーツ記者になり、その後タンザニアのダルエスサラーム大学に留学。帰国後に看護専門学校を出て看護師になった。ここだけでも相当珍しい経歴だが、その後看護やスポーツに関わる小説を書き始めた。デビュー作の「いつまでも白い羽根」(2009)はドラマにもなった。「手のひらの音符」は2014年の本で、2016年に文庫化されていたが、最近になって話題を呼んでいる。題名がいま一つ内容とミスマッチな感じで、これじゃ音楽の話かなと思ってしまう。ラストの忘れがたい感動はぜひ多くの人に読んで欲しい。










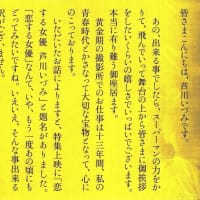
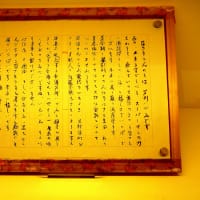








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます