林芙美子を読むシリーズ4回目。その後に文庫に入っている『林芙美子随筆集』(岩波文庫)、『トランク 林芙美子大陸小説集』(中公文庫)を読んで、最後に『放浪記』を読み直してみた。まあ人生に2回読んでも良い本かなと思って、昔読んだ新潮文庫を見つけ出してきた。ところが字が小さくて、今じゃ読み辛いのである。しょうが無いから他の本を探すことにして、本屋で実物を見たら岩波文庫なら何とか読めそうだったので、買い直してしまった。解説が充実していて買った意味はあった。

しかし、これが思った以上に大変なシロモノだった。前に読んだときもそう思ったけど、今回も底なし沼にハマったかと思った。今は戦後になって発表された第三部を含めた三部作の「完全版」が出ている。ところがこれが改訂に改訂を重ねた「魔改造日記」(by柚木麻子)なのである。解説に出ている一番最初の原『放浪記』は確かに「若書き」であり、まだ作家以前の文章とも言える。成熟した作家となり、文章を練り直したいというのは理解出来る。また戦前には検閲を考慮して削除されていた記述もあった。(皇族関係など。)それを復活させたいのも判る。だが問題は『放浪記』の根本的な構成にあるのである。
 (舞台版『放浪記』の森光子)
(舞台版『放浪記』の森光子)
『放浪記』は映画や舞台となって、むしろそっちで知られた。名前も知られているから読んでみた人も多いだろうが、「完全版」だと途中で挫折した人もかなりいるんじゃないだろうか。普通は「三部作」というと、それは時系列で進む物語である。まあ、実際の日記をもとにしているので、物語性に乏しいのはやむを得ない。それは良いとして、実は日記の時系列をバラバラにして、複雑なピースにして並べているのが『放浪記』第一部なのである。映画や舞台で有名なカフェで働く場面も確かにあるが、実は女工や女中、女給、事務、宛名書き、露天商、行商など実にいろいろな仕事をしている。
時系列をバラして、人名も匿名にしているのは、当時は関係者が皆生きていたからだろう。母親や作家仲間の平林たい子、壺井栄などを除き、関係があった男性は皆誰だかよく判らない。戦後になってまとめられた第三部では、かなり実名に戻している。それが逆効果なのである。「無名の貧しい女性」の魂の叫びをぶつけた実録日記として売れたのに、一番大切な自然な思いを作者はあえて消してしまった。そして、時系列バラバラの構成は、第一部、第二部、第三部すべて同一なのである。つまり、第二部が第一部を受けた内容というわけではなく、すべて同じ時期、東京へ出て来てから結婚して落ち着くまでの数年間なのである。
 (映画『放浪記』の高峰秀子)
(映画『放浪記』の高峰秀子)
貧乏に苦しみ、仕事については辞め、文学を志す男と知り合って同棲しては壊れ、それでも文学に心惹かれて詩を書き続ける。貴重なドキュメントで、今まで一度も書かれなかった貧困階級の真実である。だが日記は飛び飛びで、数ヶ月するとまた違う仕事をしている。いつの間にか付き合う男も変わっている。もちろん、そのことが悪いわけじゃない。だけど、そのような貧乏→新しい仕事→新しい男→また辞めて放浪→新しい仕事→新しい男→貧乏のループが第一部、第二部、第三部とすべて同じように繰り返されるのである。この「無限ループ」から読者も抜け出せないのだ。
何しろ文庫本でも545ページもあるので、この無限ループを読み進めるのが苦しくなってくる。バカバカしい気もしてくる。ところどころに挿入される詩も、最初は新鮮だが次第に飽きてくる。それが『放浪記』なんだけど、第一部発売当時に大ベストセラーになった。その当時は無名女性の日記なので(一部では新人作家として知られてきていたが)、どっちかと言えば「カフェ女給が書いた」というスキャンダラスな本として売れたんじゃないか。
しかし、林芙美子は天性の放浪者であると同時に、天性の詩人だった。自分は美人じゃなく、もっと美しかったら仕事も恵まれていたとよく書いている。仕事としては確かに今以上にルッキズムがはびこっていただろう。だけど、文学志向、芸術志向の青年たちと続々と恋愛しているのは、どこか只者では無い雰囲気があったんだと思う。だがその文学志向が「良妻」になることを妨げ、中には暴力を振るったりする男もいる。仕事を投げ出して詩を書いていても、トコトン貧乏になっていくだけ。さらに母や義父が飛び込んできたりする。貧窮の中でも「文学」に取り憑かれてしまったのが林芙美子という女性だった。


林芙美子の実人生に関しては、ここでは書かないことにする。前にも書いたが、尾道の女学校の教師がよくぞ才能を見出して励ましたものである。貧窮の中で魂の叫びを発したが、それは「プロレタリア文学」ではない。プロレタリア陣営からは批判されたりもしたが、今でも読まれているのは林芙美子の方である。林芙美子が本格的な作家になったことをよく示すのが、『トランク』という作品集である。中国、フランス、ソ連についての小説が収録されている。戦時中の文章には戦争協力の跡があって痛ましいが、豊かな物語性が今も生きている作品が多い。『林芙美子随筆集』も面白いが、どうも随筆や旅行記だからと言って必ずしも「事実そのまま」ではない場合もあるらしい。これで林芙美子は終わりだが、関連本がまだ残っている。

しかし、これが思った以上に大変なシロモノだった。前に読んだときもそう思ったけど、今回も底なし沼にハマったかと思った。今は戦後になって発表された第三部を含めた三部作の「完全版」が出ている。ところがこれが改訂に改訂を重ねた「魔改造日記」(by柚木麻子)なのである。解説に出ている一番最初の原『放浪記』は確かに「若書き」であり、まだ作家以前の文章とも言える。成熟した作家となり、文章を練り直したいというのは理解出来る。また戦前には検閲を考慮して削除されていた記述もあった。(皇族関係など。)それを復活させたいのも判る。だが問題は『放浪記』の根本的な構成にあるのである。
 (舞台版『放浪記』の森光子)
(舞台版『放浪記』の森光子)『放浪記』は映画や舞台となって、むしろそっちで知られた。名前も知られているから読んでみた人も多いだろうが、「完全版」だと途中で挫折した人もかなりいるんじゃないだろうか。普通は「三部作」というと、それは時系列で進む物語である。まあ、実際の日記をもとにしているので、物語性に乏しいのはやむを得ない。それは良いとして、実は日記の時系列をバラバラにして、複雑なピースにして並べているのが『放浪記』第一部なのである。映画や舞台で有名なカフェで働く場面も確かにあるが、実は女工や女中、女給、事務、宛名書き、露天商、行商など実にいろいろな仕事をしている。
時系列をバラして、人名も匿名にしているのは、当時は関係者が皆生きていたからだろう。母親や作家仲間の平林たい子、壺井栄などを除き、関係があった男性は皆誰だかよく判らない。戦後になってまとめられた第三部では、かなり実名に戻している。それが逆効果なのである。「無名の貧しい女性」の魂の叫びをぶつけた実録日記として売れたのに、一番大切な自然な思いを作者はあえて消してしまった。そして、時系列バラバラの構成は、第一部、第二部、第三部すべて同一なのである。つまり、第二部が第一部を受けた内容というわけではなく、すべて同じ時期、東京へ出て来てから結婚して落ち着くまでの数年間なのである。
 (映画『放浪記』の高峰秀子)
(映画『放浪記』の高峰秀子)貧乏に苦しみ、仕事については辞め、文学を志す男と知り合って同棲しては壊れ、それでも文学に心惹かれて詩を書き続ける。貴重なドキュメントで、今まで一度も書かれなかった貧困階級の真実である。だが日記は飛び飛びで、数ヶ月するとまた違う仕事をしている。いつの間にか付き合う男も変わっている。もちろん、そのことが悪いわけじゃない。だけど、そのような貧乏→新しい仕事→新しい男→また辞めて放浪→新しい仕事→新しい男→貧乏のループが第一部、第二部、第三部とすべて同じように繰り返されるのである。この「無限ループ」から読者も抜け出せないのだ。
何しろ文庫本でも545ページもあるので、この無限ループを読み進めるのが苦しくなってくる。バカバカしい気もしてくる。ところどころに挿入される詩も、最初は新鮮だが次第に飽きてくる。それが『放浪記』なんだけど、第一部発売当時に大ベストセラーになった。その当時は無名女性の日記なので(一部では新人作家として知られてきていたが)、どっちかと言えば「カフェ女給が書いた」というスキャンダラスな本として売れたんじゃないか。
しかし、林芙美子は天性の放浪者であると同時に、天性の詩人だった。自分は美人じゃなく、もっと美しかったら仕事も恵まれていたとよく書いている。仕事としては確かに今以上にルッキズムがはびこっていただろう。だけど、文学志向、芸術志向の青年たちと続々と恋愛しているのは、どこか只者では無い雰囲気があったんだと思う。だがその文学志向が「良妻」になることを妨げ、中には暴力を振るったりする男もいる。仕事を投げ出して詩を書いていても、トコトン貧乏になっていくだけ。さらに母や義父が飛び込んできたりする。貧窮の中でも「文学」に取り憑かれてしまったのが林芙美子という女性だった。


林芙美子の実人生に関しては、ここでは書かないことにする。前にも書いたが、尾道の女学校の教師がよくぞ才能を見出して励ましたものである。貧窮の中で魂の叫びを発したが、それは「プロレタリア文学」ではない。プロレタリア陣営からは批判されたりもしたが、今でも読まれているのは林芙美子の方である。林芙美子が本格的な作家になったことをよく示すのが、『トランク』という作品集である。中国、フランス、ソ連についての小説が収録されている。戦時中の文章には戦争協力の跡があって痛ましいが、豊かな物語性が今も生きている作品が多い。『林芙美子随筆集』も面白いが、どうも随筆や旅行記だからと言って必ずしも「事実そのまま」ではない場合もあるらしい。これで林芙美子は終わりだが、関連本がまだ残っている。










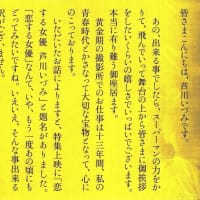
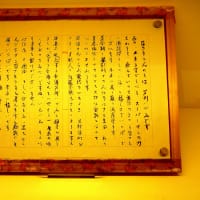








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます