映画監督の大林宣彦(おおばやし・のぶひこ)が亡くなった。4月10日、82歳。亡くなったのは、奇しくも遺作の「海辺の映画館ーキネマの玉手箱」の公開予定日だったが、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言で延期になった。一体いつになったら見られるんだろうか。ガンで闘病中で余命宣告を受けていたのは公表されていた。だから驚きはなく、むしろ「花筺」(はながたみ)と「海辺の映画館」と最後に集大成的な作品が二つも作られたことに感謝である。
 (大林宣彦)
(大林宣彦)
大林宣彦は僕の世代にとって特別な映画監督(の一人)だ。溝口、小津などの巨匠は名前を知ったときにはずいぶん前に亡くなっていた。黒澤明は存命だったが、数年に一本大作を撮る人で全盛期は過ぎていた。大林監督は1938年生まれと世代的には年長だが、商業映画デビューは1977年の「HOUSE ハウス」だから、デビュー作から見ているのである。そして70年代から80年代に大きな影響力を持った角川映画でも撮ってヒット作を連発した。角川文庫と連動した「ねらわれた学園」(1981)や「時をかける少女」(1983)など僕らの世代は大体見てるんじゃないか。もちろんテーマ曲も歌えるだろう。
 (「時をかける少女」)
(「時をかける少女」)
そういう人は他分野を見ても数少ないと思う。ただ大林監督は有名になりすぎたかもしれない。故郷の尾道を舞台に撮り続けたことで、「ふるさと創生」の代名詞のようになりマスコミや大企業にも受けてしまった。社会批判色が少なかったので、広告などにも起用されやすかった。それが僕には残念だったが、最晩年になって大震災後に今度はまた変わったと思う。反戦のメッセージを次代に残そうと努め、映像技法的にも自由奔放な映画を作り始めた。そこがやはり偉大な映像作家だった証だ。
大林監督はもともと個人映画の作家として有名だった。上映される機会は少なかったが、時々池袋の文芸地下(今の新文芸坐の敷地に洋画専門の文芸坐があり、日本映画専門の文芸地下は下にあった)でやっていた。それらの映画は独特な長い名前を持ち、不思議に懐かしい思い出のような映像が魅力的だった。「Complexe=微熱の玻璃あるいは悲しい饒舌ワルツに乗って葬列の散歩道」(1964)、「EMOTION=伝説の午後・いつか見たドラキュラ」(1966)、「CONFESSION=遥かなるあこがれギロチン恋の旅」(1968)などである。これが面白くて、僕は名前を記憶することになった。
これらの映画は当時は自分で8ミリ映写機を回して撮影して編集するもので、そういう映画を作っていた人は当時は非常に珍しかった。それが認められ、CMディレクターとなり大活躍する。日本映画の海外ロケも珍しい時代だが、CMなら海外スターを起用できるとチャールズ・ブロンソンの男性用整髪料「マンダム」が大評判となった。「丹頂」から社名を「マンダム」に変えてしまったぐらいだ。他にも上原謙、高峰三枝子の「国鉄フルムーン」、山口百恵・三浦友和の「グリコアーモンドチョコレート」、ソフィア・ローレンの「ホンダ・ロードパル」、「レナウン・ワンサカ娘」など評判になったCMをいっぱい作っている。
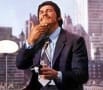 (「マンダム」)
(「マンダム」)
そこで満を持して商業映画を撮ることになって、当時の流行でもあったホラー、パニック映画の「HOUSE ハウス」(1977)を東宝で製作した。批評家受けは悪くて、キネ旬ベストテンでは21位だったが、僕はとても面白くてその年のベストワンである。少女たちが家に食べられてしまうという話をポップな感覚で撮っている。今思えばガーリーなファンタジーとして先駆的な作品で、影響を受けた若い世代が後にたくさん出てくる。次が「ブラックジャック」を映画化した「瞳の中の訪問者」だが面白くなかった。主演が片平なぎさだから見たんだけど。その後段々判ってくるけど、原作があってヒットを期待される時期に公開される映画ほど面白くない。やはり「個人映画」の作家なのだった。
 (HOUSE」)
(HOUSE」)
転機になったのは、1982年の「転校生」。2017年にフィルムセンターで再見した時のことは「大林宣彦『転校生』を35年ぶりに見る」に書いたので、ここでは省略する。ベストテン3位に入選し、初めて高く評価された。「尾道三部作」の最初で、山中恒原作だがほとんど自由に作っている。ATGで製作して大手じゃなかったのが良かった。次が角川の「時をかける少女」(1983)で、原田知世主演で大ヒットした。原作は筒井康隆のジュブナイルSFだが、何度も映像化されている中で一番いいだろう。あの頃僕らは「ラベンダーの香り」と言われても、謎めいて判らなかったのだ。
 (「さびしんぼう」)
(「さびしんぼう」)
尾道三部作の最後が「さびしんぼう」(1985)だが、ノスタルジックなムードが最高と言える作品で、僕は大林作品の最高傑作レベルだと思う。「ふたり」(1991)「あした」(1995)「あの、夏の日~とんでろ じいちゃん~」(1999)を「新尾道三部作」と言うが、やはり最初の方がずっといいと思う。僕らも、監督も飽きたのかもしれない。「ふたり」はとてもいいと思ったが、どうも既視感が次第に強くなった。これらの尾道映画は「観光映画」ではなく、何気ない日常を撮ることで、全体として懐かしいムードを作り出し「ロケ聖地めぐり」の先駆けとなった。その功績は非常に大きい。
作品が多くて長くなっているが、わざわざ16ミリで撮影した「廃市」(1984)は忘れがたい。福永武彦の傑作短編の映画化で、福岡県柳川の堀割を古びた町のムードを満喫した。もっとも数年前に再見したら、ちょっとガッカリしたところもあった。もっと大傑作に思い込んでいた。時間経過による思い込みの美化である。もう一つ、ノスタルジー映画ではないが、個人的な思いで作った「北京的西瓜」(1989)がある。中国人留学生のお世話に奔走する千葉県船橋の八百屋を描く。ちょうど天安門事件にぶつかり、中国ロケが出来なかった。あまり取り上げられないが、非常に特別な価値がある映画だと思う。
 (「廃市」)
(「廃市」)
残りは簡単にしたいが、原作映画化として「異人たちとの夏」(1988)、「青春デンデケデケデケ」(1992)、「はるか、ノスタルジイ」(1993)、「女ざかり」(1994)、「理由」(2004)などがある。「異人たちとの夏」は高く評価されたが、僕は設定に納得できない。素晴らしいのは「青春デンデケデケデケ」で、芦原すなおの直木賞受賞作を実にうまく映像化した。四国の高校生のバンド映画だが、ベンチャーズ世代なのである。これを見ると、やはり大林映画のキモは「失われゆく青春へのノスタルジー」にある。丸谷才一の話題作「女ざかり」は吉永小百合主演だが全然面白くなかった。
 (「青春デンデケデケデケ」
(「青春デンデケデケデケ」
「SADA」(1998)という映画はベルリン映画祭で受賞したというので、一応見に行ったが面白くなかった。阿部定の映画なんだけど、大島渚、田中登に付け加えるところはなかったと思う。こうして次第に面白くない映画が多くなってしまい、「なごり雪」(2002)や「22歳の別れ」(2007)などは見逃した。そして大震災後に「この世の花ー長岡花火物語」(2012)、「野のなななのか」(2014)、「花筺」(2017)、「海辺の映画館~キネマの玉手箱~」(2020)の、いわば「山崎紘菜四部作」が作られた。その評価はまだ僕には出来ない感じだ。「海辺の映画館」を見られてからじっくり考えたい。
ずっと追ってきたので長くなってしまった。青春時代からずっと見ていた監督で、ひたすら画面に夢中になって切ない思いに浸ってきた。まだ書きたい映画も残っているぐらい、作品数が多い。全部見た人はいないんじゃないだろうか。特集上映が行われ、また映画館のスクリーンで見られる日を待ち望んでいる。長い間素晴らしき映画を作り続けた大林監督に感謝したいと思う。
 (大林宣彦)
(大林宣彦)大林宣彦は僕の世代にとって特別な映画監督(の一人)だ。溝口、小津などの巨匠は名前を知ったときにはずいぶん前に亡くなっていた。黒澤明は存命だったが、数年に一本大作を撮る人で全盛期は過ぎていた。大林監督は1938年生まれと世代的には年長だが、商業映画デビューは1977年の「HOUSE ハウス」だから、デビュー作から見ているのである。そして70年代から80年代に大きな影響力を持った角川映画でも撮ってヒット作を連発した。角川文庫と連動した「ねらわれた学園」(1981)や「時をかける少女」(1983)など僕らの世代は大体見てるんじゃないか。もちろんテーマ曲も歌えるだろう。
 (「時をかける少女」)
(「時をかける少女」)そういう人は他分野を見ても数少ないと思う。ただ大林監督は有名になりすぎたかもしれない。故郷の尾道を舞台に撮り続けたことで、「ふるさと創生」の代名詞のようになりマスコミや大企業にも受けてしまった。社会批判色が少なかったので、広告などにも起用されやすかった。それが僕には残念だったが、最晩年になって大震災後に今度はまた変わったと思う。反戦のメッセージを次代に残そうと努め、映像技法的にも自由奔放な映画を作り始めた。そこがやはり偉大な映像作家だった証だ。
大林監督はもともと個人映画の作家として有名だった。上映される機会は少なかったが、時々池袋の文芸地下(今の新文芸坐の敷地に洋画専門の文芸坐があり、日本映画専門の文芸地下は下にあった)でやっていた。それらの映画は独特な長い名前を持ち、不思議に懐かしい思い出のような映像が魅力的だった。「Complexe=微熱の玻璃あるいは悲しい饒舌ワルツに乗って葬列の散歩道」(1964)、「EMOTION=伝説の午後・いつか見たドラキュラ」(1966)、「CONFESSION=遥かなるあこがれギロチン恋の旅」(1968)などである。これが面白くて、僕は名前を記憶することになった。
これらの映画は当時は自分で8ミリ映写機を回して撮影して編集するもので、そういう映画を作っていた人は当時は非常に珍しかった。それが認められ、CMディレクターとなり大活躍する。日本映画の海外ロケも珍しい時代だが、CMなら海外スターを起用できるとチャールズ・ブロンソンの男性用整髪料「マンダム」が大評判となった。「丹頂」から社名を「マンダム」に変えてしまったぐらいだ。他にも上原謙、高峰三枝子の「国鉄フルムーン」、山口百恵・三浦友和の「グリコアーモンドチョコレート」、ソフィア・ローレンの「ホンダ・ロードパル」、「レナウン・ワンサカ娘」など評判になったCMをいっぱい作っている。
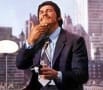 (「マンダム」)
(「マンダム」)そこで満を持して商業映画を撮ることになって、当時の流行でもあったホラー、パニック映画の「HOUSE ハウス」(1977)を東宝で製作した。批評家受けは悪くて、キネ旬ベストテンでは21位だったが、僕はとても面白くてその年のベストワンである。少女たちが家に食べられてしまうという話をポップな感覚で撮っている。今思えばガーリーなファンタジーとして先駆的な作品で、影響を受けた若い世代が後にたくさん出てくる。次が「ブラックジャック」を映画化した「瞳の中の訪問者」だが面白くなかった。主演が片平なぎさだから見たんだけど。その後段々判ってくるけど、原作があってヒットを期待される時期に公開される映画ほど面白くない。やはり「個人映画」の作家なのだった。
 (HOUSE」)
(HOUSE」)転機になったのは、1982年の「転校生」。2017年にフィルムセンターで再見した時のことは「大林宣彦『転校生』を35年ぶりに見る」に書いたので、ここでは省略する。ベストテン3位に入選し、初めて高く評価された。「尾道三部作」の最初で、山中恒原作だがほとんど自由に作っている。ATGで製作して大手じゃなかったのが良かった。次が角川の「時をかける少女」(1983)で、原田知世主演で大ヒットした。原作は筒井康隆のジュブナイルSFだが、何度も映像化されている中で一番いいだろう。あの頃僕らは「ラベンダーの香り」と言われても、謎めいて判らなかったのだ。
 (「さびしんぼう」)
(「さびしんぼう」)尾道三部作の最後が「さびしんぼう」(1985)だが、ノスタルジックなムードが最高と言える作品で、僕は大林作品の最高傑作レベルだと思う。「ふたり」(1991)「あした」(1995)「あの、夏の日~とんでろ じいちゃん~」(1999)を「新尾道三部作」と言うが、やはり最初の方がずっといいと思う。僕らも、監督も飽きたのかもしれない。「ふたり」はとてもいいと思ったが、どうも既視感が次第に強くなった。これらの尾道映画は「観光映画」ではなく、何気ない日常を撮ることで、全体として懐かしいムードを作り出し「ロケ聖地めぐり」の先駆けとなった。その功績は非常に大きい。
作品が多くて長くなっているが、わざわざ16ミリで撮影した「廃市」(1984)は忘れがたい。福永武彦の傑作短編の映画化で、福岡県柳川の堀割を古びた町のムードを満喫した。もっとも数年前に再見したら、ちょっとガッカリしたところもあった。もっと大傑作に思い込んでいた。時間経過による思い込みの美化である。もう一つ、ノスタルジー映画ではないが、個人的な思いで作った「北京的西瓜」(1989)がある。中国人留学生のお世話に奔走する千葉県船橋の八百屋を描く。ちょうど天安門事件にぶつかり、中国ロケが出来なかった。あまり取り上げられないが、非常に特別な価値がある映画だと思う。
 (「廃市」)
(「廃市」)残りは簡単にしたいが、原作映画化として「異人たちとの夏」(1988)、「青春デンデケデケデケ」(1992)、「はるか、ノスタルジイ」(1993)、「女ざかり」(1994)、「理由」(2004)などがある。「異人たちとの夏」は高く評価されたが、僕は設定に納得できない。素晴らしいのは「青春デンデケデケデケ」で、芦原すなおの直木賞受賞作を実にうまく映像化した。四国の高校生のバンド映画だが、ベンチャーズ世代なのである。これを見ると、やはり大林映画のキモは「失われゆく青春へのノスタルジー」にある。丸谷才一の話題作「女ざかり」は吉永小百合主演だが全然面白くなかった。
 (「青春デンデケデケデケ」
(「青春デンデケデケデケ」「SADA」(1998)という映画はベルリン映画祭で受賞したというので、一応見に行ったが面白くなかった。阿部定の映画なんだけど、大島渚、田中登に付け加えるところはなかったと思う。こうして次第に面白くない映画が多くなってしまい、「なごり雪」(2002)や「22歳の別れ」(2007)などは見逃した。そして大震災後に「この世の花ー長岡花火物語」(2012)、「野のなななのか」(2014)、「花筺」(2017)、「海辺の映画館~キネマの玉手箱~」(2020)の、いわば「山崎紘菜四部作」が作られた。その評価はまだ僕には出来ない感じだ。「海辺の映画館」を見られてからじっくり考えたい。
ずっと追ってきたので長くなってしまった。青春時代からずっと見ていた監督で、ひたすら画面に夢中になって切ない思いに浸ってきた。まだ書きたい映画も残っているぐらい、作品数が多い。全部見た人はいないんじゃないだろうか。特集上映が行われ、また映画館のスクリーンで見られる日を待ち望んでいる。長い間素晴らしき映画を作り続けた大林監督に感謝したいと思う。


















