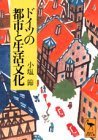 先日、早めの夏休みをとって駆け足でドイツをめぐってきた。ドイツ語は勿論のこと、英語もできないのであれば旅行会社のツアーに頼るしかないのが情けない。5年前のドイツ旅行は、音楽と美術鑑賞に目的をしぼりドレルデンとベルリンが中心だったので、今回は観光のための旅行で、景色の風光明媚を楽しめる季節を選び、ハイデルベルク、ローテンブルク、ミュンヘン、ハンザ、ワイマール、ドレスデン、ベルリンと大型バスでドイツのアウト・バーンをひたすら走りめぐった全日程8日間の旅。世界遺産でなくてもどの街も清潔で美しく整っているのがドイツの都市の特徴である。
先日、早めの夏休みをとって駆け足でドイツをめぐってきた。ドイツ語は勿論のこと、英語もできないのであれば旅行会社のツアーに頼るしかないのが情けない。5年前のドイツ旅行は、音楽と美術鑑賞に目的をしぼりドレルデンとベルリンが中心だったので、今回は観光のための旅行で、景色の風光明媚を楽しめる季節を選び、ハイデルベルク、ローテンブルク、ミュンヘン、ハンザ、ワイマール、ドレスデン、ベルリンと大型バスでドイツのアウト・バーンをひたすら走りめぐった全日程8日間の旅。世界遺産でなくてもどの街も清潔で美しく整っているのがドイツの都市の特徴である。本旅行の目的を果たし、楽しき日々は過ぎ去り、、、しかし、つくづく感じたのが、私にはこういう一般の観光旅行は向かないということだ。もっとじっくり、城やゲーテの館や資料館で過ごしたいと願いつつ、ただただ通り過ぎただけの旅行だったような気がする。もっとドイツのことを知りたいと手にとったのが本書。(多分、あと2年は私のドイツ探索は続くはず。)
フランスやイタリアも絶対に訪問したいと少ない給料からせっせとへそくりを貯めているのだが(まだ貯め込むまではいかない)、ドイツにはまた別のある種の憧れがある。一緒に戦争を戦ったという負の歴史や、明治以来、医学や法学など兄貴分としてドイツにせっせと学んできた日本人としての歴史もあるが、旧制中学、旧制高校で涵養された多くの先輩たちからの「ドイツ」の教養の影響も受けている最後の世代かもしれない。著者の小塩節氏は信州の松本、旧制松本高校で学ぶ。高校の先輩には北杜夫や辻邦生!(←昭和23年から36年までおふたりの書簡集「若き日の友情―辻邦生・北杜夫 往復書簡」が、最近、新潮社から出版された。)がいて、トーマス・マンやリルケ、ヘッセが近くにいるような幸福な学生生活を送った。この旧制高校の存在もポイント。寮の向かいには哲学者の森有正、同級生ののちに映画監督になる熊井啓たちと一緒に山を登るうちに、とうとうドイツ精神への山登りに一生を賭けることになったという。
文庫本向けの書き下ろしということで、ドイツのみならずウィーン、モーツァルトなど、著者の筆がすすむままに、ドイツ文学者によるドイツ東西統一されたばかりの当時の新生ドイツからの都市と生活文化を記した本ではあるが、それこそあらゆる外国生活や文化を紹介する本は巷に溢れているが、それらの本とは本書は一線を画す。元アナウンサーで現在パリに住んでいらっしゃる雨宮塔子さんが雑誌に連載されている「雨宮塔子のパリの酸いも甘いもパリ風味」もなかなか素敵で私は好きなのだが、やはりそれは女子的お洒落なレベルだからこそ受けるのであって、有名人の「ブログ」に過ぎない。文化を語るには、その人に本物の文化人の厚みが必要になる。
ドイツの気候、歴史、ビジネススタイル、暮らしとドイツ人とドイツの語りを最初は軽い気持ちで流しながら、私はその文章に小塩氏の深い教養のエッセンスを感じてしばし立ち止まり、じっくりと真剣に一文一文を心に刻むようになった。
「フランケンの白の辛口がいい。ワインは人を朗らかにする。その晴朗さは、モーツァルトと詩人ゲーテの世界だ」
この平易な一言に、軽やかな語り口に、私はドイツで呑んだ白ワインを思い出し、楽しく酔えた。
そしてドイツの暮らしを知るうちに考えさせられたのが、わが日本と日本人の生活事情だ。それぞれにはそれぞれの家庭の事情があり、隣のご家庭をうらやんでも仕方がないのだが、我々日本人は本当に豊かな生活を送っているのか、ということだ。ドイツ生活にも不便なことも多くあり、ドイツ人気質にも受け入れがたい部分もある。それでも、ドイツでの暮らしは日本よりよいのではと思ってしまうのである。ドイツのケルン放送交響楽団の主席コントラバス奏者の河原泰則氏は私も大好きな演奏家だが、以前、雑誌に掲載されていた郊外にある河原邸を訪問したご友人の感想を思い出した。室内では暖炉の薪がはぜる音だけが静かに聞こえ、一面ガラスの窓の向こうには純白の雪に覆われた森がひろがり、時々鹿が遊びにやってくる。これがドイツの芸術家の暮らしか・・・と、そのご友人は感じたそうだ。芸術家ではなくても、この地では平凡な日々の中に静かで豊かな暮らしが送れそうだ。
最後の余暇について、著者は余暇は人生を豊かにする最大の課題として、職場中心の生活から、時間的にも空間的にも「個人の生活」「個人の時間」をより重視するバランスのとれた生活転換を勧めている。怠けろ、というのではなく、バランスをとることによって豊かな人間を生み出す貴重な時間をつくることである。
20年近くの前の提案だが、これこそまさに、近年言われている「ワーク・ライフ・バランス」ではないか。職場でも「ワーク・ライフ・バランス」を求められているが、そもそも現状の体制では無理!日本のように多くの機能が東京に集中し、通勤時間が1時間超当たり前、少ない休暇、余暇の環境が貧弱、とそうそう簡単に過剰なワークからライフへの転換はできない理由もあるが、太平洋戦争がはじまる前、日本で初めて「生活文化」という言葉を積極的に使った哲学者の三木清も、非国民として獄中死しているお国柄である。それが日本なのである。
「明朗で、健康で、また能率的な生活は美しい」
と三木清は記しているが、何故ドイツ人ではできて、日本人はできないのか、という著者の問いは、自らの日々の生活の事業仕分けの必要を痛感する。
近頃、厚生労働省雇用均等・児童家庭局から政府主導の「イクメンプロジェクト」なるものが発足し、男性の育児参加も強く望まれているのだが、はたして現実的に男性が育児休暇を取れるのだろうか。私だったら、なかなかコワクテとれないと思う。私がドイツに憧れる理由、それは深い精神性に基づいた真に豊かな人生をおくりたいという願望からだということにも気づかされたのも本書による。











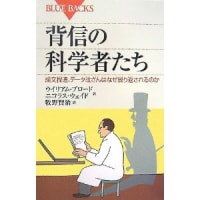

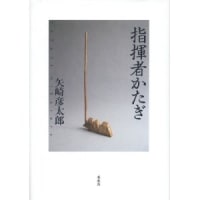
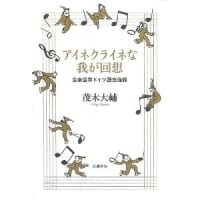
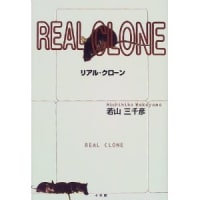
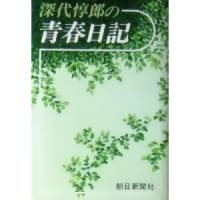
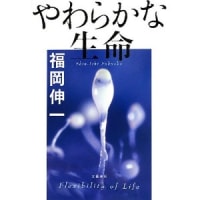
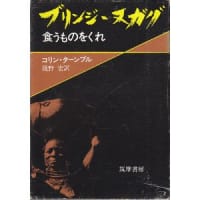
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます