校閲の目 いろはかるた
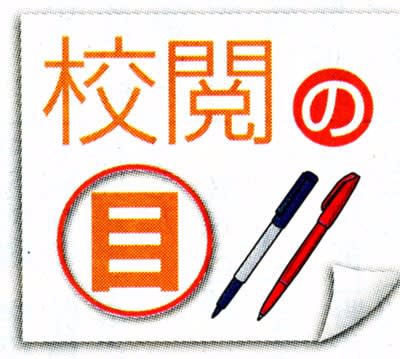
かつてお正月といえば、すごろく、こま回し、いろはかるたでした。
「かるた」はポルトガル語で、英語では「カード」、ドイツ語では病院の「カルテ」、フランスに行けば「アラカルト」の「カルト」と変わります。語源は「紙片」です。日本では歌留多、加留多、骨牌の字があてられてきました。外来語ですが新聞では「たばこ」や「かっぱ」のように平仮名で書きます。

かるたで有名なのが「犬も歩けば棒に当たる」から始まる江戸の「犬棒かるた」です。用もないのにうろうろ動き回っていると災難にあうことでしたが、江戸中期から「思いがけない幸運をつかむ」という意味も持つようになりました。
ことわざや慣用句に出てくる犬は、「犬の遠ぼえ」「犬も食わぬ」「犬に論語」「負け犬」「権力の犬」「犬死に」などさんざんな使われようです。
「猫」「猿」などの偏は「けもの偏」で、犬の字の変形です。『新字源』などによれば、犬が囲いを飛び出し人にかみつくことから「犯」、手におえない犬は「狂」、ほかに「狡い(ずるい)」や「猜む(そねむ)」など、うんざりするような漢字が並びますが、それだけ人と犬との関係が深いことを表しています。
ペットの犬はかわいいし、介助犬や盲導犬、聴導犬、災害救助犬に警察犬、セラピードッグなど社会に役立つ犬はたくさんいます。貢献の献にも犬の字が使われています。
(河邑哲也)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年1月9日付掲載
僕も、子どものころは、お正月と言えば、「かるた」「凧あげ」「こま回し」でしたね。
大人と違って、「冬休み中」までが「お正月」だったので、よく遊んだものです。
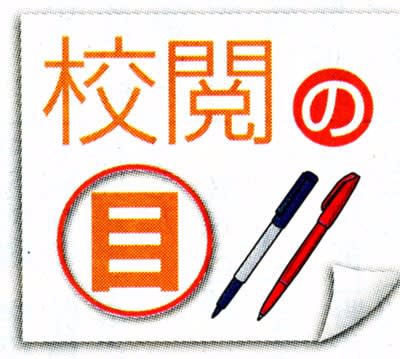
かつてお正月といえば、すごろく、こま回し、いろはかるたでした。
「かるた」はポルトガル語で、英語では「カード」、ドイツ語では病院の「カルテ」、フランスに行けば「アラカルト」の「カルト」と変わります。語源は「紙片」です。日本では歌留多、加留多、骨牌の字があてられてきました。外来語ですが新聞では「たばこ」や「かっぱ」のように平仮名で書きます。

かるたで有名なのが「犬も歩けば棒に当たる」から始まる江戸の「犬棒かるた」です。用もないのにうろうろ動き回っていると災難にあうことでしたが、江戸中期から「思いがけない幸運をつかむ」という意味も持つようになりました。
ことわざや慣用句に出てくる犬は、「犬の遠ぼえ」「犬も食わぬ」「犬に論語」「負け犬」「権力の犬」「犬死に」などさんざんな使われようです。
「猫」「猿」などの偏は「けもの偏」で、犬の字の変形です。『新字源』などによれば、犬が囲いを飛び出し人にかみつくことから「犯」、手におえない犬は「狂」、ほかに「狡い(ずるい)」や「猜む(そねむ)」など、うんざりするような漢字が並びますが、それだけ人と犬との関係が深いことを表しています。
ペットの犬はかわいいし、介助犬や盲導犬、聴導犬、災害救助犬に警察犬、セラピードッグなど社会に役立つ犬はたくさんいます。貢献の献にも犬の字が使われています。
(河邑哲也)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年1月9日付掲載
僕も、子どものころは、お正月と言えば、「かるた」「凧あげ」「こま回し」でしたね。
大人と違って、「冬休み中」までが「お正月」だったので、よく遊んだものです。














