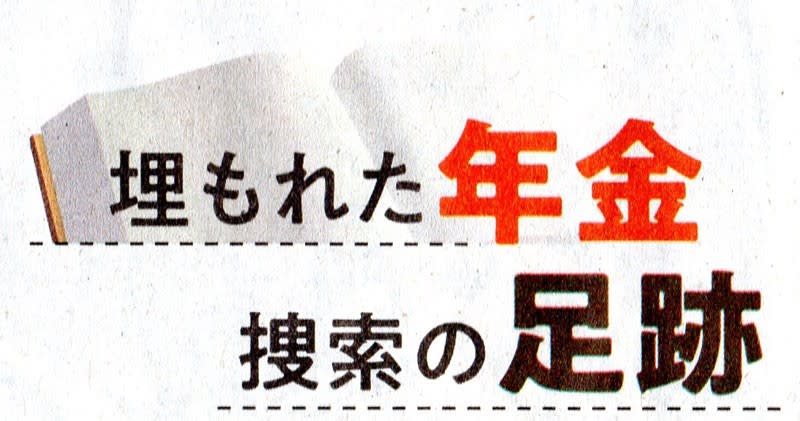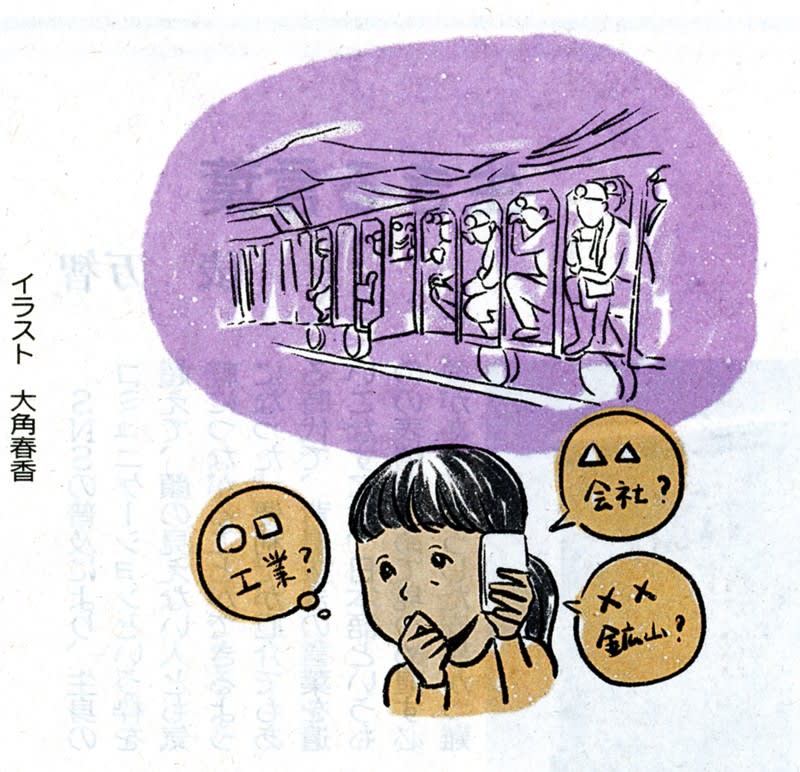第50回「視点」展 伝統を継承し新たな50年へ
金井紀光
日本リアリズム写真集団(JRP)が主催する、全国公募写真展「視点」は1976年に創設されました。東京・上野の都立美術館での本展をはじめ、全国数カ所で巡回展が開催される、日本最大規模の公募写真展です。
50回の節目を迎えた今年は、応募者数683名、作品数1348、作品枚数2850枚でした。多くの方が応募してくださるのは、半世紀にわたる伝統の重みではないでしょうか。選考は、写真家の宇井眞紀子さん、同じく清水哲朗さんのお二人をゲストに、日本リアリズム写真集団側から3名が参加して行いました。その結果、242作品、686枚の入賞、入選作品が決定しました。

久保村厚「リニアが通る村」(カラー6枚組)
見せる工夫
視点賞、久保村厚さんの「リニアが通る村」(カラー6枚組)は、難しいテーマへ果敢に挑戦した意欲作です。バックミラーに写るダンプカー、重苦しいトーンの中に際立つ誘導員の赤い旗など、見せるための工夫があり単なる工事の状況説明ではなく、作者独自の視点を示しています。先の見通せないこの問題を、表現することに成功しています。
奨励賞、藤田篤男さんの「送電線は何処ヘ―福島の14年―」(カラー5枚組)は、原発事故の問題を送電線に焦点をあてて表現した作品です。福島第1原発でつくった電気のほとんどが、東京を中心とした首都圏で使われていたことはよく知られています。この作品はそれを可視化したものでしょう。山中にそびえる鉄塔や張りめぐらされた電線が見る者に迫ります。原発を含め、エネルギーの問題をどうするのか、一人一人に突きつけているようです。
同賞、中野光代さんの「お兄ちゃん」(カラー4枚組)は、兄になったばかりの少年の自覚と戸惑いの表情から、家族の絆が感じられ印象的です。心温まる作品になりました。同賞、若林茂さんの「母患う」(カラー4枚組)は、年齢を重ねた母への慈しみが簡潔に表現されています。
50回記念特別賞として英伸三選考委員により、なかにしみつほさんの「日々折々―絵本作家ねっこかなご」(カラー5枚組)が選ばれました。絵本作家の凛とした日常が淡々と、季節を感じさせながらさりげなく描かれています。この作家の絵本を見たいという気持ちにさせます。

中野光代「お兄ちゃん」(カラー4枚組)
若者の表現
ヤング賞、高浜蓮さんの「負けないで」(モノクロ単写真)や、準ヤング賞、吉岡來美さん「秘密」(カラー単写真)などは、友人を撮ったものと思われる作品でした。若者らしい発想、表現で、撮影者と撮られる側との会話が聞こえてきそうで好感が持てました。ヤング部門には、「視点」展への応募常連のお孫さんや親族が応募されるケースが何点かありました。こうして本展の伝統が継承され、次の世代へつながっていくことに期待します。
今年の入賞作品には暗く重い題材の写真が多い印象ですが、これは、今の日本社会の現実を率直に見つめた結果でしょう。忘れてはいけない大事なことが、ともするとニュース価値がないと判断されがちです。「視点」展は、日々新しい話題を追いかけていくSNSなどとは対極の、ていねいに撮り続け、伝えていく世界です。作品発表の場であると同時に、社会へ発信する場です。今回の「視占心展を機に、その役割、立ち位置を再確認し、新たな50年を目指します。
(かない・のりみつ 第50回「視点」展委員長・選考委員)
*6~13日、東京都美術館(上野公園内)03(3823)6921。仙台、兵庫、三重、富山に巡回
「しんぶん赤旗」日刊紙 2025年5月30日付掲載
視点賞、久保村厚さんの「リニアが通る村」(カラー6枚組)は、難しいテーマへ果敢に挑戦した意欲作。バックミラーに写るダンプカー、重苦しいトーンの中に際立つ誘導員の赤い旗など、見せるための工夫があり単なる工事の状況説明ではなく、作者独自の視点を示しています。先の見通せないこの問題を、表現することに成功。
ヤング部門には、「視点」展への応募常連のお孫さんや親族が応募されるケースが何点かありました。こうして本展の伝統が継承され、次の世代へつながっていくことに期待。
金井紀光
日本リアリズム写真集団(JRP)が主催する、全国公募写真展「視点」は1976年に創設されました。東京・上野の都立美術館での本展をはじめ、全国数カ所で巡回展が開催される、日本最大規模の公募写真展です。
50回の節目を迎えた今年は、応募者数683名、作品数1348、作品枚数2850枚でした。多くの方が応募してくださるのは、半世紀にわたる伝統の重みではないでしょうか。選考は、写真家の宇井眞紀子さん、同じく清水哲朗さんのお二人をゲストに、日本リアリズム写真集団側から3名が参加して行いました。その結果、242作品、686枚の入賞、入選作品が決定しました。

久保村厚「リニアが通る村」(カラー6枚組)
見せる工夫
視点賞、久保村厚さんの「リニアが通る村」(カラー6枚組)は、難しいテーマへ果敢に挑戦した意欲作です。バックミラーに写るダンプカー、重苦しいトーンの中に際立つ誘導員の赤い旗など、見せるための工夫があり単なる工事の状況説明ではなく、作者独自の視点を示しています。先の見通せないこの問題を、表現することに成功しています。
奨励賞、藤田篤男さんの「送電線は何処ヘ―福島の14年―」(カラー5枚組)は、原発事故の問題を送電線に焦点をあてて表現した作品です。福島第1原発でつくった電気のほとんどが、東京を中心とした首都圏で使われていたことはよく知られています。この作品はそれを可視化したものでしょう。山中にそびえる鉄塔や張りめぐらされた電線が見る者に迫ります。原発を含め、エネルギーの問題をどうするのか、一人一人に突きつけているようです。
同賞、中野光代さんの「お兄ちゃん」(カラー4枚組)は、兄になったばかりの少年の自覚と戸惑いの表情から、家族の絆が感じられ印象的です。心温まる作品になりました。同賞、若林茂さんの「母患う」(カラー4枚組)は、年齢を重ねた母への慈しみが簡潔に表現されています。
50回記念特別賞として英伸三選考委員により、なかにしみつほさんの「日々折々―絵本作家ねっこかなご」(カラー5枚組)が選ばれました。絵本作家の凛とした日常が淡々と、季節を感じさせながらさりげなく描かれています。この作家の絵本を見たいという気持ちにさせます。

中野光代「お兄ちゃん」(カラー4枚組)
若者の表現
ヤング賞、高浜蓮さんの「負けないで」(モノクロ単写真)や、準ヤング賞、吉岡來美さん「秘密」(カラー単写真)などは、友人を撮ったものと思われる作品でした。若者らしい発想、表現で、撮影者と撮られる側との会話が聞こえてきそうで好感が持てました。ヤング部門には、「視点」展への応募常連のお孫さんや親族が応募されるケースが何点かありました。こうして本展の伝統が継承され、次の世代へつながっていくことに期待します。
今年の入賞作品には暗く重い題材の写真が多い印象ですが、これは、今の日本社会の現実を率直に見つめた結果でしょう。忘れてはいけない大事なことが、ともするとニュース価値がないと判断されがちです。「視点」展は、日々新しい話題を追いかけていくSNSなどとは対極の、ていねいに撮り続け、伝えていく世界です。作品発表の場であると同時に、社会へ発信する場です。今回の「視占心展を機に、その役割、立ち位置を再確認し、新たな50年を目指します。
(かない・のりみつ 第50回「視点」展委員長・選考委員)
*6~13日、東京都美術館(上野公園内)03(3823)6921。仙台、兵庫、三重、富山に巡回
「しんぶん赤旗」日刊紙 2025年5月30日付掲載
視点賞、久保村厚さんの「リニアが通る村」(カラー6枚組)は、難しいテーマへ果敢に挑戦した意欲作。バックミラーに写るダンプカー、重苦しいトーンの中に際立つ誘導員の赤い旗など、見せるための工夫があり単なる工事の状況説明ではなく、作者独自の視点を示しています。先の見通せないこの問題を、表現することに成功。
ヤング部門には、「視点」展への応募常連のお孫さんや親族が応募されるケースが何点かありました。こうして本展の伝統が継承され、次の世代へつながっていくことに期待。